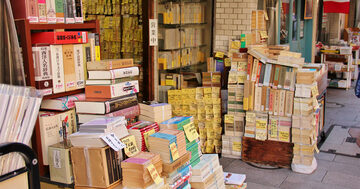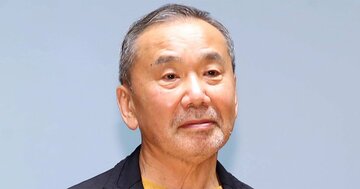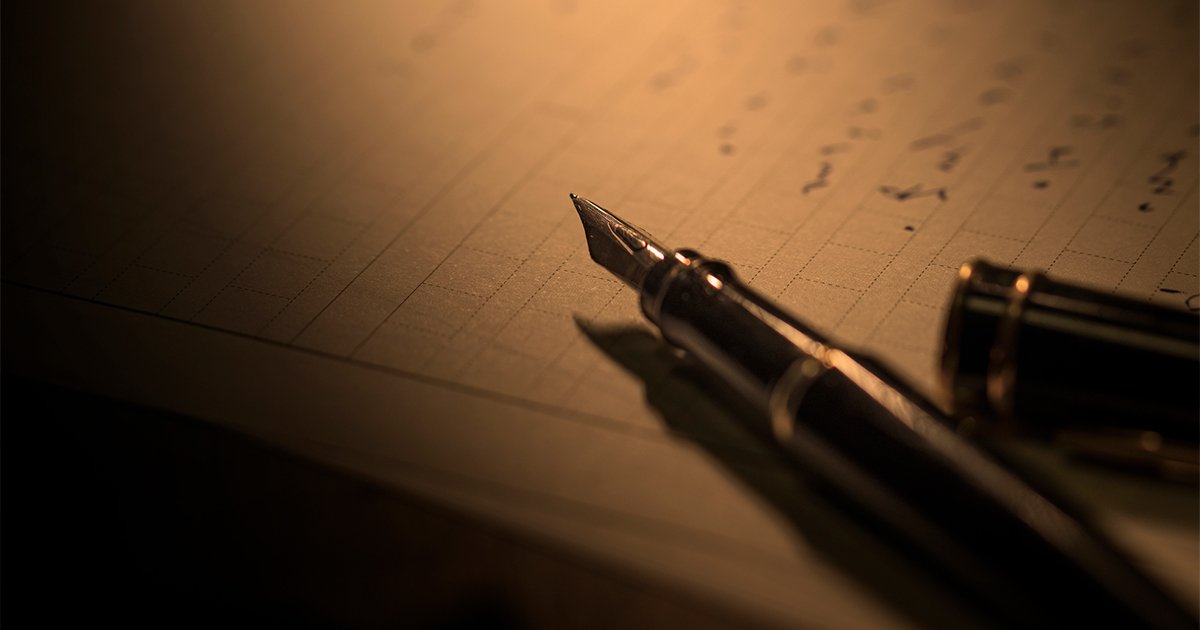 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
明治から大正にかけて、作家と社会をつなぐ“編集者”という職業を切り拓いた滝田樗陰。文芸と時事を行き来しながら、雑誌を通して人々の価値観や社会の変化を映し出した。その姿には、書き手の情熱を引き出し、読者と共有する“出版の原点”がある。現代の編集者・三島邦弘が、その仕事から見出した「出版の本質」とは。※本稿は、編集者の三島邦弘『出版という仕事』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。
『中央公論』をバカ売れさせた
伝説の編集者・滝田樗陰とは?
滝田樗陰。数千部にも満たなかった月刊誌『中央公論』を、倍々に販売部数を伸ばしていった編集者であり、日本有数の出版社へと中央公論社を押し上げた最大の功労者です(以下、杉森久英『滝田樗陰――『中央公論』名編集者の生涯』中公文庫に大きく拠ります)。
「中央公論」は、もともと京都・西本願寺の機関誌から始まった雑誌でした。明治36年(1903年)9月に大学入学をはたした樗陰は、まもなく小欄を担当します。数年後には本格的に関わり出し、以降、文芸作品を雑誌に取り入れます。小説家たちの文章を載せ出したのです。
明治39年10月号には、夏目漱石「二百十日」、島崎藤村「家畜」、国木田独歩「入郷記」を同時に載せ、「世間の視聴をあつめた」と言います。同時に、吉野作造、徳富蘇峰はじめ論壇、オピニオンと言われる文章を併載。こうして「総合雑誌」の先駆けとなっていくのです。
樗陰は、硬派な小説、純文学と天下国家を論じた論説を載せる一方で、雑誌の真ん中に箸休めのような意味合いで、大衆小説も載せます。これが見事に当たり、どんどん部数が伸びていきます。ちなみにその頃の樗陰は、実績契約をしていたため、給料もうなぎのぼりだったそうです。