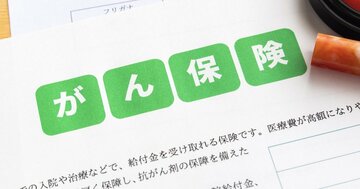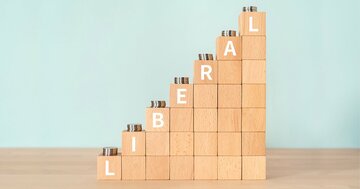養老 「分類学者が集まって酒を飲むと必ずケンカになる」と言われるくらい、「分類」は人間が典型的にケンカする話題のひとつです。キマダラヒカゲを種として分けるべきだとか、分けなくてもいいじゃないかとか。蝶の分類なんて具体的な利害関係のまったくないことですら言い争いになるのだから、抽象的な話題で人がぶつかるのはさもありなんと思います。
強みだった人文学の政治的多様性が
急速に失われている
東 一昔前は「いろんな見方」が論壇誌や学会などで言われていたのですが、いまはみな政治的に正しくなってしまって、なかなか自由には発言できないですね。
茂木 それは面白いね。政治的に正しいことで、科学的な客観性から外れてきている。
東 人文学には、自然科学のような客観性はもともとない。政治的な多様性だけが強みだったのに、それすら急速に失われている。
茂木 ないのか(笑)。
東 これなら学者なんていらないんじゃないのと言われても仕方がないくらい、皆同じことを言うようになってますね。
茂木 そうすると、科学的・客観的な分析は、政治や社会においては無理だということになりますよね。そもそも僕みたいにすっとぼけた自然科学者からすると、戦闘員と非戦闘員を区別して、戦闘員は殺していいという議論もどうなんだと思いますけど。
養老 第一次大戦から総力戦になったからね。
東 それを言うなら「戦争犯罪」という言葉だってかなり謎で、そもそも戦争自体が犯罪だと思います。
養老 そうそう。
東 でも、そういうのもいまは言ってはいけないことになっている。戦争自体が犯罪だと言うと、ロシアの味方かと非難される。
茂木 そうなんですか。政治的な正しさって、かなり問題のある概念ですよね。
東 そうですね。でもそれも言っちゃいけない。人文系アカデミズムはどうなってしまうのでしょうか。まあ、どうにもならず滅びるのかもしれない。
養老 それもまたやむなし(笑)。
茂木 今日において、人文学は政治的正しさと切り離せないということですか。
東 いまはそうなってしまった。就職とか資金提供のシステムとかとも関係しているのだと思います。
茂木 生活に直結しているのか。アメリカの大学の人事で、そのような風潮があるということはときどき耳にしますが、日本でもそうだとすると、なんだか残念な気がします。