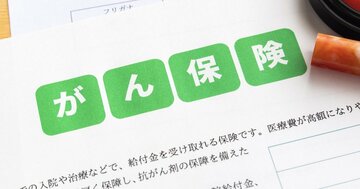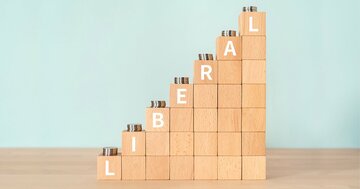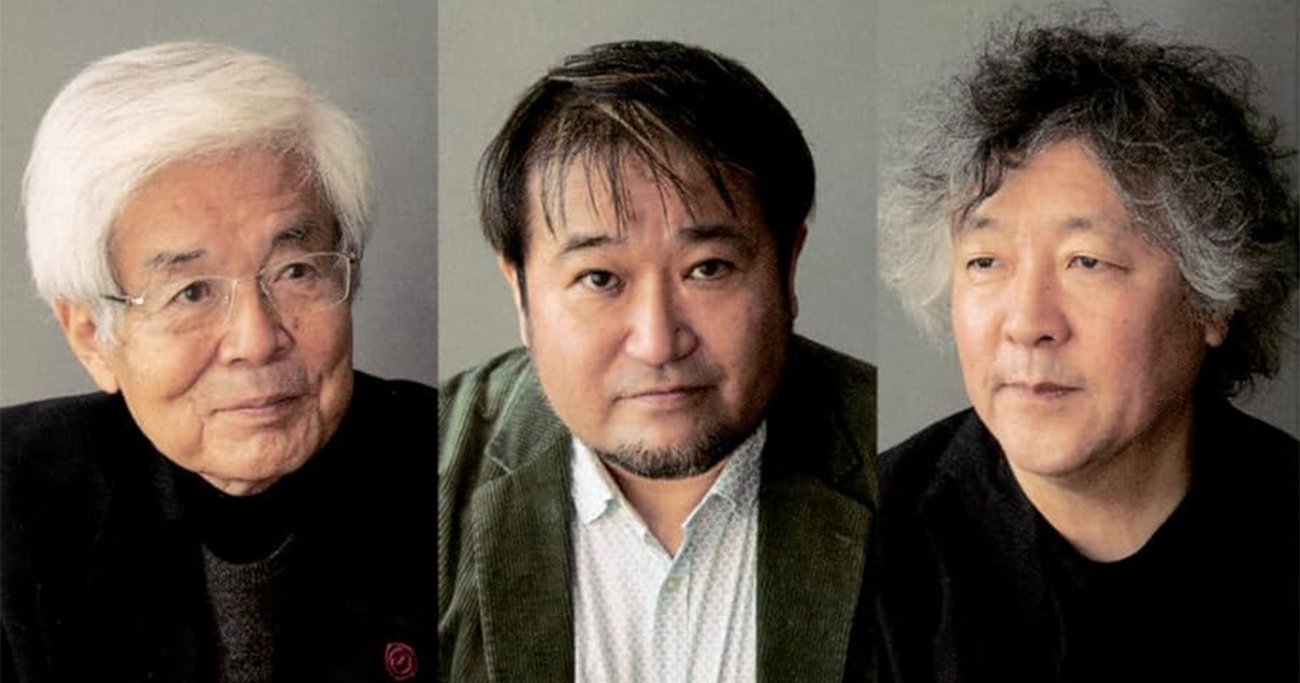
明治維新から150年が過ぎ、終戦から80年になろうとする現代。日本の社会経済体制は、さまざまな制度疲労を来たしている。そんな「歪み」を、養老孟司、茂木健一郎、東浩紀が、徹底的に語り尽くした。今回のテーマは、科学の客観性を軽視し、政治的正しさを掲げて突っ走る社会の危うさだ。※本稿は、養老孟司、茂木健一郎、東 浩紀『日本の歪み』(講談社現代新書)の一部を抜粋・編集したものです。
蝶の分類も国の区別も
思想に左右される
茂木 キマダラヒカゲという蝶がいるのですが、僕が子供の頃に突然、「ヤマキマダラヒカゲ」と「サトキマダラヒカゲ」に種が分裂しました。キチョウも「キタキチョウ」と「ミナミキチョウ」に分かれたのですが、正直、あまり種として分ける意味があるのかどうかわからない。蝶を研究して学生科学展に出したりしていた立場としては、種が変わるのは大地が揺らぐような思いです。オサムシもDNAを調べて種の分類が変わったというのがありましたよね。
養老 DNAを使ったら系統関係の整理がついたんです。しかし、系統関係を現物の分類にどう使うかというのはけっこう主観的で、それを池田清彦が「分類とは思想である」と言っています。
茂木 ロシアとウクライナも、どこまで別の国かはいろんな立場がありますよね。人間の認知は、案外いい加減で恣意的なところがあります。言語についても、ロシア語とウクライナ語は遠いと、半ば政治的な文脈で開戦後に盛んに言われています。東さんはチェルノブイリに何度も行かれていますが、ロシア語とウクライナ語はどんな感じで使われているのですか。
東 チェルノブイリは最初に行ったのが2012年で、最後に行ったのが2019年ですが、キーウ(キエフ)の街中ではそのあいだでも急速にウクライナ語化が進んでいたという印象があります。ただ、僕はロシア語もそれほどできないし、ウクライナ語はぜんぜんできないので、正確なところはよくわかりません。ただ逆に、僕ぐらいわからないと、2言語がかなり似て見えるのは確かです。
茂木 それが開戦後に、ウクライナ語はロシア語よりポーランド語に近いのだというキャンペーンが時に張られるようになった。政治的な意図は明確です。本来、言葉が近かろうがどうだろうが、プーチンの行為が許容されるわけではない。これも一つの歴史過剰であるように思います。
東 ウクライナ語は、現在はロシア語やベラルーシ語などとともに東スラブ語群ということになっています。言語学はつねに政治と結びついているので、分類が変わる可能性もあるんじゃないでしょうか。