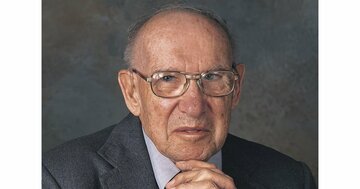ダメな管理職は「自由を与えて苦しめる」、いい管理職は「何を与える」か?
そう語るのは、これまで4000社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「もう誰も言ってくれないことがここに書いてある」と話題の著書『リーダーの仮面』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに「判断軸」を授けている。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、注目のマネジメントスキルを解説する。(構成/種岡 健)
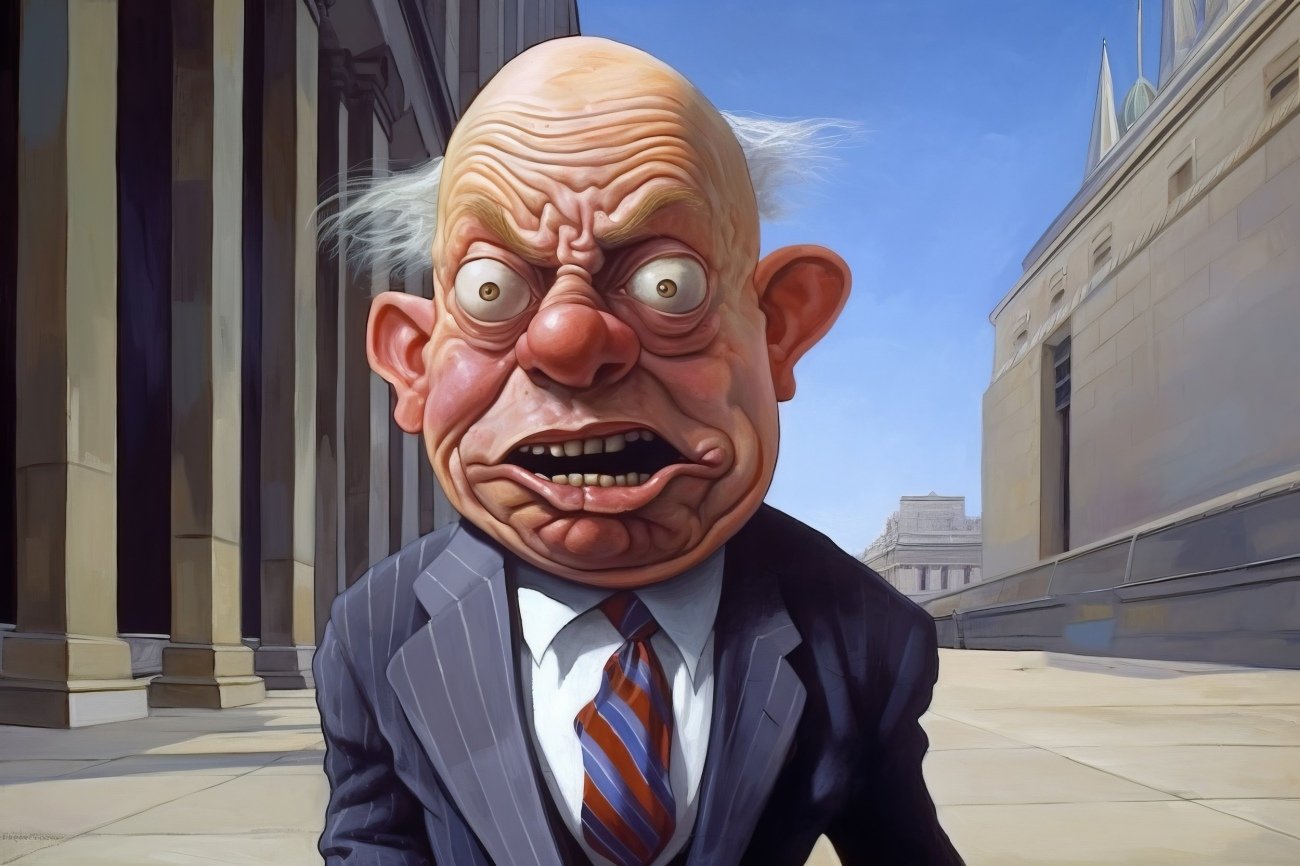 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「自由にしていい」で病む?
「なんでもいいから好きなことをやってください」
と言われて、ストレスを感じないでしょうか。このストレスは人を追い詰めてしまいます。
では、次のような質問に変えればどうでしょう。
「最近、いちばんお金を使ったものは何ですか? それに関連したことをやってください」
どうでしょう。やるべきことが、グッとリアルになりますよね。
管理職がやることとして、もっとも大事なのが、この「ルールを決める」ということです。
いま、日常生活を送っていて、法律にストレスを感じている人はいないでしょう。
たくさんのルールがあるけれど、人々はスムーズに生きている。
逆に、法律がなかったら、世の中はめちゃくちゃになってしまいます。ルールがないと、人は病んでしまいます。
適度なルールを与える人
組織を運営する上で、必ず適度な「ルール」が必要になります。
それを現場レベルで決めるのが、管理職の役割です。
ただ、ルールを守るとき、もしくは守らせるとき、そこに個人的な感情を加えてしまうと問題が起こります。
「あの人は特別だからルールを守らなくていい」
というように、例外をつくってしまうと、チームや組織は弱くなります。
「あの人は許されているのに、なぜ自分はダメなのか」と言い出す人が現れて、組織はぐちゃぐちゃになります。
そもそも、会社組織というのは、ルールの産物です。
ルール上の関係なのですから、それを運営するのにルールが必要なのは当然のことです。
そこに感情が入り込んでしまうと、「ルール上の関係」という意識が薄れてしまいます。
いい管理職は、個人的な感情で動くのではなく、組織の人間として仮面をかぶり、ルールを守らせないといけないのです。
「空気の読み合い」はもうやめましょう。
「最初からそう言ってよ!」と思うことは、最初から潰しておくべきです。
ルールが明確でないことは、部下にとってストレスになります。
上司の顔色をうかがい、空気を読みながら行動しないといけないからです。
ちゃんとルールがある会社のほうがギスギスせず、組織内の人間関係が良好になるのです。
(本稿は、『リーダーの仮面』より一部を抜粋・編集したものです)
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社NTTドコモ、ジェイコムホールディングス株式会社(現:ライク株式会社)を経て、ジェイコム株式会社にて取締役営業副本部長を歴任。2013年、「識学」という考え方に出会い独立。識学講師として、数々の企業の業績アップに貢献。2015年、識学を1日でも早く社会に広めるために、株式会社識学を設立。人と会社を成長させるマネジメント方法として、口コミで広がる。2019年、創業からわずか3年11ヵ月でマザーズ上場を果たす。2024年4月現在、約4000社の導入実績がある。主な著書に『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』のシリーズ(いずれもダイヤモンド社)がある。