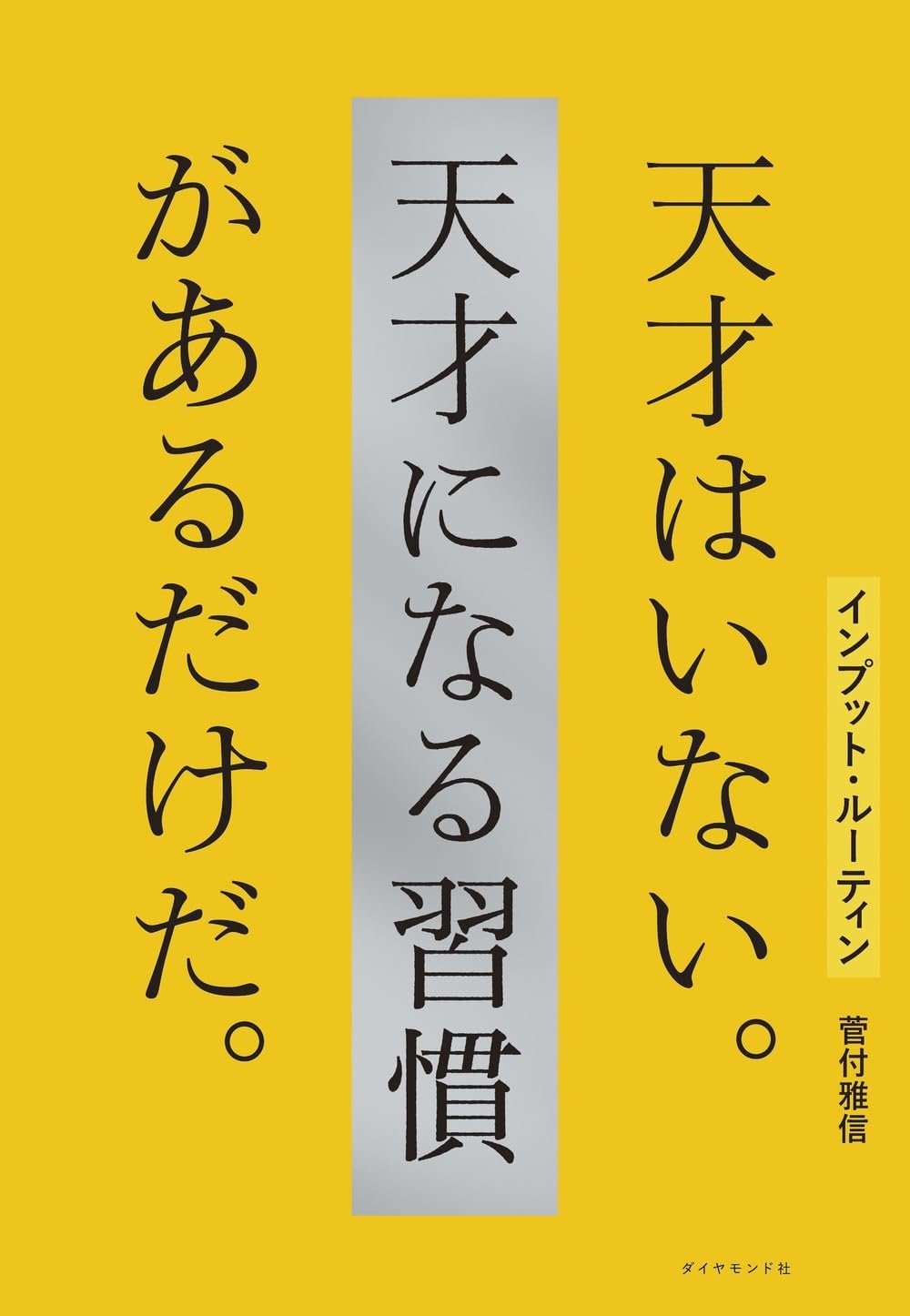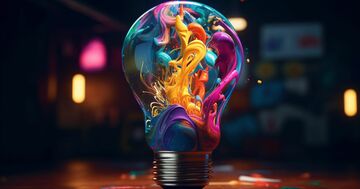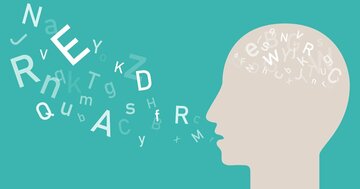優れたアイデアや表現を生み出すための最強技法と意識改革をまとめた書籍『インプット・ルーティン 天才はいない。天才になる習慣があるだけだ。』が刊行されました。編集者として坂本龍一、篠山紀信、カール・ラガーフェルドなど数多くのトップクリエイターと仕事をし、大学教授としてもクリエイター育成に携わってきた菅付雅信氏による渾身の一冊です。
アウトプットの質と量は、インプットの質と量が決める。もしあなたが「独創的な企画」や「人を動かすアイデア」、「クリエイティヴな作品」を生み出し続けたいのであれば、やるべきことはたった1つ。インプットの方法を変えよ!
この連載では同書内容から知的インプットの技法を順次紹介していきます。今回は、世界中のトップクリエイターたちがアイデアを生み出すために必ず持っている「仕組み」について。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
大量のインプットを仕組み化せよ!
編集者である私は、これまで数多くの才能たちと出会ってきたが、クリエイティヴな人々の多くが、独自のインプットの習慣=インプット・ルーティンを持っていた。新しいアイデアを常に生み出すために、大量のインプットを習慣として仕組み化しているのだ。
「どうやって、アイデアを/イメージを思いつきますか?」
国内外のアーティスト、作家、写真家、ライター、グラフィックデザイナーとさまざまな仕事をしてきたが、そのたびに私はこの質問を手をかえ品をかえ、彼らに尋ねてきた。
クリエイティヴのプロとして活躍し続ける秘訣を知りたいからである。
彼らの回答の多くは次のようなものであった。
「アイデアは思いつくものではない。出るものだ」と。
さらには、こう語る者もいた。
「すばらしいアイデアやイメージが急に降りてくる、または爆発的にひらめくということを期待しないほうがいい」と。
私が彼らから学んだことは、トップのクリエイターほど「アイデアやイメージが確実に生まれてくる日常的な仕組み」を持っているということだ。
坂本龍一、篠山紀信と仕事をして気づいた、
天才ほど「ひらめき」に頼らない
私がこれまで仕事をしてきた「天才」と称されるクリエイターたちは、たとえば音楽家の坂本龍一氏にしろ、写真家の篠山紀信氏にしろ、どんな課題に対しても「ほぼ即答に近いかたち」でアイデアを出すことができるのを私は仕事の現場で目の当たりにしてきた。
彼らは日々膨大にインプットし、膨大なアイデアの掛け算を頭の中で試しているからこそ、そんな芸当も可能になるのだ。
天才と呼ばれても、彼らはけっして己の才能を過信しない。そもそも自分の中からとめどなくアイデアやイメージが湧いてくるとは思っていない。
「このパターンは、あれと組み合わせると面白くなりそう」「この切り口は、何かに使えそうだ」「このネタは使いたいけど、今じゃないかな」……。彼らが一般人と異なるのは、その天才性というより、ネタのストックの量と、ネタの組み合わせの試行錯誤数だ。
クリエイティヴを生業とする職業である以上、どんな仕事においても毎回優れたアウトプットが求められる。そのときに頼るべきは、偶発的なひらめきなどではなく、アイデアを生み出し続ける仕組みであり、それを支える日常的な基盤なのである。
プロとアマチュアの違いは何か?
ここで少し疑問に思う方もいるかもしれない。
「自分もSNSを使って毎日大量に知識や情報をインプットしているけれど、優れたアウトプットは一向に出てこない」と。
そこにはインプット術に関する大きな勘違いがある。
才人のインプット法は、その内実は、本を読む、新聞・雑誌を読む、映画を見る、音楽を聴く、美術館・ギャラリーに通う、知恵ある人と会う、旅をする、といった傍目には案外あり触れた行動だったりするが、注意して見ると一般人とは大きな、そして決定的な違いがある。
たとえば、優れたマラソンの指南書には「マラソンの成績を上げるには、日々たくさん走ること。以上」などと書いてあるわけではない。日常的に走ることは肝心だが、人はそんなにたくさん走れるわけではない。トレーニングの量は大事だが、量の追求はすぐに限界がくる。
スポーツにおいてもクリエイティヴ・ビジネスにおいても、アマチュアとプロのいちばんの違いは何か。それはトレーニングの精度である。
第一線のプロは、やみくもに大量の知識や情報をインプットしているのではない。それであれば、SNS漬けの人間はみな、優れたクリエイターになれるはずだが、そんなことはめったにない。プロは、「精度の高いインプットを仕組み化している」のである。
意識的選択
では、精度の高いインプットとはどういう行為か?
ひと言でいえば、「選ぶ」ということだ。
たとえば映画好きの人は多くいるが、映画をクリエイティヴの重要なインプット・ソースと見なすプロや(多くのクリエイターはそうだろう)、実際に映画/映像を生業にしている人は、普段の映画のインプット法が違う。
テレビのCMやワイドショウ、ネットの口コミで話題になっているから、またはなんとなく目についたから見るというのは、プロの選択法としてはあまり賢明とは言えない。プロが評価する、またはプロの間で賛否両論なものこそを見るプロは多く、私も同様にそれらを優先的に見るようにしている。
海外の新作映画でいえば、私は「Rotten Tomatoes」というアメリカの映画レビューサイトで評価が高いものを、選択のひとつの指標にしている。映画のレビューサイトは数多く存在するが、そのなかで「Rotten Tomatoes」を選ぶ理由は、プロの批評家と一般視聴者の批評の両方がしっかり併記されて、採点・集計化されていること。加えてプロのレビューが数多く表記されていることも判断に役立つ。
また三大映画祭──カンヌ、ヴェネチア、ベルリン──の主な受賞作は必ず見るようにしている。たとえそれが、どんなに「退屈な芸術映画」であっても。
本の書評や音楽のディスクレビュー、アートの展評も同様で、私はさまざまなジャンルのプロによる評論/レビューを読むことを日課にし、それらをもとに、何を見るか/読むか/聴くかを意識的に選択している。
人生でいちばん大事なものとは?
なぜ「意識的な選択」が必要なのか?
その問いに答える前に、もっと大きな問いを立ててみよう。
「人生でいちばん大事なものは何か?」
私は時間だと考える。お金も愛も友情もあとで取り戻すことはできるが、時間だけは絶対にできない。ゆえに「時間の有限性」を人一倍認識したところから、より良いインプット法が生まれる。
私たちは無限に本を読むことも、映画を見ることも、音楽を聴くことも残念ながらできない。さらに昨今は、コンテンツがあふれかえる時代だ。SNSを覗き込めば、とても追いきれない新しい情報でタイムラインが埋め尽くされている。Spotifyをひらけば7000万曲もの楽曲が配信され、毎日膨大な曲が更新されていく。
ゆえに私たちは判別し、選択しないといけない。
何を読んで、何を読まないか。
何を見て、何を見ないか。
何を聴いて、何を聴かないか、を。
(本原稿は菅付雅信『インプット・ルーティン 天才はいない。天才になる習慣があるだけだ。』から一部を抜粋・編集して掲載しています)