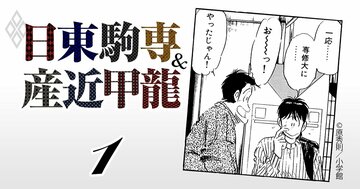Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
18歳人口の減少にともなって、いまや定員割れする私大は半数を超えた。そんな「大学全入時代」にもかかわらず、有名校に入るのは難しくなっているという。かつて自分が大学を受験した頃の経験は、我が子の場合にはほぼあてはまらないと考えるべきだろう。※本稿は、宮本さおり『知っておきたい超スマート社会を生き抜くための教育トレンド:親と子のギャップをうめる』(笠間書院)の一部を抜粋・編集したものです。
少子化で大学全入時代なのに
入試が難しい?どういうこと?
先日、友人たちと話していたら、こんな話題が上がりました。
「大学入試、推薦で行く人増えてるらしいけど、うちの学校はいまだに一般入試しか頭にないみたい。浪人も当たり前な校風で、大丈夫かなと思っちゃう」
「全入時代なんて言われるけど、これってどういう意味なんだろう」
私も仕事で教育に関する取材をしていなければ、皆さんと同じ気持ちになっていたと思います。なんとなくキーワードは耳に入るのですが、詳しくは分からないなという人が大半ではないでしょうか。
中でも会話で出てきた大学入試は、特に大きな変化が起きています。情報戦となりつつある大学入試について、見て行きたいと思います。
数年前のことですが、中学受験で大学付属校の人気が上がったことがありました。文部科学省が出した「大学入学定員厳格化」を促す通達をきっかけに「大学に入るのが難しくなる」という噂が流れ、中学入試に影響したのです。
大学に入るのが「難しい」という要因は、大きく2つありました。「大学入学定員厳格化」は東京など、一部の大都市圏の大学に受験者が集中してしまうことに歯止めをかけようと、国が2015年から呼びかけたものでした。背景に、地方の若者が都市部へ流出してしまうという問題がありました。
「大学入学定員厳格化」が
巻き起こした現象
流出の一つの要因として考えられたのが進学でした。進学により大都市圏に出て行った若者が、そのまま大都市圏で就職すると、地方の働き手はますます減ります。
労働人口が減少すれば、産業の継続は難しくなりますし、当然、その地方では税収も減ります。