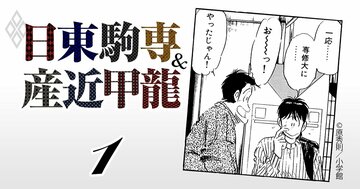「チャレンジを避けて手堅く」
受験生の間に生まれた安全志向
定員がこれだけ絞られるのならば、チャレンジ校は避けようという思いが働いたのか、チャレンジ校を受けていたような層が、堅実路線を選ぶようになり、今までMARCH(明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学)に入れた偏差値帯の子が、日東駒専(日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学)でも合格が難しいという現象がおきました。
そしてもう一つ、チャレンジ出願の減少を加速させた出来事がありました。それが、大学入試改革です。
長らく大学入試で活用されてきた大学入試センター試験(通称センター試験)が2020年度入試までで終わり、2021年度からは大学入学共通テスト(通称共通テスト)へと変更されることが決まっていました。
共通テストは新しい時代の教育に相応しい入試のあり方の実現を目指して作り出されたもので、センター試験とは問題の問い方、質が変わることが分かっていました。
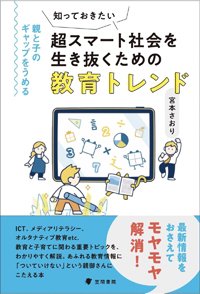 『知っておきたい超スマート社会を生き抜くための教育トレンド:親と子のギャップをうめる』(宮本さおり、笠間書院)
『知っておきたい超スマート社会を生き抜くための教育トレンド:親と子のギャップをうめる』(宮本さおり、笠間書院)
センター試験が導入された1990年は、第2次ベビーブームの世代が大学入試を迎える年でした。どうやったら効率的に入試を行えるだろうかということが考えられた時代でした。
また、社会を動かすのはマンパワーが中心で、与えられた仕事をいかに正確に、素早くこなせるかなど、社会では処理能力の高さが求められていました。このため、センター試験でも、処理能力を求めるような問い方、作問がされていました。
ところが現在は違います。求められているのは技術との共存です。科学技術の発達により、正確に処理するような単純作業はAIができる時代になりました。
人間に求められるのはそれを元に、課題や問題をいかに解決するかを考える力です。加えて、それを他者に伝える表現力も求められるようになりました。そのため、共通テストでは処理能力の高さではなく、いずれの科目も情報を読みとり、「なぜそうなるのか」を問うような問題となったのです。