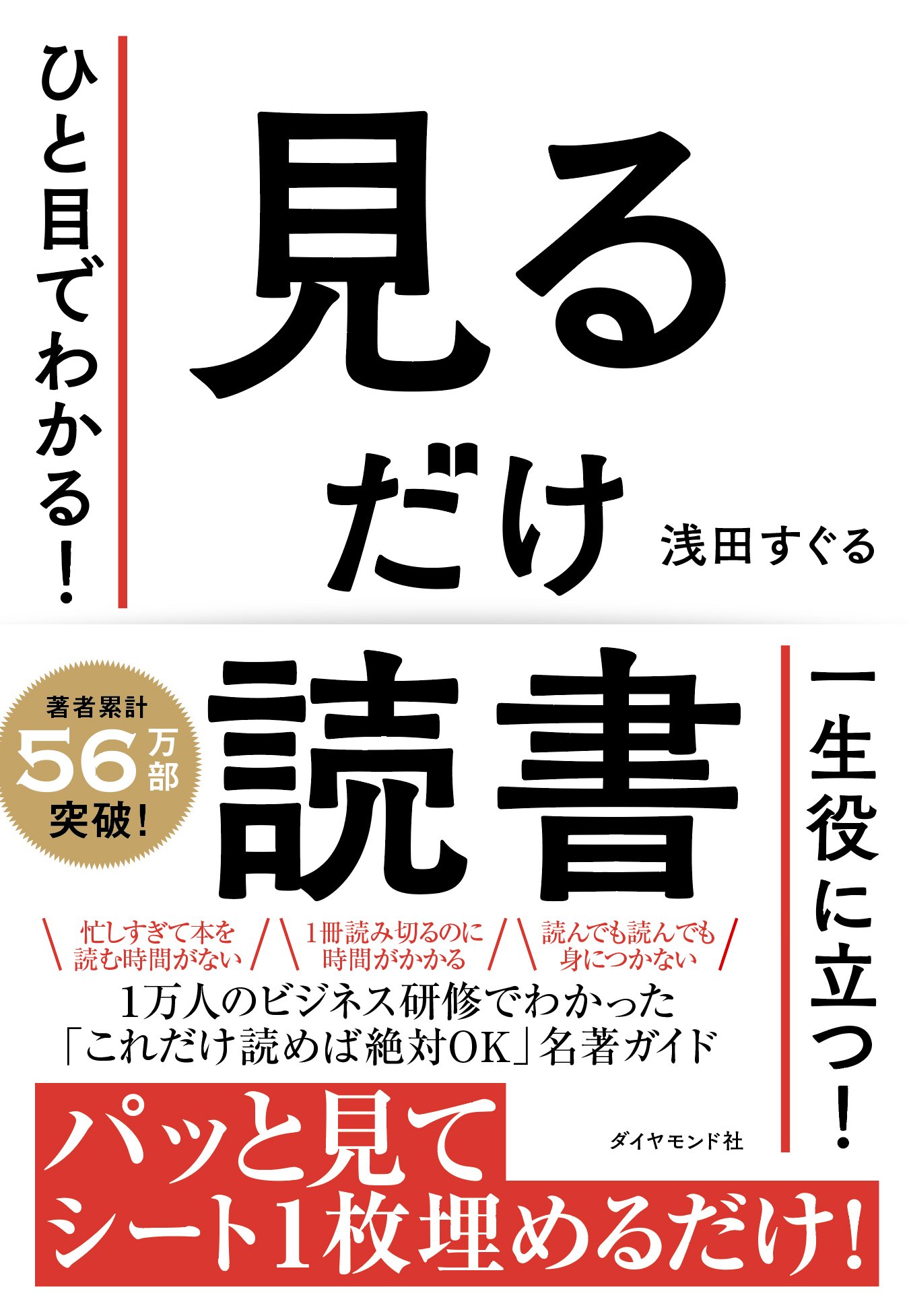忙しすぎて本を読む時間がない」「1冊読み切るのに時間がかかる」「読んでも読んでも身につかない」――そんな悩みを抱えているビジネスパーソンは少なくありません。本を読めばいいことはわかっているのに、自主的に読めない人もいるでしょう。
何の本をどう読み、どう活かしていくか――働くうえで必携のビジネススキルを良書から抜き出したのが『ひと目でわかる! 見るだけ読書』。本書は、コスパやタイパを重視する現代的な読書スタイルを重視する人にとっても、魅力的な読み解き&活用法です。たった「紙1枚」を見るだけで本の最も大事なポイントが圧倒的なわかりやすさで理解でき、用意したワーク1枚を埋めるだけで即スキル化できる1冊。それも1万冊の読書体験と1万人を教えてきた社会人教育の経験から、絶対に読んでほしい24冊+αを紹介。ただ、エッセンスをまとめただけでなく、読後には、紹介した本が有機的につながっていく仕掛けがあなたのビジネススキルを飛躍的に向上させます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「紙派」か「電子派」か
読書に関するご質問としてよくいただくものの1つに、「紙か、電子か?」というトピックがあります。私自身は、基本的に紙書籍で読むことが大半でした。ただ、2023年末にマレーシアに海外教育移住をしてからは、ほとんどの本を電子書籍で読んでいます。
結論としては、電子書籍でも紙書籍と遜色ない深さで読解できているのですが、紙よりも電子のほうがより短時間で疲れてしまうな……と感じています。
理由は、電子媒体で読んでいると、どうしても思考が浅くなり、サクサク次のページに進みたくなってしまうからです。そうならないようにと自制しながら読んでいるため、こまめにブレーキをかけながら読書をしている感覚になり、紙書籍よりも疲れやすくなってしまうのです。
学術的にはどう言われているか
ここまでは私の個人的な体験談ですが、学術的にも、このテーマについて繰り返し実験等の研究が行なわれています。
具体的には、『デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳 ――「深い読み」ができるバイリテラシー脳を育てる』(メアリアン・ウルフ著、大田直子訳、インターシフト)をぜひ読んでほしいのですが、こうした書籍を紐解くと、「内容を深く読み込む力については、電子よりも紙媒体の方が身につけやすい」といった見解がでてきます。
したがって、「幼少期の絵本の読み聞かせなどは、デジタル媒体ではなく紙媒体でやった方が良い」とも書かれていて、実際にわが家でもこうした知見に基づいた子育てを実践してきました。
ただ、決して誤解しないでほしいのは、決してデジタル媒体での読書を否定しているわけではないという点です。紙媒体での読書を通じて深み読み込む力を身につけた「後」であれば、デジタル媒体でも同レベルの読解は可能になる。これが、タイトルにある「バイリテラシー」の意味です。
「紙のち電子」なら深く読めるようになる
「紙か電子か」問題については、「こういう時代だから、もう電子書籍だけでOK」といった見解を示す知識人や著名人の方々がたくさんいます。
ただ、今回の話を踏まえると、そうした知識人・著名人の人達は、幼少期や学生時代に大量の紙書籍を読み込んできた体験があるからこそ、電子書籍でも平気な読書力を身につけている。そう捉えることができるのではないでしょうか。
私自身、マレーシアに移住して以降、ほとんどの読書が電子書籍になっても平気なのは、日本にいる間に膨大な紙書籍による読書体験の蓄積があったからです。
だとすると、「あの人も電子派だから」といって安易にアドバイスを鵜呑みにすることには、注意が必要です。最大のポイントは、「読みが浅くなりがちな電子媒体でも、深く読み込めるだけの読解力があるか」。過去に紙書籍の読書体験を通じてこうした力を高められているのであれば、電子でも紙でも、どちらでも構わないというバイリテラシーが可能です。
一方、そうした読書体験をこれまであまり積めていないのであれば、いきなり電子書籍オンリーの読書ライフに舵をきってしまうのは、少々まずいと言わざるをえません。
少なくとも、「せっかく読むなら、1回の読書でできるだけ深く読み取りたい」と望むなら、紙書籍を優先した方が時間当たりの読書体験はより有意義なものになるはずです。
以上、今回は「紙か電子か」という問いを扱ってみました。要点をまとめれば、自身のこれまでの読書体験や読解力に応じて、どちらをメインとするかは変わってくる。これが、私なりに見出している答えです。『見るだけ読書』についても、1回の読書でできるだけ深い学びを得たいのであれば、紙書籍のほうをおススメします。
(本原稿は書籍『ひと目でわかる! 見るだけ読書』著者の書き下ろしです)