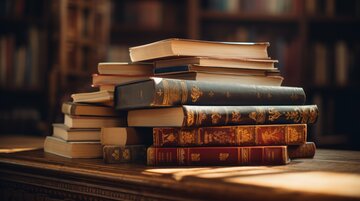老後「限られた時間を充実させる」“たった1つの習慣”
世界的名著『存在と時間』を著したマルティン・ハイデガーの哲学をストーリー仕立てで解説した『あした死ぬ幸福の王子』が発売されます。ハイデガーが唱える「死の先駆的覚悟(死を自覚したとき、はじめて人は自分の人生を生きることができる)」に焦点をあて、私たちに「人生とは何か?」を問いかけます。なぜ幸せを実感できないのか、なぜ不安に襲われるのか、なぜ生きる意味を見いだせないのか。本連載は、同書から抜粋する形で、ハイデガー哲学のエッセンスを紹介するものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
もし明日死ぬとしたら、今までの日々に後悔はありませんか?
【あらすじ】
本書の舞台は中世ヨーロッパ。傲慢な王子は、ある日サソリに刺され、余命幾ばくかの身に。絶望した王子は死の恐怖に耐えられず、自ら命を絶とうとします。そこに謎の老人が現れ、こう告げます。
「自分の死期を知らされるなんて、おまえはとてつもなく幸福なやつだ」
ハイデガー哲学を学んだ王子は、「限りある時間」をどう過ごすのでしょうか?
【本編】
「人はいつか、必ず死ぬ」この事実と向き合い、日々生きる
「死を意識すれば、自己のかけがえのなさ(交換不可能性)を思い出して『人生とは何か?』を問いかけるきっかけができるが、死を忘却していたらそんなことは問いかけない。さて、死を忘却した生き方である『非本来的な生き方』とは何だったか。おさらいしておこう」
非本来的な生き方
=交換可能な、道具のような生き方
=自己の固有の存在可能性を問題としない生き方
=自分の人生とは何だったのかを問わない生き方
=死を忘却した生き方
「そうだ、非本来的な生き方にこれも追加しておこう」
=おしゃべりと好奇心に満ちた生き方
「おしゃべりと好奇心、またずいぶんと日常的な言葉遣いですね」
「うむ。死を忘却した人間、すなわち『人生とは何かを問いかけない非本来的な人間』は何をして人生を過ごすのか? ハイデガーの答えがこれだ。おまえ自身はどうだったかな?」
じっくりと思い返すまでもない、ほんの一週間ほど前の、自分の生き方そのものだ。刺激的で豪華絢爛なパーティを繰り返す日々。そして、そこで出会う貴族の友人たち―と言っても死ぬことがわかってから誰も会いに来なくなり、もはや友人の名に値しないが―彼らと話すことと言えば、流行りの服やアクセサリーについて、それから興味をそそる時事ネタやニュース、あとはどうでもいい人間関係の噂話ぐらいであった。
「限りある時間」を充実させるために
「そうですね。まさに好奇心に満ちて、おしゃべりをして過ごしていました。ただ―今にして思えばくだらない世間話ばかりでしたが、そのときには人生においてそれが一番楽しい時間であったのも事実です。おしゃべりや好奇心は、何がいけないのでしょうか?」
「なに、単純な話さ。死を忘却し、自己の固有の可能性に向き合わなくなってしまうから、いけないのだ。たしかに、おしゃべりは楽しい。そして好奇心が次々と話題を見つけ出してくれるから、その楽しみをいつまでも続けることができる。
だが、一度しかない貴重な人生の時間を、そのおしゃべりで埋め尽くしてしまって本当に良いのだろうか? おしゃべりは、決して何も生み出さない。人づてに聞いたこと、または、自分の人生とまったく関係のないこと、それらを他人に語る行為は、まさしく『時間を潰す』行為であるが、それは本当に満足した幸福な人生の過ごし方だと言えるのだろうか?」
(本原稿は『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』の第5章を抜粋・編集したものです)