【哲学って何?】「ずば抜けて頭がいい人」のすごい回答
世界的名著『存在と時間』を著したマルティン・ハイデガーの哲学をストーリー仕立てで解説した『あした死ぬ幸福の王子』が発売されます。ハイデガーが唱える「死の先駆的覚悟(死を自覚したとき、はじめて人は自分の人生を生きることができる)」に焦点をあて、私たちに「人生とは何か?」を問いかけます。なぜ幸せを実感できないのか、なぜ不安に襲われるのか、なぜ生きる意味を見いだせないのか。本連載は、同書から抜粋する形で、ハイデガー哲学のエッセンスを紹介するものです。
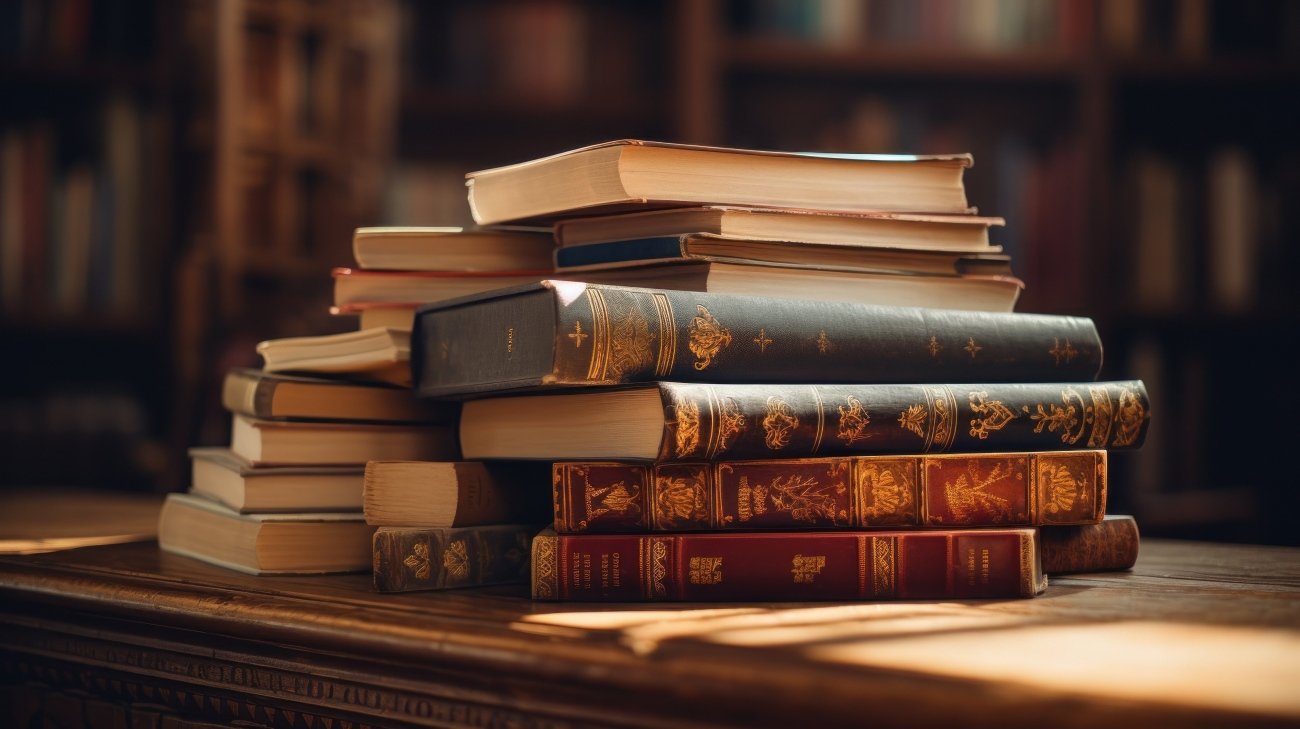 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
もし明日死ぬとしたら、今までの日々に後悔はありませんか?
【あらすじ】
本書の舞台は中世ヨーロッパ。傲慢な王子は、ある日サソリに刺され、余命幾ばくかの身に。絶望した王子は死の恐怖に耐えられず、自ら命を絶とうとします。そこに謎の老人が現れ、こう告げます。
「自分の死期を知らされるなんて、おまえはとてつもなく幸福なやつだ」
ハイデガー哲学を学んだ王子は、「残されたわずかな時間」をどう過ごすのでしょうか?
※前回記事『「老後がつまらない」を一瞬で解決する“すごい考え方”』
【本編】
「ご老人、いえ先生と呼ばせてください。もう少しそのハイデガーの哲学について教えてほしいのですが、その前にそもそも哲学とはいったいどういうものなのでしょうか?」
ハイデガーは「哲学」をこう定義した
「哲学とは『思考できないことを問いかけること』だ。もっと簡単に『考えられないことを考えること』だと言ってもいい」
「考えられないことを……考える? すみません、謎かけのように聞こえますが」
「おっと、すまない。結論を急ぎすぎてしまったな。今のは、ハイデガー自身の哲学の定義だったのだが……。うむ、ではまず一般的な知識として、『哲学とは何か?』という質問に答えよう」
そう言って先生は小舟を漕いで岸へと近づけた。そして私に乗るように促す。私は言われるがまま小舟に乗り込み、先生と向かい合う形で座った。
「哲学の基本」を学ぶ
「哲学とは、知の探究であり、当たり前のものとして見過ごしてきた価値観―常識と言ってもよいが―それを徹底的に問いかけることだ。ようするに、『○○とは何か?』をひたすら考える学問だと思ってもらえばいい。そして、この『〇〇』には、今述べたように常識的な当たり前の言葉が入る。たとえば愛だったり、正義だったり、だ」
「つまり、『愛とは何か?』『正義とは何か?』を考えるということですね。なるほど、そういう形で問いかけるのが哲学だと。そうすると、ハイデガーは『死とは何か?』について考えた哲学者という理解で良いですか?」
「いや、それは半分正しいが、正確には違うと言ったところだな。一般的なイメージとしては『死とは何か?』『人間とは何か?』を問いかけた哲学者として有名だ。しかし実際のところ彼は、あらゆる常識的な言葉の中で、最も根源的なものを自分の哲学のテーマに選んだ。それは『存在とは何か?』だ。
世の中には、いろいろなモノが『存在する』。その『存在する』とは、そもそもどういうことなのか? それをハイデガーは問いかけたのだ。そして、彼は『存在とは何か』を考えるために『人間とは何か』を問いかけ、『人間とは何か』を考えるために『死とは何か』を問いかけた―という順番である。ただ、きっとおまえは、それらの細かい事情よりも『死とは何か』『死が人間にどんな可能性を与えるのか』のほうを早く知りたいのだろう。
その気持ちはわかる。しかし哲学というものは、長い年月を経た古木のように巨大で複雑な体系であり、そう簡単に理解できるものではない。実際、おまえも哲学と言えば難解というイメージがあるはずだ。
だから、ハイデガーの哲学を正しく理解したいと思うのであれば根気強く段階を踏まなくてはならない。そうしないで結論だけを聞こうとするなら、せいぜい『人間は死ぬから、人生が輝くのだ』くらいの見せかけの理解しか得られないだろう。そんな口当たりの良い、上っ面の知識を、おまえは欲しいわけではあるまい」
「そうですね。それが答えだと言われても、納得できないのであれば意味がありません。早く答えが欲しいという焦りはもちろんありますが、それでも時間を無駄にするわけにはいきません。正しく理解できるよう段階を踏む方法で、ぜひご教授をお願いします」
(本原稿は『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』の第1章を抜粋・編集したものです)



