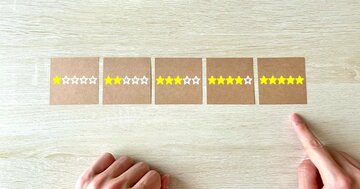美食=高級とは限らない。料理の背後にある歴史や文化、シェフのクリエイティビティを理解することで、食事はより美味しくなる! コスパや評判にとらわれることなく、料理といかに向き合うべきか? 本能的な「うまい」だけでいいのか? 人生をより豊かにする知的体験=美食と再定義する前代未聞の書籍『美食の教養』が刊行される。イェール大を経て、世界127カ国・地域を食べ歩く美食家の著者の思考と哲学が、食べ手、作り手の価値観を一新させる1冊だ。本稿では、同書の一部を特別に掲載する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「食べログ」の妥当性を考える
日本の食べログは、いろいろな批判もありますが、個人的にはレストランを頻繁に食べ歩いている人の感覚とそれなりに合致していると僕は感じています。もちろん、僕個人がその点数や順位に100%賛同するかというと、そんなことはありません。
自分が気に入らない店がたとえばトップ10に2、3軒入っているからといって食べログは信用できない、という人もいますが、点数は不特定多数の評価をアルゴリズムによって集計した結果でしかないので、そんなものだと思います。
逆に、より多くの人が、食べログより妥当性がある、と感じるランキングはあるでしょうか? 比較的OAD(※Opinionated About Dining/アメリカ人フーディーのスティーブ・プロトニキが立ち上げたレストランリスト)がいい線いっていると個人的には思うものの、多分現時点では存在しない。完璧でないからといって食べログに文句をいっている人は、逆にどれだけ食べログに期待しているの、と思ってしまいます。
食べログの評価システムと特徴は、そのアルゴリズムにあります。あくまで僕の印象ですが、食べログのアルゴリズムは、サクラなどの不正の影響を削ぐことを最重要視していると思っています。
具体的にいうと、いろんなお店で実際に食べていて、影響力のあるレビュアーは、配点のウエイトが高い。だから、そういう人が点数をつけると、お店の総合点が目に見えて動くことがあります。逆に、特定のお店を陥れる目的で捨てアカウントをどんどん作って悪い評価をつけたり、逆に自分のお店の評価を上げようと5点をつけたりしても、ほとんど影響がありません。
もちろん、どんな方法論も完璧ではありません。食べログの場合、影響力のあるレビュアーが力を持ちすぎる、という懸念はあるでしょう。また、新しくオープンした店は、そういうレビュアーが何人か食べに行って評価するまで、点数がつかない、もしくは基準点の3点近くにとどまってしまう、という課題もあります。つまり、不正を防止する代償として、速報性が犠牲になっている側面があります。