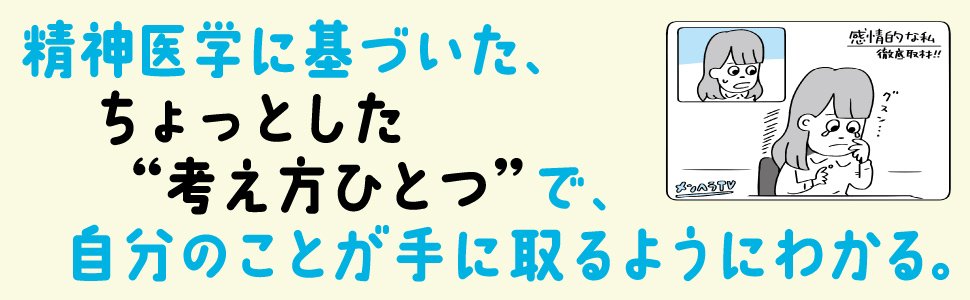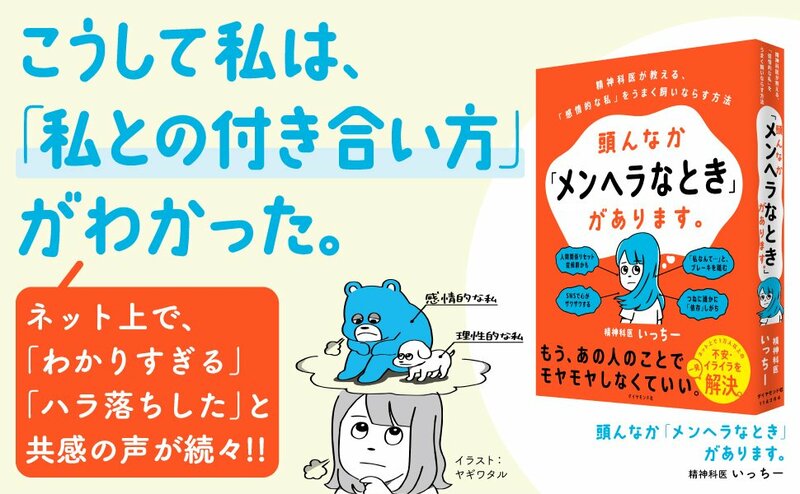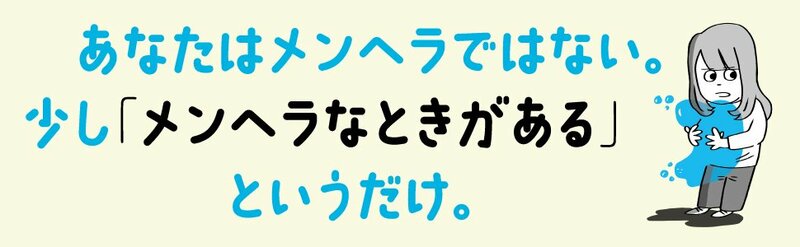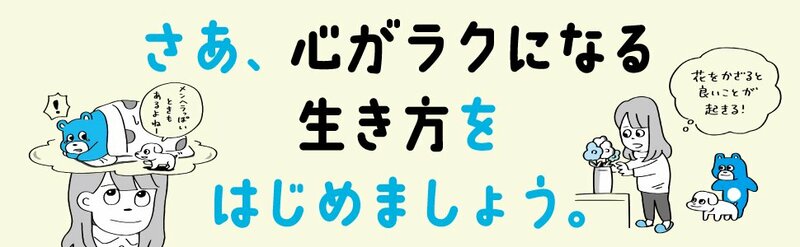「寝ても寝ても疲れが取れない」。精神科医が教える納得のアドバイスとは?
それを語るのは、これまでネット上で若者を中心に1万人以上の悩みを解決してきた精神科医・いっちー氏だ。「モヤモヤがなくなった」「イライラの対処法がわかった」など、感情のコントロール方法をまとめた『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』では、どうすればめんどくさい自分を変えられるかを詳しく説明している。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、考え方次第でラクになれる方法を解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ぐっすり寝ても疲れが取れない
朝起きた瞬間から疲れを感じてしまう、何をしてもだるさが抜けない――
そんな不調が続いてなんだかスッキリしないときってありますよね?
夜ぐっすり眠ったはずなのに、目覚めた後もエネルギーが湧いてこない…。
そんな状態が続くと、「自分、どこかおかしいのかな」と不安になることもあるかもしれません。
実は、その疲れの原因は、あなたの「緊張感」が取れていないことにあるかもしれません。
今日はそんな「緊張感」との上手な付き合い方について、共有したいと思います。
寝ても疲れが取れない理由とは?
私たちの体と心は常にバランスを取ろうとしています。
人間の「緊張」と「リラックス」はシーソーのようなもので、どちらに傾きっぱなしでは体調を崩してしまいます。
ですが、ストレスが多い日々を過ごしていると、このバランスが崩れてつねに「緊張」しっぱなしになってしまいます。
特に、ストレスやプレッシャーを抱えた状態が長く続くと、心も体もリラックスする方法を忘れてしまいます。
この「緊張感」が、実は疲労感の大きな原因になっているのです。
たとえば、仕事でのミスをいつまでも引きずったり、人間関係のトラブルで気持ちが沈んでいると、夜寝る前でもいつも考えてしまって脳は休む暇がありません。
心が常に警戒モードになっていると、体もその影響を受けてしまい、夜眠っている間も本当の意味で休めなくなってしまいます。
その結果、朝起きたときに「まだ疲れている」と感じてしまうのです。
リラックスこそが現代での特効薬
では、この疲労感から抜け出すためにはどうすればいいのでしょうか?
答えはシンプルです。「リラックスする時間」を意識的に作ることです。
たとえば、日常の中で自分をゆるめる小さな工夫を取り入れてみましょう。
朝起きたときに深呼吸をしてみる、カーテンを開けて日差しを浴びる、暖かい飲み物を手にして一息つく……。こうした些細な行動が、緊張感を和らげる第一歩です。
また、寝る前にスマートフォンを見ないようにするのもおすすめです。
画面から発せられる光は脳を刺激し、リラックスを妨げてしまいます。
代わりに、好きな本を読んだり、静かな音楽を聴いたりすることで、心と体を「休む準備」に導いてみてください。
「今、この瞬間」に集中する
リラックスするためのもう一つの鍵は、「今、この瞬間」に意識を向けることです。
過去の失敗や未来の不安を考えるのをやめて、今ここで自分が感じていることに集中する。
それは簡単なようでいて難しいことですが、効果は絶大です。
たとえば、散歩をするときに足元の感触や風の音に注意を向けてみる、食事をするときに一口ごとの味わいを意識する……。こうした小さな行動が、心を穏やかにしてくれます。
自分に優しく、ゆるやかに感じること、「疲れた」と感じることは、心からの大切なメッセージです。
そのメッセージを無視せず、「今日は少しペースを落としてみよう」と自分に許可を与えてあげることが、心と体を回復させる第一歩です。
次の休みの日、少し贅沢をしてお気に入りのカフェでゆっくり過ごしてみてはいかがでしょうか?
または、温かいお風呂にゆっくり浸かりながら、何も考えない時間を作るのも素敵です。
リラックスしてなにも考えない時間を作ることは、じつは私たちが健康に生きるためにとても大切な時間なのです。
(本稿は、『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』の著者・精神科医いっちー氏が特別に書き下ろしたものです。)
精神科医いっちー
本名:一林大基(いちばやし・たいき)
世界初のバーチャル精神科医として活動する精神科医
1987年生まれ。昭和大学附属烏山病院精神科救急病棟にて勤務、論文を多数執筆する。SNSで情報発信をおこないながら「質問箱」にて1万件を超える質問に答え、総フォロワー数は6万人を超える。「少し病んでいるけれど誰にも相談できない」という悩みをメインに、特にSNSをよく利用する多感な時期の10~20代の若者への情報発信と支援をおこなうことで、多くの反響を得ている。「AERA」への取材に協力やNHKの番組出演などもある。