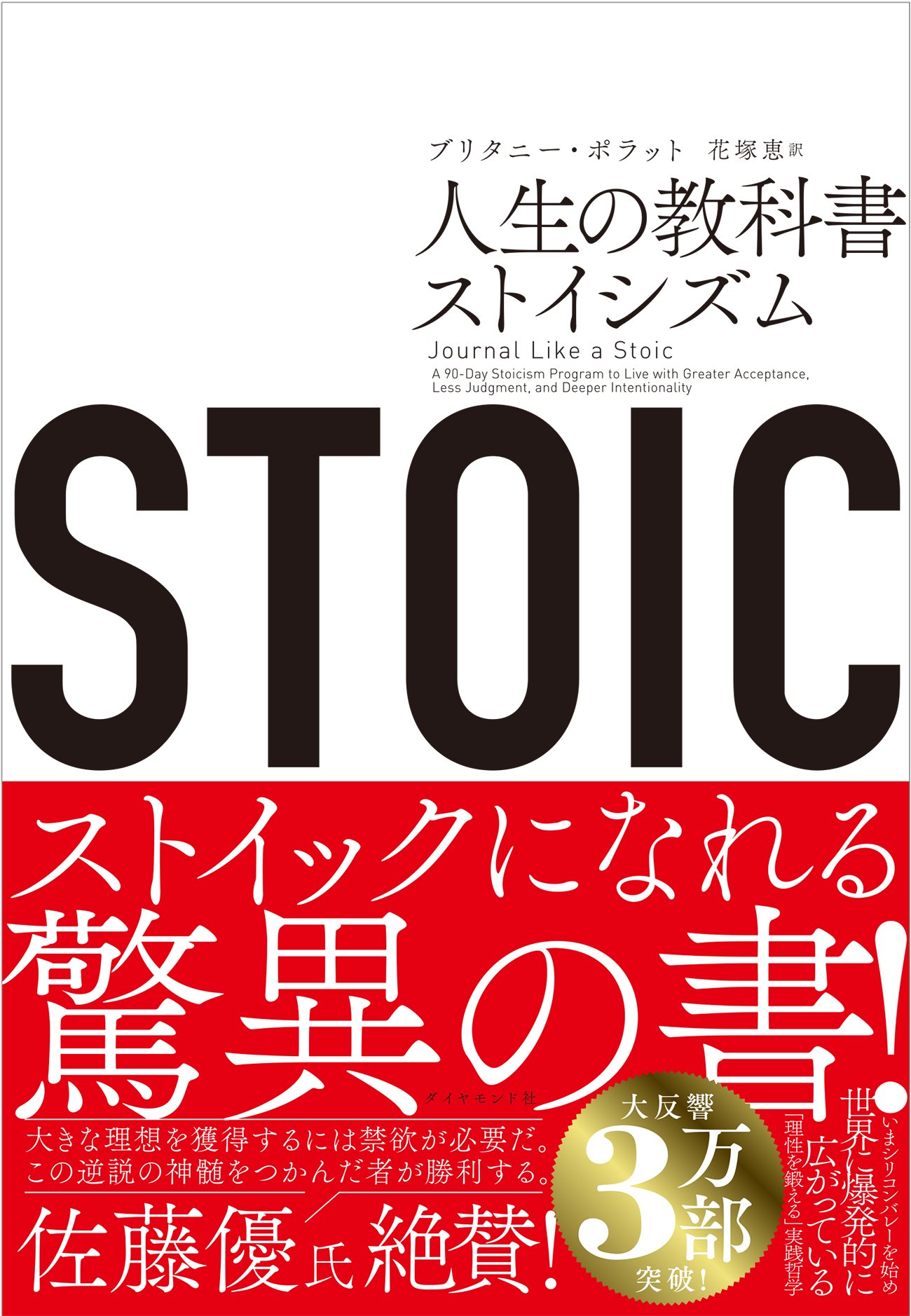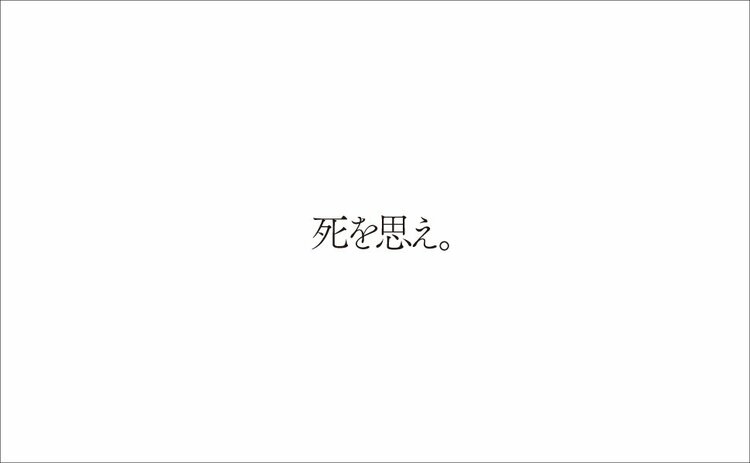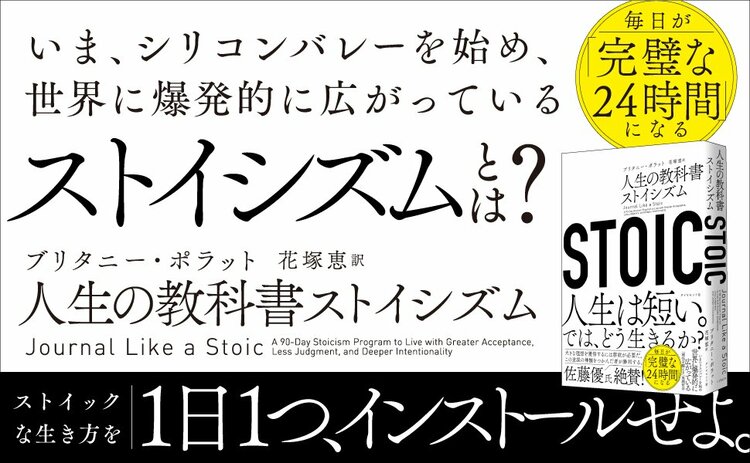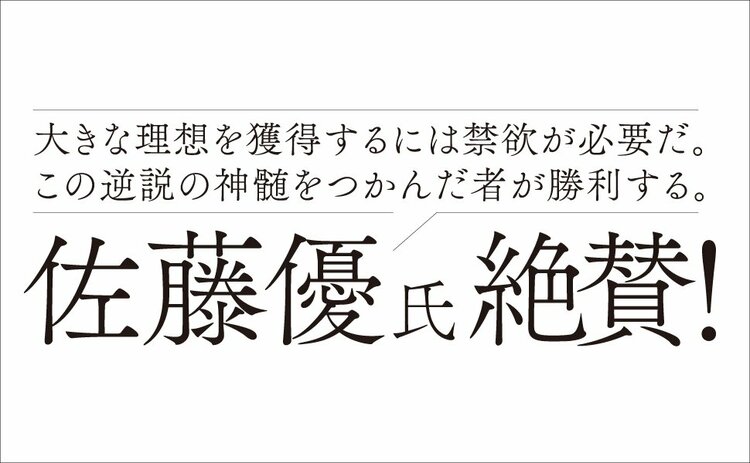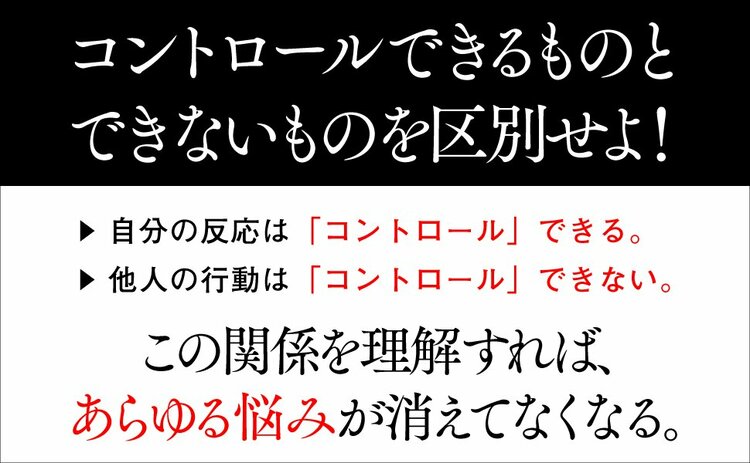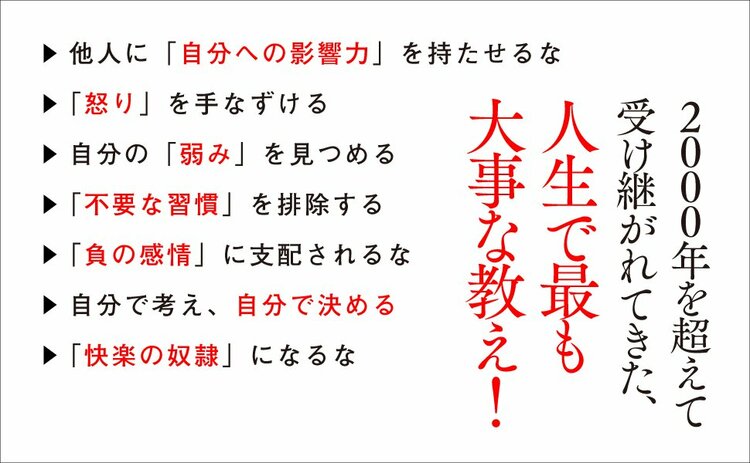いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
静かな勇気を発揮する
勇気とは、浅はかで軽率な行動や危険を好むこと、恐怖心を煽る何かを求めることではない。
何が悪で、何が悪でないかを区別できる知力、それが勇気だ。
――セネカ『ルキリウスに宛てた道徳書簡集』
(『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より)
「当たり前のこと」こそ勇気がいる
「万引きをしない勇気をもとう」といった啓発ポスターが、数年前に話題になったことがある。
いやいやいや、どっちかっていうと万引きをするほうが勇気がいるでしょ。
こうつっこみたくなる。「万引きをしない」という当たり前のことに勇気がいるって、どういうことよ?
以前、少年犯罪に詳しい、犯罪心理学者の出口保行先生に聞いた「本屋さんで万引きをする少年たち」の話が印象的だった。
彼らは本が読みたくて本を盗むのではない。スリルを楽しむためにやっている。
事実、盗んだ本は一切読むことなく、そのまま家に積んでいる。
「ゲーム性」に引かれてはいけない
最初は一人で、一冊だけドキドキしながら盗む。次第に大胆になっていき、何冊も盗む。仲間に声をかける。勇気を試すゲームなのだと言って引きこむ。秘密を共有する仲間がいるということが、よりゲームを面白くする。
そして、盗んだ量を競い合うようになり、しまいには大きな袋に本をガバっと入れて引きずるようにして盗むようになるということだった(この心理は、出口保行著『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』の中で「センセーション・シーキング」という用語で解説されている)。
「おまえの勇気を試したいから、一緒に万引きをしようぜ」と言われたとき、その危険なゲームに参加するのが「勇気がある」ことなのか。それとも、「それは悪いことだから、やらない」と断るほうが勇気があるのか。
むろん、後者である。「万引きをしない勇気」が正しい。
「わかっていて流される」のは危険行動
『STOIC 人生の教科書ストイシズム』によると、ストア派の哲学者セネカは、「何が悪で、何が悪でないかを区別できる知力、それが勇気だ」と言っている。
セネカは「暴君」として知られる第5代ローマ皇帝ネロの少年時代の家庭教師をしていた。
ネロが皇帝に即位してからは、政治的な補佐役も務めた。
敵、味方を問わず残虐非道な行為をしていたというネロを諫め、支えるのはどんなにしんどかっただろう。何が悪で、何が悪でないかを区別できる知力=勇気が自分にはあるのかと自問自答し続けなければならなかったに違いない。
万引きならまだ簡単だが、世の中には、悪の判断が難しいものもある。
たとえば自分の所属している組織が、「あまり良くないことをしているんじゃないか?」とうっすら思う程度のことが、あるかもしれない。「自分も知らず知らず、それに加担しているのではないか?」
向き合うのは怖い。
なにも、「(告発のような)行動をすべき」というのではない。ただ心の中に沸いた疑問を打ち消さず、向き合う。恐怖心を乗り越えて、何が悪で何が悪でないかを判断しようとする。
それこそを勇気だと言っているのである。
(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)