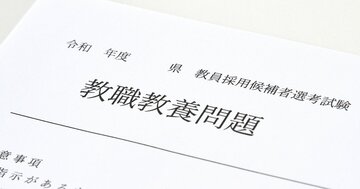もちろん学校内で代替者になれるような先生たちは、すでに他の穴を埋めるために使われて、担任に入れる人がいなくなっていたのだろう。
確かに、教育委員会の説明の通り、教職員名簿上では病気の先生はこの学校に勤務していることになっているから、名簿上の人数は足りているという説明にも一理ある。一方で、実際には担任の先生が教室にいないという状態が起きている。子どもの目線からみれば、代わりの担任の先生が教室にいないという意味で、教員が不足している状態ともいえるはずである。
この事例をみれば、いったい何のどのような状態を「教員不足」というのかは、立場や状況によって異なっていて、実は共通の理解がなされていないことがわかる。これが、教員不足をめぐる議論がうまくかみあわない理由の1つなのである。
文部科学省が示している
「教員不足の定義」とは
実は文科省は、2021年になるまで、「教員不足」について正式な定義を示してこなかった。2018年に「いわゆる『教員不足』について」という資料を公表し、11の都道府県・政令市へのアンケート調査の結果を明らかにした。
おそらくこれが、近年の教員不足問題に初めて言及したものだった。しかし、この資料の「いわゆる『教員不足』」というタイトルが示す通り、当時の文科省は教員不足が起きていること自体にも懐疑的で、教員不足とは何かということにまで踏み込んだ定義は示されていなかったのである。
ところが、その後数年で急激に教員不足が深刻化し、2021年になって全国調査が実施された。この調査用紙上では、以下のような定義が示されていた。
「学校に配置されている教員(正規教員、臨時的任用教員及び非常勤講師を含む。)の数が、学校に配当されている教員定数を満たしていない状態」
つまり、教員不足とは「学校に配当されている教員定数」を基準とし、この基準に満たない状態だというのである。それでは、「学校に配当されている教員定数」はどのように決定されているのだろうか。教員数を決める仕組みを概観することにしよう。
国と地方自治体の両方で
教員数を決めている
日本では、教員の数については、まず国が標準的な教員数を算定し、地方自治体が最終決定する仕組みが採用されている。