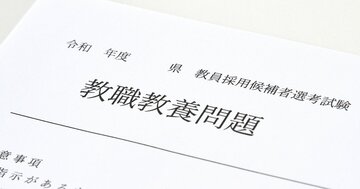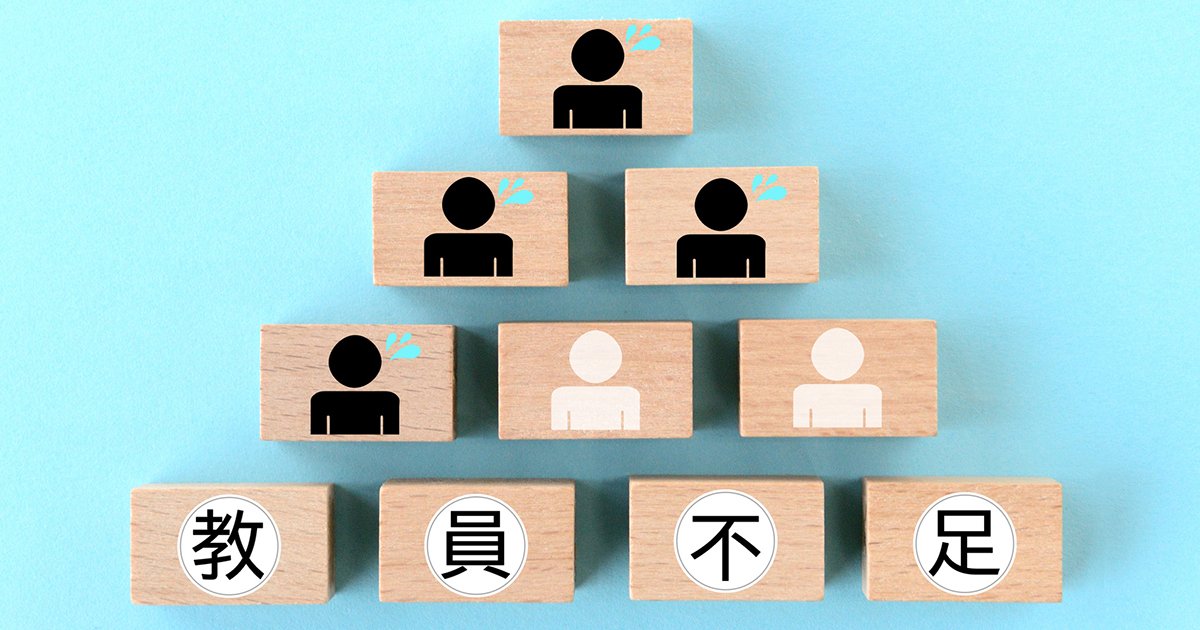 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本の公立小中学校の教員数は、国と地方自治体が決めるシステムを採用している。名簿上、決められた教員定数を満たしていれば、急きょ欠員が出て替わりの教員が見つからなくても「教員不足」にはあたらないという。一般の人々にはわかりにくい“教員不足の定義”について、教育学を専門に研究する佐久間亜紀氏が解説する。※本稿は、佐久間亜紀氏『教員不足――誰が子どもを支えるのか』(岩波書店)の一部を抜粋・編集したものです。
外からは分かりにくい
「教員不足」の基準
教員不足とは、いったい何を基準にした「不足」なのだろうか。文科省は、教員不足を「教員の配当定数」からの不足分と定義しているが、いったいこの配当定数とは誰がどのように決めた教員数のことなのだろうか。これらの問いに答えるために、日本の教員数がどのような仕組みで決定され、教員が配置されていくのかを検討しよう。
ある知り合いが、私にこんな疑問をつぶやいた。
「教育委員会に聞いたら、これは教員不足のせいではないって否定するのですが、いったいどういうことなのでしょうか?」
彼女の子どもが通う小学校では、1カ月近く学級担任がいないままで、子どもたちが落ち着かなくなっているという。いろいろな先生方が入れ替わり立ち替わりやってきて、授業はなんとか行われているらしい。それでも、自習が多いと子どもが愚痴を言うし、学校に尋ねてもはぐらかされてきちんと答えてもらえないので、思い切って教育委員会に「どうして先生がこんなに足りないのですか」と尋ねたというのである。
すると教育委員会からは、「担任になるはずだった先生が病休に入っています。本当は1週間で復帰する予定でしたが、体調が思うように回復せず、病休が延長になってしまいました。先生の名前は職員名簿にきちんとありますし、この件は教員不足ではありません」と回答された。
「先生はいませんが、不足はしていません」と返答されても、一般の市民には謎というほかないだろう。
この教室の舞台裏で、関係者はきっと苦慮していたに違いない。教員も労働者なので、通常は1年間で20日間の年休を取得する権利が認められている。おそらく、担任になるはずだった教員が年休から続けて病休に入り、しかもその病休が長引きそうだとわかった時点で、学校は病休の間だけ代わりを務めてくれる非正規雇用教員を探したが、見つからなくて困っている状態だったのではないか。