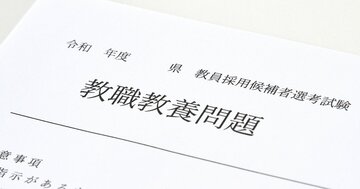教育とは人が人を育てる営みである。つまり教育は必然的に労働集約的な仕事であるため、公立学校を運営するために必要な経費のほとんどは、教員の人件費だという構造になっている。
この点は、世界各国で共通しており、一般的に教員給与を負担するセクターが、教員数を決める仕組みになっている。例えば、ドイツやフランスでは国が教員数を決定し、教員給与を負担している。一方、アメリカやイギリスでは、地方自治体が教員数を決定し、教員給与を負担している。日本や韓国で採用されているのは、いわばその中間に位置づけられるような仕組みである。
ここで重要な点は、日本では国と地方自治体の両方が教員数を決めるプロセスに関与し、教員の給与を分担して負担しているという点である。独仏のような中央政府決定型でも、英米のような地方自治体決定型でもなく、その中間の制度になった背景には、日本が長い時間をかけて、教員の数の決定方法を改良してきた歴史がある。
日本でも、かつてはイギリスやアメリカのように、地方自治体決定型だった。明治時代の学制改革によって、史上初の小学校という近代学校制度ができた時には、教員の人件費は市町村の負担とされていた。
ところが、市町村だけで教員を雇用するには、財政負担が大きすぎた。また市町村ごとに、財政状況の格差が激しかった。そのため、子どもが生まれた地域によって、学校の教育環境に大きな格差が生じてしまっていたのである。
生まれた地域によって教育を受ける機会やその質に有利・不利が生まれてしまうこの状況は、当時の社会でも大きな問題として認識され、少しずつ改善の道が模索されていった。
その結果、もっと広い地域で協力して教員給与を支え、市町村ごとの格差を縮小していこうと、1940年に道府県ごとに教員給与を負担する制度が成立した(県費負担教職員制度)。また、未来を担う子どもを育てるという点では、国と地方は同等の責任をもつべきという論理のもと、道府県が負担する教員給与の2分の1を、国が負担して国庫から支出することになった(義務教育費国庫負担制度)。これにより、道府県ごとの教員数の格差も縮小しようとする制度が整えられたのである。