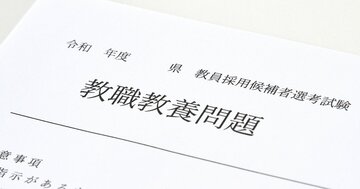2000年代以降再び
“地域間教育格差問題”が浮上
したがって1940年以降は、県費負担教職員制度と義務教育費国庫負担制度によって、日本全国どこに生まれても子どもが教育を受ける機会を得られるよう、教育の地域格差を解消していく努力が続けられてきた。
ただし、課題も生じていた。市町村立の小中学校の教員が、市町村ではなく道府県(1943年以降は都道府県)に雇用されるという、学校の設置者と教員の給与負担者の不一致(いわゆる「ねじれ」)が生じてしまったのである。しかしそれでも、明治期からずっと、みんなで教員の人件費を負担し合って、地域ごとの教育格差をなんとか縮小していこうという方向が、国全体で共有されていた。
ところが、1980年代以降、ゆるやかにその改革の方向が反転しはじめ、2000年代以降は、格差拡大もやむなしとする改革が急速に進められてきた。まず、1980年代以降の行財政改革を背景に、国と地方の役割分担が見直されるようになった。
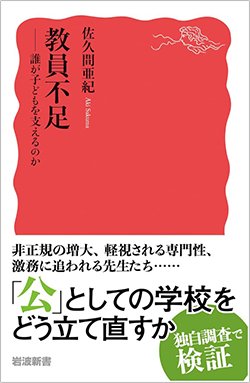 『教員不足――誰が子どもを支えるのか』(岩波書店)
『教員不足――誰が子どもを支えるのか』(岩波書店)佐久間亜紀 著
そして、2006年にはいわゆる「三位一体の改革」の一環として、前述した義務教育費国庫負担制度の見直しが行われた。地方自治体の裁量を大きくする一方、国の教員給与の負担は2分の1から3分の1に縮小された。これに伴って2000年代以降は、再び教員数などの地域間格差が大きくなってきたのである。
さらに2017年度から県費負担教職員制度が改革され、政令市の学校教職員の給与費は都道府県から政令市に移管された。政令市は人事権をもつのに財源を負担していないという「ねじれ」を解消するためであった。
ところが一口に政令市といっても、横浜市のような巨大な政令市とそうでない自治体の財政状況には大きな差がある。したがって現在では、都道府県が雇用する教員と政令市が雇用する教員の人数や給与の差、あるいは政令市ごとの教員数や給与の差は、拡大する傾向にある。
総じて、日本では教育の地域格差を縮小するため、国と都道府県・政令市の両方が、教員数を決定するプロセスに関与する制度が採用されてきたが、近年では英米に類似する方向で改革が進んでいるといえるだろう。