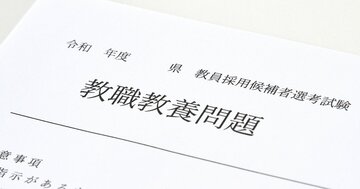写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
年々、深刻さを増す“教員不足問題”。実際の教育現場はどのような状況に陥っているのか。そして、教員不足の問題は教員と子どもたちにどのような影響を及ぼすのか。長年教員の育成に携わってきた佐久間亜紀氏が、教員となった自身の教え子たちのリアルな声から深刻な現場の状況を書き記す。※本稿は、佐久間亜紀氏『教員不足――誰が子どもを支えるのか』(岩波書店)の一部を抜粋・編集したものです。
明るく愛情深い女性教師から
送られてきた「絶望」の二文字
「今日がまだ木曜日であることに絶望しています」
ある朝、中学校教員になった教え子から、LINEアプリにこんなメッセージが入っているのを見つけ、私は思わず画面を凝視した。
奈々子先生(仮名)は30代半ばの中堅教員だ。彼女が大学1年生だった時、私の講義を履修していたのが出会いだった。その頃から、彼女はいつも、どうやって自分自身と周りの人たちを楽しくするかを考えていた。たわいない会話の中にも「今日は胃カメラを、3オエオエくらいで無事にオエました!」と笑いを乗せてくるような、元気印という言葉がぴったりくる人だった。しかも、ひとたび教育の話になると、生徒が可愛くてたまらないと思う気持ちがあふれ出て止まらない。
その奈々子先生が、「絶望」というような鋭い言葉を送ってくること自体が、事態の深刻さを物語っていた。どれほど追い込まれ、どれほど土曜が遠いのか。
このメッセージの少し前、コロナ禍でオンライン開催になってしまった授業に関する自主的な研究会でも、奈々子先生は画面越しに、いつになくお笑い抜きで、仲間にそのしんどさを語っていた。
4月から研究主任を任され、そもそも忙しい毎日だった。公立学校では必ず、学校全体の教育活動の質を向上させるために、各校で毎年テーマを決めて学校全体で教育研究に取り組む努力が行われている。奈々子先生に任された研究主任とは、授業の質を向上させる学校ごとの取り組みの統括を担う仕事だ。
教員としての通常業務に加えて、研究主任の仕事を任されて大変ななか、6月頃に、同僚で同じ理科担当のA先生が妊娠し産休に入った。ところが、代替の先生が見つからない。やむをえず、本来なら産休代替の教員がするべきA先生の授業や校務を、理科の教員で分担して行うことになり、奈々子先生の理科の担当授業数も1.5倍になった。授業の量は増え、勤務時間内に授業の準備やテストの採点等をする空き時間もなくなってしまったのである。