「『なぜ、そう思うの?』は、絶対にNGです」
「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ?」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ?」「どうして?」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話=「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。
「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」=事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「ありがちなNG質問」について紹介する。(構成/ダイヤモンド社・榛村光哲)
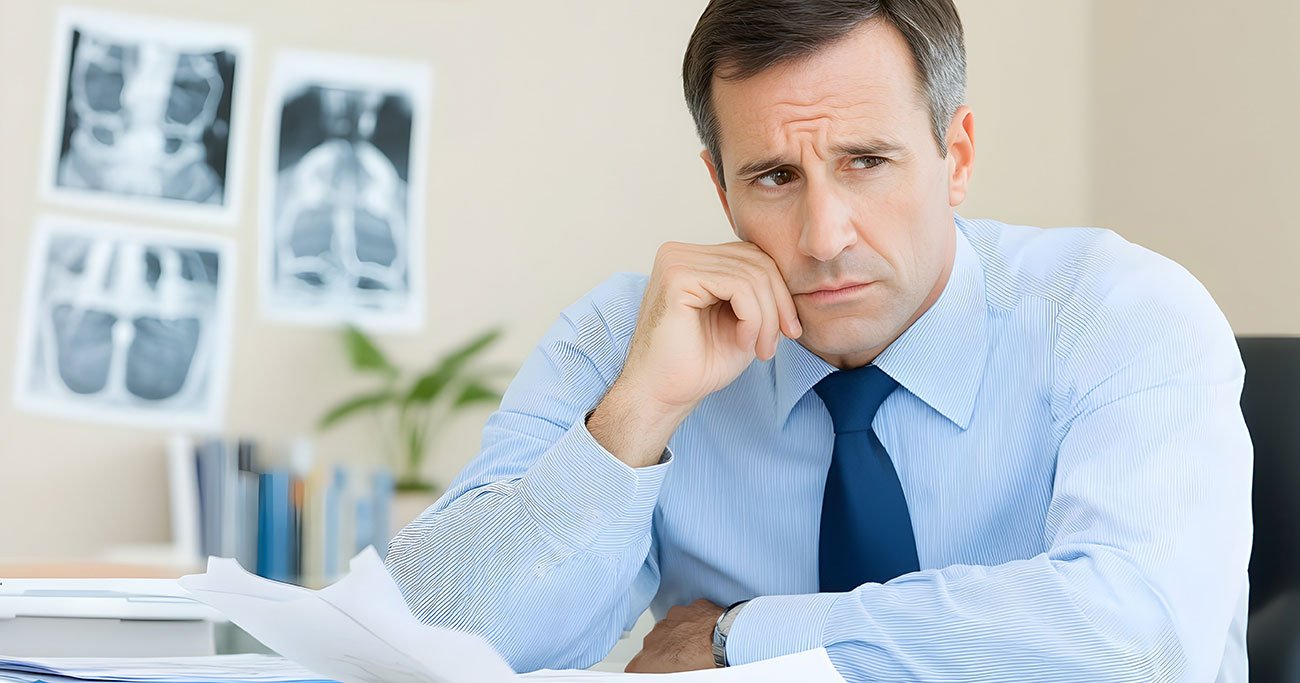 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「休暇は“どう”でした?」は良くない質問
質問には、よい質問とよくない質問があります。
よくない質問の代表が「なぜ?」「どうして?」と聞く質問です。その理由は、前回記事で説明した通り、相手の「思い込み」を引き出してしまい、それがコミュニケーションのねじれにつながるからです。
実はこの他にも、良くない質問はたくさんあります。
その代表的なものが、次のような質問です。
日々の会話の中で使わないほうが珍しいほど頻繁に使われているこの「どうですか/どうでしたか」に代表される「どう質問」には、大きな落とし穴があります。それは、「相手に負担をかける」という点です。今回はそれについて考えてみましょう。
「どう質問」は相手に負担を与える
具体的な例を見てみましょう。なお、本書で紹介する事例はいずれも私や私の仲間がこれまで経験してきた実際の事例をもとにしたものです。
例えばあなたが有給休暇をとった後、職場に戻ってきて、上司のAさんから先ほどのように尋ねられたとしましょう。
あなたはどう答えるでしょうか。正直、困りますよね。「良かったです」くらいしか、答えられないのではないかと思います。どこで何をしたかを答えればいいのか、楽しんだかどうかを答えればいいのか、あるいは期間は十分だったかを知りたいのだろうか……と、一瞬戸惑うはずです。
つまり、「どうでしたか」という質問は、尋ねるほうは気軽に、安易に尋ねられるものの、答えるほうには手間のかかる、面倒な質問なのです。
そもそも「どう?」質問をしているほうは、たいてい、特に聞きたいことがあるわけではありません。なんとなく、沈黙の気まずい雰囲気を避けようとして、特にこれといって聞きたいことが何かを考えずに、ただ相手に回答の負担を強いているのです。このような怠惰な質問では、相手との人間関係がよくなることは到底、期待できません。
賢い人は「事実」に絞って質問を継ぐ
ではこういった場合には、どのように聞くのがよいのか。
ここで解決策となるのが、本書で紹介する、事実に絞って具体的に質問する「事実質問術」です。「事実質問術」は、「いつ」「どこ」「だれ」などの、5W1H(ただしWhyとHowは除く)を使って、相手に細かく質問を継ぎ、コミュニケーションをしていきます。
「まるで刑事の尋問のようだ」と感じられる方も多いかもしれませんが、実は人は「自分が聞かれて嬉しいこと」に関して質問されるのは、あまり嫌がらない傾向があるようです。
例えばAさんから、次のような質問を受けたとします。
B:子どもと遊んでいました。
A:そうですか。お子さんは何歳なんですか?
B:2歳になったばかりです。
A:へぇ! お名前は?
B:◯◯です。
A:誰と決めたお名前なんですか?
B:祖父母と一緒に、いくつかの候補から決めました。
A:昨日はどこかに出かけましたか?
B:昨日は1日中、近所の公園で遊んでいました。ブランコが大好きみたいで、家に帰ってからも「また行きたいね」という話をしていました。
このように聞かれて、話しているときの自分を想像してみてください。「子どもについていろいろ聞いてくれて嬉しい」と思う人も、多いのではないかと思います。楽しい思い出について聞かれて、それを話すのは、嬉しいものですよね。
逆に刑事の尋問は、当然相手を疑ってかかり、時には答えづらい質問もするでしょうから、圧も感じることでしょう。しかし、事実質問術は、「相手が答えやすい質問をする」のが原則です。
対話は、どちらかが質問し、相手がそれに答えることから始まります。よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあり、よいコミュニケーションの出発点には、良い質問があるのです。
(本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)








