もっとも、いずれも最終受皿が見つかるまでのつなぎであり、業務も継続する点で共通している。さらにブリッジバンクで事業譲渡方式を取ると、巨大銀行の譲渡は大変な事務負担が発生した可能性はあった。いずれにせよ、当時の与野党協議の中で与党案は野党案に取り込まれ、与党案は事実上消え去っていた。
この間、金融再生法には最終局面で大蔵省が強く野党に働きかけ、ブリッジバンク方式も選べるように書き込まれた。それに基づき、2002年3月、石川銀行(2001年12月破綻)、中部銀行(2002年3月破綻)の破綻処理のためブリッジバンク(承継銀行)を預保の子会社として設立した例がある。ただ、同方式は事業譲渡で行われたこともあり、債権・債務、担保権の移転等に手間、費用がかかった。
拓銀処理よりマシだったが
金融危機を増幅した点では同じ
ブリッジバンク、一時国有化の両方の方式は、時限立法だった金融再生法が廃止になった後も預金保険法に盛り込まれ、ともに恒久措置となっている。一時国有化は規模の大きい銀行、ブリッジバンクは規模の小さな銀行、それぞれ破綻処理に用いられる。
拓銀処理と長銀処理とを比較すると、拓銀の場合は、(1)最終受皿の選定が付け焼刃で、受皿選定の基準もない。ただし、当局の意向は重い、(2)ビジネスモデル等(業務、店舗等)は当局が決定し、暖簾(その金融機関への信頼感)の維持といった観点は欠落、(3)借り手保護といった発想はなく、連鎖倒産も広範に発生するなど経済を下押し、(4)この結果、破綻処理費用も高くつく。
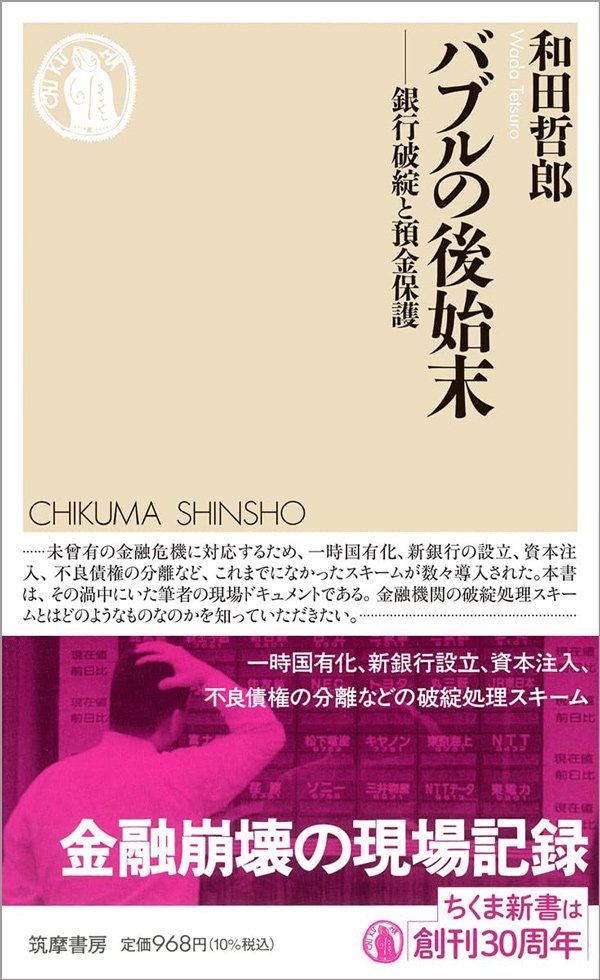 『バブルの後始末――銀行破綻と預金保護』(和田哲郎、筑摩書房)
『バブルの後始末――銀行破綻と預金保護』(和田哲郎、筑摩書房)
一方、長銀(特別公的管理)の場合は、(1)最終受皿は入札で決定され、透明性が高い、(2)ビジネスモデル等は最終受皿が決定するので、合理的、(3)最終受皿が決まるまで業務は継続され、また暖簾維持の観点から貸出回収、資産売却に走ることもない。
このように、長銀処理策は拓銀のケースに比しては、大きく改善している。
しかし、いずれも危機時における大手銀行の破綻処理であり、莫大な処理費用すなわち公的資金を費やしたほか、金融危機を増幅した点は同じである。







