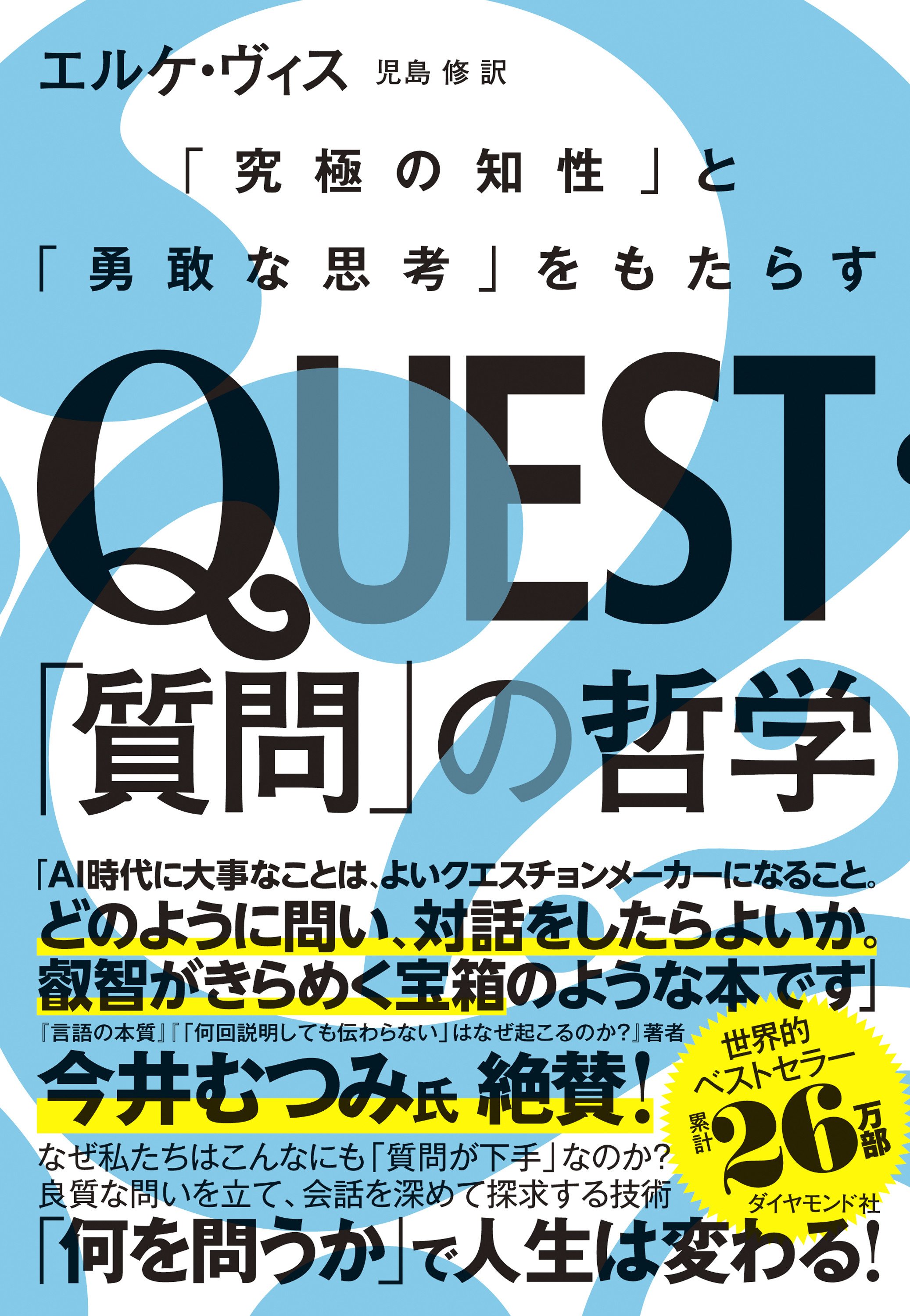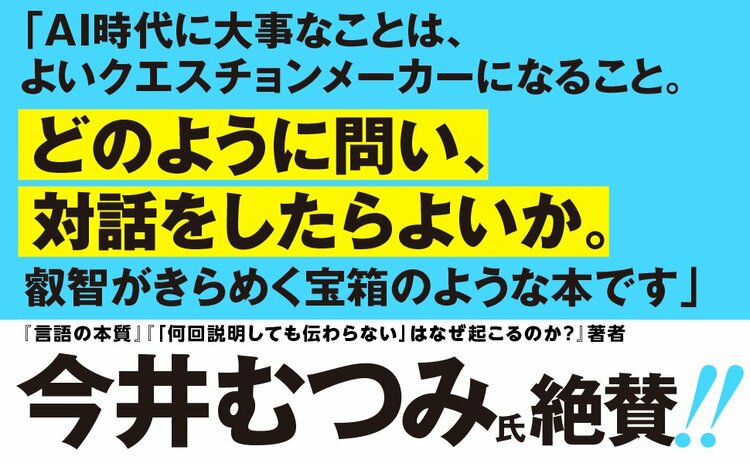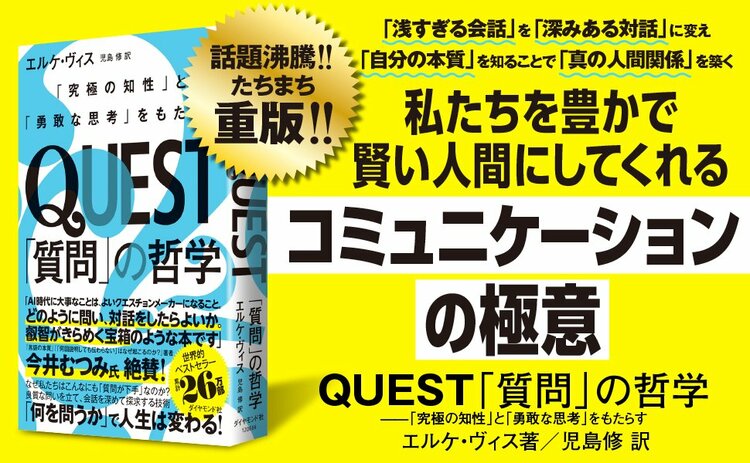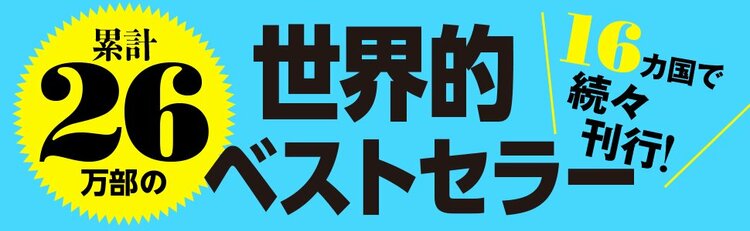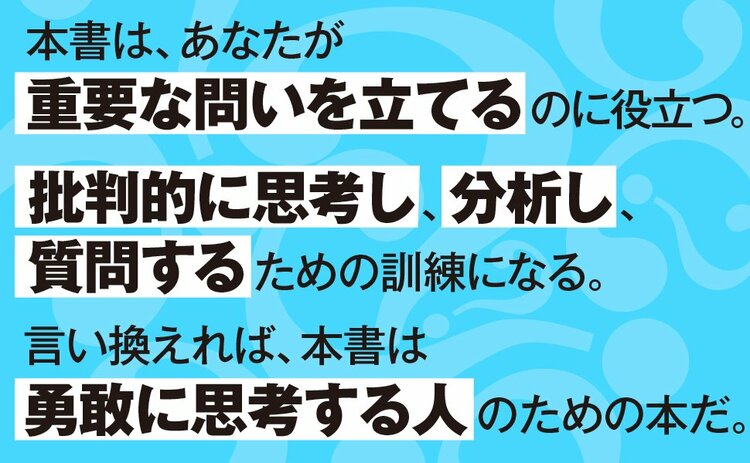「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
質問せず「知ったかぶり」をしてしまう
私たちが質問を躊躇してしまうのは、一般的に、質問をすることは周りに良い印象を与えないと考えられているからでもある。
質問をするということは、何かを知りたいということであり、つまり無知であること(少なくともその時点では)を暗示している。
「私はそのことがわかりません」と言うのは、あまり格好よくはないし、セクシーでもない。
それは印象を良くしないし、履歴書にも書けない。質問をすることは、自分を際立った存在にしたり、高い評価をされたり、昇進を勝ち取ったりすることには結びつきにくい。
今日の世界で求められているのはリーダーや意思決定者、人を鼓舞して物事を動かす人、仕事のできる人、自分の考えがあり自信をもって話す人、などだ。
私たちは、「知らないこと」と「愚かであること」をすぐに結びつけようとする。
勇気や恥、共感などを研究しているブレネー・ブラウンは著書『Braving the Wilderness(荒野に立ち向かう)』(未訳)の中で、次のように書いている。
記憶している限り、昨年、私は誰かに質問されたとき、意見を述べなかったことはない。
その問題について十分な視点や知識がなかった場合でもだ。(中略)相手に合わせることが重視される社会では、家庭や職場でも、大きなコミュニティでも、好奇心は弱点と見なされる。
質問をすることは、学ぶ意欲があると評価されるのではなく、反感を買うことに等しい。
知らないことや疑うことに「劣っている」というレッテルを貼ることで、私たちは良い質問をする代わりに、無知な意見がはびこる温床をつくっている。
自分の無知を隠すために、深く分析的な会話を避け、コーヒータイムの雑談でお茶を濁す。疑問ばかり抱いている愚か者と思われないように、知ったかぶりをする。
「質問をする人や疑問をもっている人は自信がない。自信がない人は相手にする価値がない」。
こうした考えのもと、私たちは自らを有能に見せるために、自分の意見を客観的な事実として話そうとする。
(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)