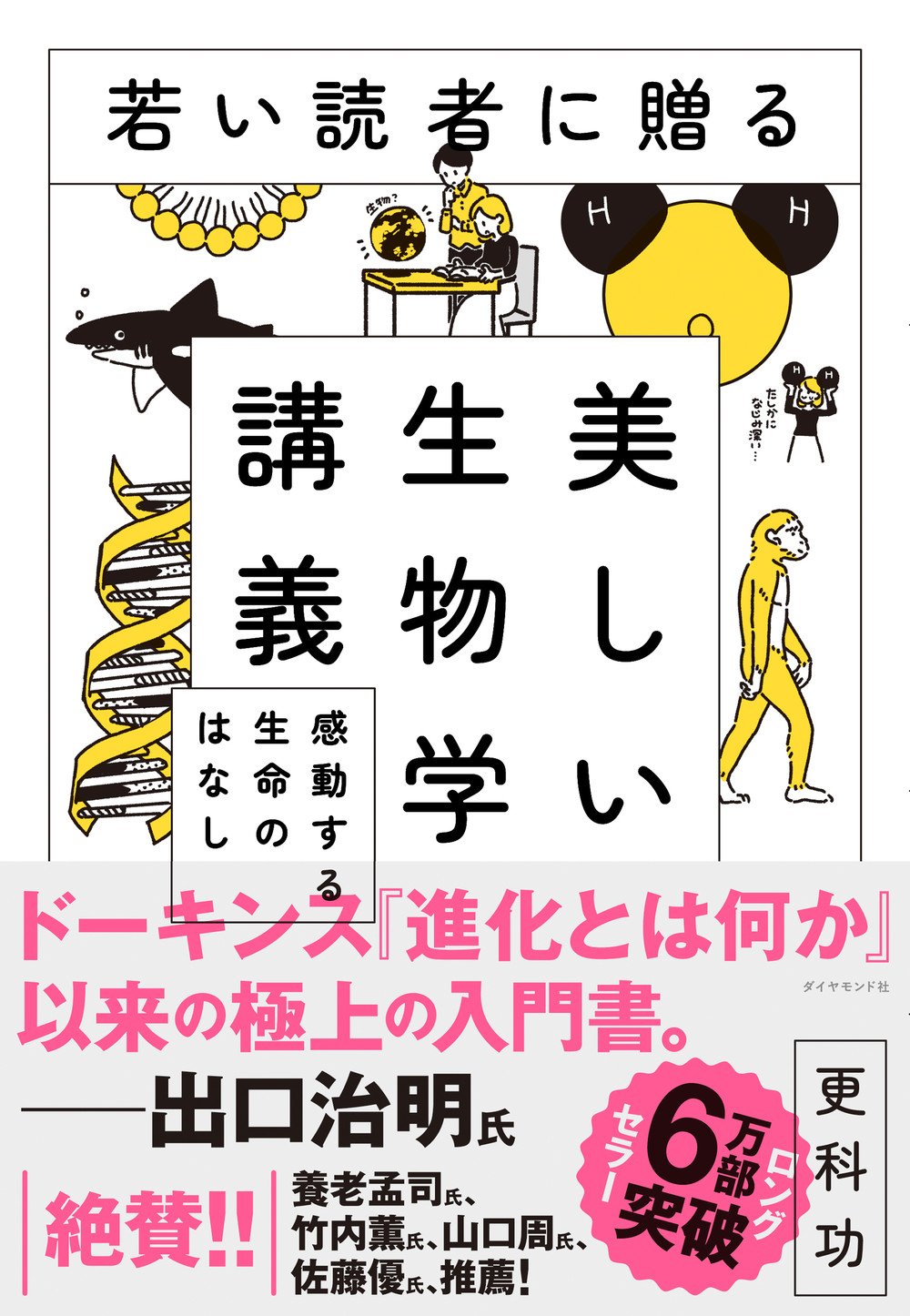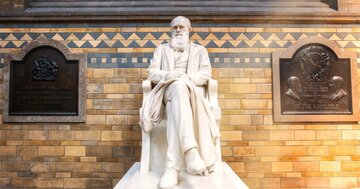分子古生物学者である著者が、身近な話題も盛り込んだ講義スタイルで、生物学の最新の知見を親切に、ユーモアたっぷりに、ロマンティックに語るロングセラー『若い読者に贈る美しい生物学講義』。養老孟司氏「面白くてためになる。生物学に興味がある人はまず本書を読んだほうがいいと思います。」、竹内薫氏「めっちゃ面白い! こんな本を高校生の頃に読みたかった!!」、山口周氏「変化の時代、“生き残りの秘訣”は生物から学びましょう。」、佐藤優氏「人間について深く知るための必読書。」、ヤンデル先生(@Dr_yandel)「『若い読者に贈る美しい生物学講義』は読む前と読んだあとでぜんぜん印象が違う。印象は「子ども電話相談室が好きな大人が読む本」。科学の子から大人になった人向け! 相談員がどんどん突っ走っていく感じがほほえましい。『こわいもの知らずの病理学講義』が好きな人にもおすすめ。」、長谷川眞理子氏「高校までの生物の授業がつまらなかった大人たちも、今、つまらないと思っている生徒たちも、本書を読めば生命の美しさに感動し、もっと知りたいと思うと、私は確信する。」(朝日新聞書評)と各氏から評価されている。今回は書き下ろし原稿を特別にお届けする。
クモの巣と自然淘汰
チャールズ・ダーウィンの『種の起源』が出版された1859年以来、生物は自然淘汰というメカニズムによって進化してきたことが広く知られるようになった。キリンの長い首やハヤブサの翼など、目を見張るような生物のすばらしい形質は、すべて自然淘汰によって作り出されたものである。
しかし、自然淘汰が作ったものは、生物の体だけではない。生物の体の外側にあるものも作ることができる。たとえば、クモの巣だ。クモの巣には、立体的な網や、扉のついた地中の巣穴など、いろいろなタイプの巣があるが、もっともよく目にするのは、円網(えんもう)と呼ばれる放射状の糸にらせん状の糸が張られた巣であろう。
これらの巣は、獲物を捕らえる罠や棲み家として使われているが、最初から現在のように、みごとな巣だったわけではない。おそらく最初は単純で、罠としてもあまり役に立たなかっただろう。それを、罠としても棲み家としても優れたものに作り上げたのは自然淘汰の力である。自然淘汰の作用は、生物の体を超えて、その外側まで広がっているのだ。
人体には40兆の細胞が棲んでいる
そして、そのような体を超えた自然淘汰の力は、私たち人間にも確実に働いている。その一つの例が、私たちの体の中に棲んでいる腸内細菌である。
私たちヒトの腸の中には、非常に多くの細菌が生息している。私たちの体はおよそ40兆個の細胞でできているが、その数とほぼ同じくらいの細菌が、私たちの腸の中に棲んでいる。ちなみに、過去50年間にわたって、腸内細菌の数は私たちの体の細胞数の10倍以上に達すると推測されてきたのだが、さすがにその推測は多過ぎたようだ。とはいえ、体の細胞と同じくらいだとしても、たいへんな数であることに変わりはない。
私たちは、これらの腸内細菌に、暖かくて住みやすい環境と十分な食物を提供する。その見返りとして、腸内細菌は、私たちの消化を助けたり、病原体から私たちを守ったりしてくれる。
たとえば、私たちは、植物に含まれるセルロースを消化できないので、腸内細菌の力を借りて消化している。私たちが自分で作れる消化酵素は約20種類に過ぎないが、腸内細菌は1万種類ほどの消化酵素を作れるので、腸内細菌の力を借りないと消化できないものが、たくさんあるのである。
腸内細菌はどのように増えるのか
また、腸内細菌は、私たちの腸の内表面を棲み家として占拠している。じつはこれが、感染に対する有効な防御となっている。なぜなら、病原体も棲み家がなければ生きていけないからだ。
ただし、人によって、腸内に生息している細菌の種類はかなり異なるらしい。私たちが母親の子宮の中にいるときは、まだ腸の中に腸内細菌はいなかった。その後、生まれるときに産道を通ったり、生まれたあとで家族や友人と交流したりする過程で、腸内細菌が増えていく。そのため、人によって腸内細菌を構成している種はいろいろだが、不思議なことに、腸内細菌が持っている遺伝子の機能を見ると、どの人もだいたい同じらしい。
つまり、人によって腸内細菌の「種の組み合わせ」は違っていても、「遺伝子の機能の組み合わせ」は同じということだ。このように、全体としての「遺伝子の機能」が同じになっているということは、「遺伝子の機能」に対して自然淘汰が働いていることを示している。
クモには巣が必要なように…
結局、私たちが腸の中に腸内細菌を棲ませている理由は、「腸内細菌の遺伝子が必要だから」なのだろう。私たちヒトは、遺伝子を約2万個しか持っていないが、腸内細菌の遺伝子は数百万個から一千万個以上に達する。クモが生きていくためには巣が必要なように、私たちが生きていくためには腸内細菌の遺伝子が必要なのだ。
私たちは一人で生きているわけではない。私たちヒトは、私たち自身の遺伝子と腸内細菌の遺伝子から成り立つ超有機体なのである。
(本原稿は『若い読者に贈る美しい生物学講義』の著者更科功氏による書き下ろし連載です。※隔月掲載予定)
更科 功(さらしな・いさお)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授、東京大学大学院非常勤講師。『化石の分子生物学』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に『宇宙からいかにヒトは生まれたか』『進化論はいかに進化したか』(ともに新潮選書)、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史』(NHK出版新書)、共訳書に『進化の教科書・第1~3巻』(講談社ブルーバックス)、6万部突破のロングセラー『
若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。
くつろいで受けられる生物学講義――著者より
ある農家に怠け者の男がいた。男は働くのが面倒でたまらないので、自分の代わりに田畑で働いてくれるロボットを作った。
ところが、ひと月経つと、ロボットは壊れてしまった。仕方なく、男はまたロボットを作った。ところが、そのロボットも、ひと月経つと壊れてしまった。
そこで男は、新型のロボットを作った。新型のロボットは、田畑で働くだけでなく、ひと月経つと新しいロボットを作って、それから壊れた。だから、男は、一日中家で寝ていられた。
そんな折、男は作られるロボットが、少しずつ違うことに気がついた。
たとえば、性能が1のロボットが作ったロボットの性能は、1.1になることも0.9になることもあった。しかしロボットの性能が、急激に変化することはなかった。
そのうちに、たまたまロボットを2体作るロボットができてしまった。ところが、男の家には、ロボットを動かす燃料は1体分しかない。
ロボットは、毎日農作業が終わって家に戻ると、燃料タンクから自分で燃料を入れることになっていた。そのため、農作業が早く終わったロボットが、先に家に戻って燃料を入れてしまう。すると、もう1体のロボットは燃料を入れることができない。そのため、燃料切れになったロボットは、家の隅に転がったままになった。
そんなことが繰り返されていくうちに、ロボットの農作業はものすごく速くなった。生き残るのは、いつも性能が高いロボットだけだからだ。仮に、毎月性能が1.1倍になったとすれば、4年で、ほぼ100倍になる。ロボットは、急速に変化していき、もはや怠け者の男にはコントロールできないものになってしまった。
ついにロボットは、自分で燃料を採掘するようになり、とうとう地球を支配するにいたった。もはや人間の姿は、どこにも見当たらなかった。
以上の話は『若い読者に贈る美しい生物学講義』の中に書いた話(の一部)である。ロボットが2体ずつ作られて、そのうちの1体だけが生き残るなら、そのときの状況に適応している方が生き残ることになる。これは自然選択と呼ばれる現象で、ダーウィンが進化のメカニズムとして見つけたものだ。
この話では、自然選択が働き始めたときに、ロボットの急速な変化が始まった。それは、もう元には戻れないような、根本的な変化であった。この瞬間にロボットは生物になったのだと、私は思う。
これまでは、生物とはどういうものかを考えるときに、物質的な側面から考えることが多かった。たとえば、地球の生物の体のなかでは、いつも物質やエネルギーが流れている。この流れを代謝というが、これを生物の定義の一つとすることが多い。
しかし、宇宙にはどんな生物がいるかわからない。たとえば、ロボットの体の中には、いつも物質やエネルギーが流れているわけではない。スイッチを切って寝ていれば、物質もエネルギーも流れない。それでも、宇宙のどこかに、さっきの話のようなロボットがいたら、それは生物と言ってもよいかもしれない。地球の常識から言えば、金属でできたロボットは生物ではないけれど、それは宇宙の常識とは違うのではないだろうか。
もしも、宇宙全体で生物を定義できるものがあるかどうかわからないが、もしあるとすれば、それは「自然選択」だろう。どんな形をしていようが、どんな物質でできていようが、どんな振る舞いをしようが、とにかく自然選択によって作られたものが生物なのではないだろうか。生物は自然選択によって、周囲の環境に適するようになったものだ。つまり、その環境の中で、なかなか消滅しないようになったものだ。つまり、生き続けるようになったものなのだ。
だから、本来生物は、生きるために生きているのであって、生きる以上の目的はないのだろう。生きるために大切なことはあっても、生きるよりも大切なことはないのだろう。まあ、生きていれば、それだけで立派なものなのだ。
『若い読者に贈る美しい生物学講義』では、従来の生物の見方に収まらない話も盛り込んでみた。
内容を簡単に紹介すると、まず生物とは何かについて考える。その中で、科学とは何かについても考えていく。生物学も科学なので、その限界を理解しておくことが大切だからだ。それから実際の生物、たとえば動物や植物などの話をしてから、生物に共通する性質、たとえば進化や多様性について述べる。最後に身近な話題、たとえばがんやお酒を飲むとどうなるかについて話をする。「講義」という言葉が入っているが、くつろいで受けられる講義にしたつもりである。
楽しんでもらえると、よいのだけれど。
■新刊書籍のご案内
☆6万部突破のロングセラー!!☆
出口治明氏
「ドーキンス『進化とは何か』以来の極上の入門書。」
養老孟司氏
「面白くてためになる。生物学に興味がある人はまず本書を読んだ本がいいと思います。」
竹内薫氏
「めっちゃ面白い! こんな本を高校生の頃に読みたかった!!」
山口周氏
「変化の時代、“生き残りの秘訣”は生物から学びましょう。」
佐藤優氏
「人間について深く知るための必読書。」
生命とは、進化とは、遺伝とは、死とは、多様性とは、生き延びるために必要な生存戦略とは――。本書は、読者に向けて、生命とは何かを平易な言葉で伝える、いままででいちばんわかりやすく、いちばん感動的な生物学の本となる。後半の病気に関連した部分は、医学的な解説ではなく、生物としてどのような現象が起こっているのかを解説する。
生物とは何か、生物のシンギュラリティ、動く植物、大きな欠点のある人類の歩き方、遺伝のしくみ、がんは進化する、一気飲みしてはいけない、花粉症はなぜ起きる、IPS細胞とは何か…。最新の知見を親切に、ユーモアたっぷりに、ロマンティックに語る。あなたの想像をはるかに超える生物学の授業! 全世代必読の一冊!!
きっと、どんなことにも美しさはある。そして美しさを見つけられれば、そのことに興味を持つようになり、その人が見る世界は前より美しくなるはずだ。きっと生物学だって、(もちろん他の分野だって)美しい学問だ。そして、この本は生物学の本だ。もしも、この本を読んでいるあいだだけでも(できれば読んだあとも)、生物学を美しいと思い、生物学に興味を持ち、そしてあなたの人生がほんの少しでも豊かになれば、それに勝る喜びはない。(本書の「おわりに」より)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock