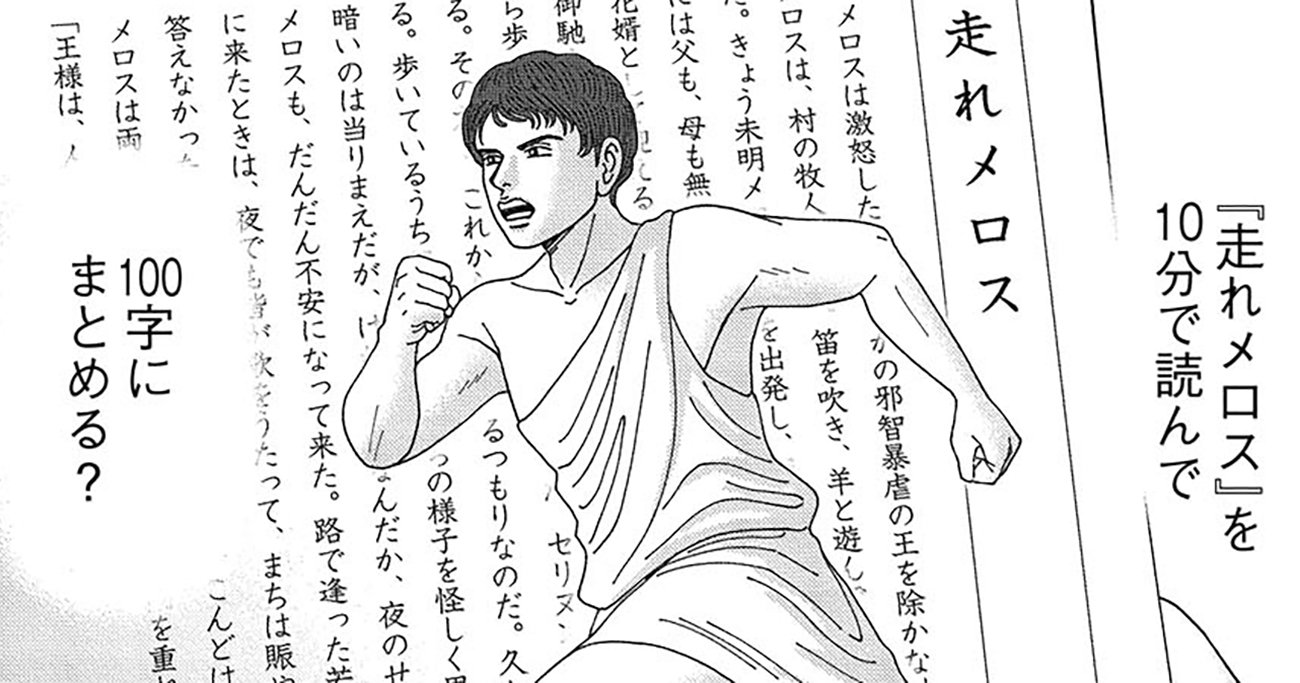 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第42回は「起承転結のメリット、デメリット」について考える。
英語と日本語の明らかな違い
国語科特別講師として龍山高校東大専科に着任した太宰府治は、「『走れメロス』を要約せよ」という課題を出す。生徒の解答にダメ出しをした太宰府先生は、文章は美しい論理構造により成り立っている、と力説するのだった。
受験勉強全体を通してトップクラスに口酸っぱく言われたこととして、「日本語と英語の論理展開は違う」というものがある。英語では、一文の構造と同じく、文章全体においても結論を先に述べる傾向が強い。
英語の教材として学習する論説文やビジネス文書では特に、最初に主張を明確にし、その後に理由や補足を加えていく。英語の授業で、「大きなことから小さなことへ」という口癖とともに黒板に書かれた逆三角形が脳裏に浮かぶ。
一方、日本語では、結論を最後に持ってくることが多く、論理展開が異なっている。論説文でさえ、最初に問題が提起され、その問題についてあれこれと吟味していき、最後に解決策を提示している。序盤に結論をいう場合でも、あえて抽象的な表現にとどめておき、最後に丁寧な説明を加える場合が多いように感じる。
ご存じのように、日本語の文章には「起承転結」という構造がある。その意味についてわざわざ説明するまでもないだろうが、「糸屋の娘」という唄が秀逸だ。
「京都三条糸屋の娘。姉は十六、妹は十四。諸国諸大名は弓矢で殺す。糸屋の娘は目で殺す」
無理やり「転」を加えることは「事実への脚色」だ
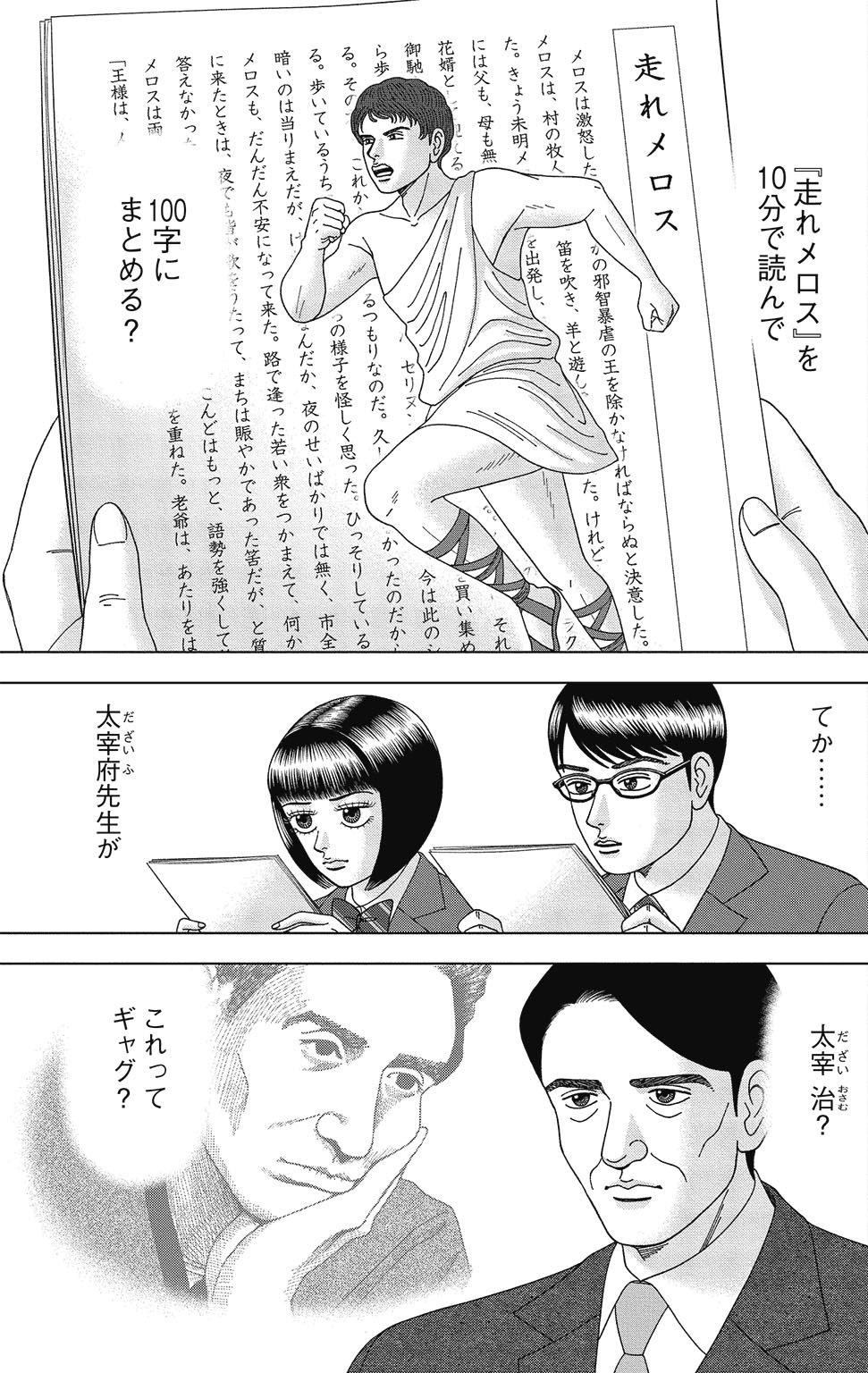 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
「起承転結」は物語やエッセイにおいてよく用いられる技法だが、一般的な説明文や論説文にも影響を与えている。しかし、英語の文章でも「起承転結」のような構成が用いられることはあるものの、それはあくまでも装飾的なものであり、論理の本質ではない。英語では、結論を明確に伝え、読み手に理解しやすい形で展開することが重視される。
英語の論説文を読むと、どことなく単調でつまらないと感じることがある。それは、物語的な展開やドラマ性が希薄だからだろう。その一方で日本語の「起承転結」を基盤とした文章は、美しく、読み応えがある。しかし、考えてみるとこの思考は危険だ。
起承転結も万能ではない。「転」の部分では、意外性やストーリー性を求めるあまり、事実をゆがめたり、不必要に誇張したりすることが起こり得る。特に、論説文や報道記事において、この構造を無理に当てはめることで、現実を正しく反映できなくなる可能性がある。
例えば、ある問題について論じる際、読者の感情を揺さぶろうと、不要なドラマ性を持たせる。すると、本来は単純な事実関係が複雑に見えてしまう。また、極端な意見を取り上げ、それがあたかも普遍的な真実であるかのように誤認させるリスクもある。
以前、とあるエッセイストの方に言われたことが頭に残っている。
「起承転結は、それ自体が一種の虚構性をはらんでいる。日常のものごとは『承』から『転』を経ずに『結』に至ることの方が圧倒的に多い。それなのに無理やり『転』を加えることは、事実への脚色である」
情報の正確性が求められる場面では、起承転結に固執せず、英語的な「結論先行型」の文章構造を採用することが、より適切な場合もある。情報を正しく伝え、誤解を防ぐためには、文章の構成についても柔軟に考えることが必要なのではないだろうか。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク






