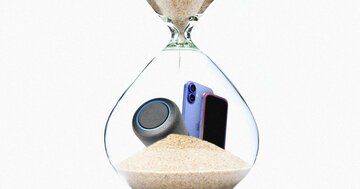Photo:Bloomberg/gettyimages
Photo:Bloomberg/gettyimages
ドナルド・トランプ米大統領が2日に約束したのと同じくらい劇的な関税引き上げを米国が前回実施したのは、1930年のことだった。
大半の歴史家は、同年にハーバート・フーバー大統領が署名してスムート・ホーリー法を成立させた後に起きたことを説明できる。世界貿易は崩壊し、恐慌に陥りかけていた世界の流れに追い打ちをかけた。
トランプ氏の発表と中国の報復措置を受けた株価暴落は、同じような結果を予感させる。無理もない。トランプ氏の関税は1930年代に実施されたものより引き上げ幅がはるかに大きいのだ。
だが、世界が必然的に1930年代を繰り返す運命にあるわけではない。今回の貿易戦争への支持は極めて限られている。これまでのところ中国を除けば報復は抑制されている。たとえ米国が内向きになりつつあるとしても、大半の国々には貿易と開放に代わる選択肢がないからだ。
米国内でさえ、主な関税支持勢力は、1987年以来貿易戦争がしたくてうずうずしていたトランプ氏だけだ。世論は関税を支持しておらず、市場や経済への打撃が大きくなれば反発が高まる公算が大きい。議会共和党も関税に消極的だ。こうした状況が示唆するのは、2日の関税発表後に起きた混乱にもかかわらず、最悪の事態を想定するのは時期尚早だということである。
トランプ氏の関税が経済にもたらす衝撃は、スムート・ホーリー法の時より大きい。当時の米国は既に平均関税率が36%に達する高関税の国だった。「Clashing Over Commerce: A History of U.S. Trade Policy(米国通商政策史)」の著者ダグ・アーウィン氏によると、関税率は同法によって6ポイント上昇しただけだった。上昇幅はその後19ポイントに拡大したが、これは関税が金額で固定されており、恐慌で物価が下落したことで関税の比率が高くなったためだ。
トランプ氏は約2%の平均実効関税率を引き継いでおり、複数のエコノミストの試算によると、それが新たな関税によって23%に上昇する。消費に輸入品が占める割合がより大きいため、新関税は1930年代より多くの経済活動に打撃を与えるだろう。