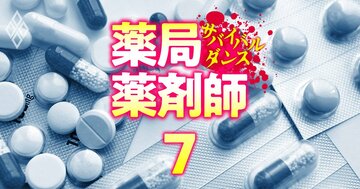写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
*本記事は医薬経済ONLINEからの転載です。
「骨細だ」「骨抜きになった」
政府が毎年6月をメドに策定する、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる「骨太の方針」をめぐっては、中身が明らかになるたびに、名前に絡めた批判が絶えない。それでも、01年の小泉純一郎首相時代から、自民党政権では、この手法が長く用いられている。
09~12年、民主党政権時代の3年間は骨太の方針がつくられることはなかった。復活したのは、安倍晋三首相が返り咲きを果たしてからだ。13年以降、首相は安倍氏から菅義偉氏、岸田文雄氏、石破茂氏と交代してきたが、骨太の方針をつくり、年末の予算編成につなげる仕組みは変化していない。
製薬業界はそれに合わせて毎年、骨太の方針が決まる前に政府・与党へのロビー活動を精力的に行い、年末の予算編成に向けた「弾込め」をしてきた。例えば、今年も日本製薬団体連合会が3月下旬、「骨太の方針2025」策定に向け、与党に対して4点を要望している。薬価については「歴史的転換期(デフレからインフレ)における新・薬価制度の構築」を掲げた。新・薬価制度の構築というのは「革新的新薬・長期収載品/後発品・基礎的医薬品からなるカテゴリー別の薬価制度の構築」を指す。
では、これまで骨太の方針に盛り込まれた内容が、実際の薬価制度改革(改定)にどのように反映されてきたのか。過去10年の対応関係を表に示した(表は次ページ掲載)。