医薬経済ONLINE
日本生命保険は2025年12月、医療データの収集・分析を手がけるメディカル・データ・ビジョン(MDV)を買収すると発表した。異例のプレミアムを付けて株式公開買い付け(TOB)で全株式を買い取る。日本生命が描く「非保険領域」の青写真とは?

三菱ケミカルグループだった旧・田辺三菱製薬は1年のうちに、米ベインキャピタル参加となり、社名変更し、虎の子事業を売却と怒涛の展開を迎えた。この国内最古の製薬企業について、ベインはどう出口戦略を描くのか。ここから先、光は差すのか。

久光製薬はMBO(経営陣による買収)で株式非非公開化することを年明けに公表した。同社が得意とする貼付薬も対象となるOTC類似薬の保険外しの議論が影響していると業界関係者と見る中、上場製薬会社トップは同社に羨望のまなざしを向ける理由とは?

「スズケンの第二の創業者」と呼ばれてきた別所芳樹最高顧問が2025年12月に亡くなった。別所氏を失った医薬品卸大手が抱える難事が「後継者問題」と「合併構想」だ。

日本ハムが早稲田大学発ベンチャーであるCoreTissue BioEngineering(CTBE)に出資した。スポーツで膝の靭帯を断裂すると、患者自身の別部位の腱を使って再建する。この手術でウシの腱を利用しようというものだ。

製薬業界の自民党への政治献金が減少している。献金をしても薬価は下がり続け、毎年改定(中間年改定)も見直されないためだ。日米での献金実情をレポートする。
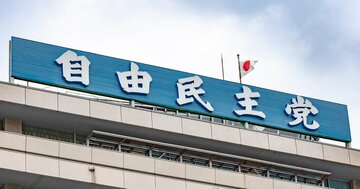
2025年4月、経済産業省の若手チームが「デジタル経済レポート」なる報告書をまとめた。24年の日本のデジタル関連収支は6.85兆円の赤字であったという。日本全体が外資系デジタルサービスに非可逆的に依存してしまっているため、今後、彼らへの依存度が最も悲観的なシナリオで進んだ場合、35年にはデジタル赤字の額は45兆円にまで膨らむと試算した。

旭化成は2024年9月、全額出資する旭化成メディカルが手がける血液浄化事業を国内投資ファンドのインテグラルに売却すると発表した。医療機器専業メーカーとして新たなスタートを切ることになった旭化成メディカルの稲留秀一郎社長にインタビューした。

12月発売のジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新生「企業連合」による販売力が試される。単独では大手に圧倒されていたプロモーション活動も、規模的には太刀打ちできるようになる。

製薬大手、エーザイの2026年3月期の売上高予想は7900億円。同社は今後下振れする可能性もあるとしているが、一部の証券会社は8000億円の大台乗せもあり得ると見込む。下半期の動向次第では、16年ぶりとなる売上高のピーク更新も夢物語ではない。今後気になるのは“既定路線”と目される名物CEOからその長男へのバトンタッチがうまくいくかどうかだ。

現実味を帯びて改革が進んでいきそうで、製薬業界の関係者が固唾を飲んで見つめる「OTC(大衆薬)類似薬の保険外し」。15年近く前から毎年、初夏頃までに浮上しては12月の予算編成を待たずに消えていく昆虫のような流転を見せていた。ところが今年は例外的に生き延びて、初めて2026年度予算に痕跡を残せそうな機運となっている。影響を受ける製薬会社はどこか。

現在の国内製薬業界は「内資」か「外資」かを重視する。それ故、実質的に米国を拠点とする武田薬品工業が業界団体の会長職に鎮座し、日本発の新薬が相次ぐのにスイス・ロシュが6割近い株式を握っている中外製薬は現状、トップに立てないのである。

自民と維新の「連立政権合意書」において社会保障政策で真っ先に打ち出したのが、OTC(大衆薬)類似薬を含む薬剤自己負担の見直し、金融所得の反映などの応能負担の徹底である。社会問題化している病院と介護施設の経営難への対応も明記している。2025年度補正予算と、診療報酬・薬価改定が絡む26年度予算編成の動向を占おう。

新政権の誕生により、創薬戦略でも「高市カラー」が出る。10月24日に初の所信表明演説に臨んだ高市早苗首相は創薬という言葉こそ使わなかったが、「健康医療安全保障」の項目を設け、女性特有の疾患対策にも触れた。健康医療安全保障は自民党総裁選で掲げた公約のひとつで、ほかにも原薬生産の国内完結体制やCBRNEテロ(化学・生物テロ)対策が含まれる。要するに製薬企業にも「国防」が求められるということを意味する。

東京グロース市場に上場するバイオベンチャー「ハートシード」は9月30日、開発中の再生医療技術について、提携先のノボノルディスクから解約の通知を受け取ったと発表。株価が急落して3日連続でストップ安となった。バイオベンチャーの市場での脆さが露呈した。

米コダックと対比される、富士フイルムホールディングスの秀逸ぶり。古森重隆元会長の名経営者ぶりが日本のメディアでは頻繁に報じられる。しかし、それは本当に揺るぎないファクトなのだろうか。同社がヘルスケア分野で最も自信を持っているように見えるバイオCDMO(医薬品開発製造受託)事業についても、予断を排して眺めると、決してバラ色の未来ではないことが浮かび上がる。

経済成長を優先する「積極財政派」で知られる自民党の高市早苗氏が首相の座に就くことで、薬剤費を含む医療費に対して、パイが膨らむことに“寛容”な政権となるのか。

日医工、共和薬品工業、T’sファーマを抱える「アンドファーマ」は後発(ジェネリック)医薬品業界再編の有力な軸と見做され、今後どの企業が合流するのかと業界関係者の耳目を集めていた。「総合商社ほど製薬と相性が悪いものはない」が通説だったが、資本参加に名乗りを上げた社の一つは伊藤忠商事だった。

医療機器大手のテルモは8月、英国の新興医療機器メーカー・オルガノックスを約2200億円で買収すると発表した。テルモはオルガノックスを橋頭堡として臓器移植領域に進出する。ただテルモの経営を俯瞰した場合、焦点となるのは大型買収の成否よりもむしろ、連結売上高の8割弱を占める海外事業、なかんずく米国と中国ビジネスの行方である。

元武田薬品工業CFO(最高財務責任者)、コスタ・サルウコス氏が9月1日付で、田辺三菱製薬の取締役会長に就任した。武田薬品を去ってわずか1年での日本復帰。米投資ファンドのベインキャピタルに買収された田辺三菱ということで、武田薬品の元社員からは「田辺三菱もコストカッターの餌食か」と心配されている。
