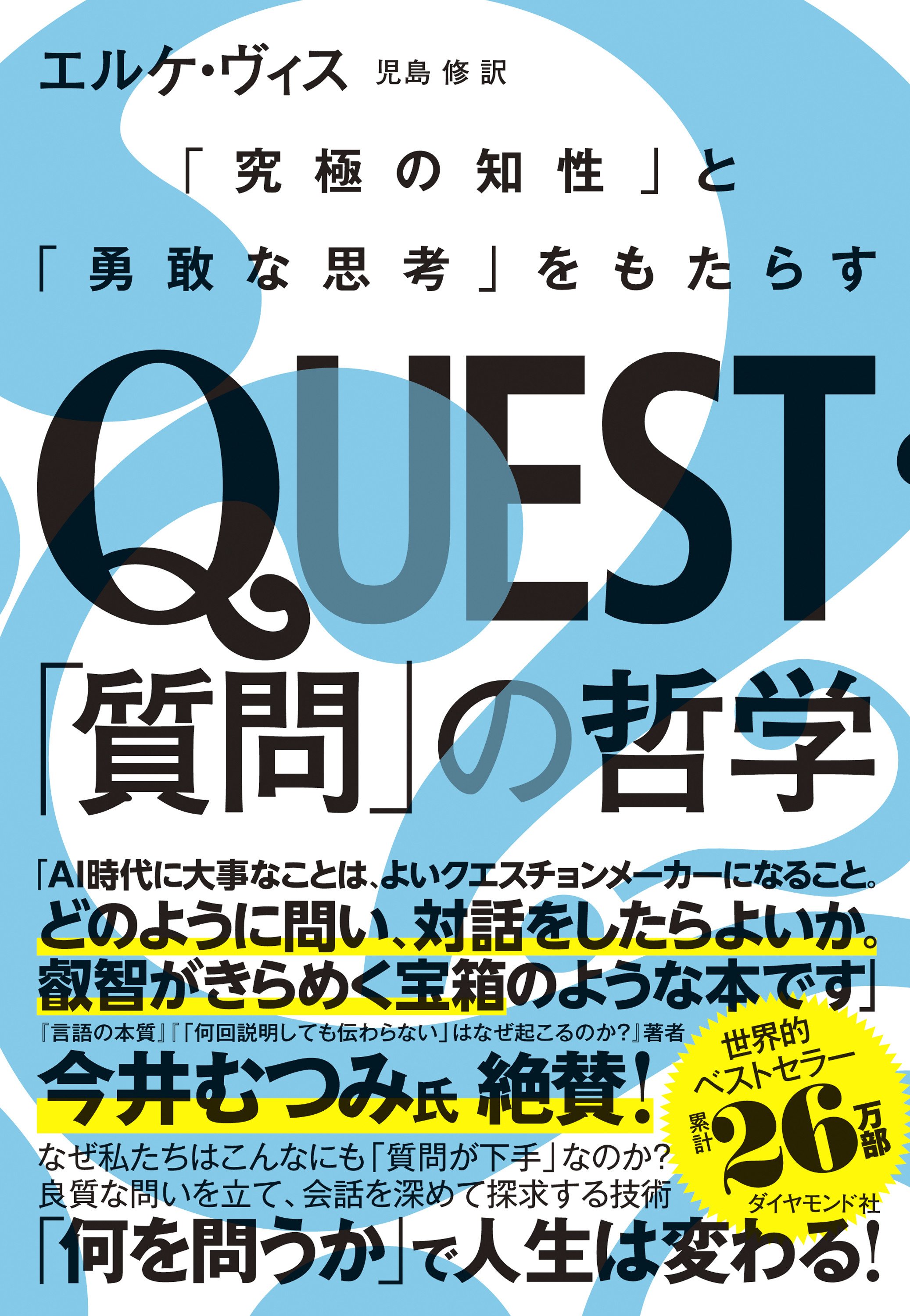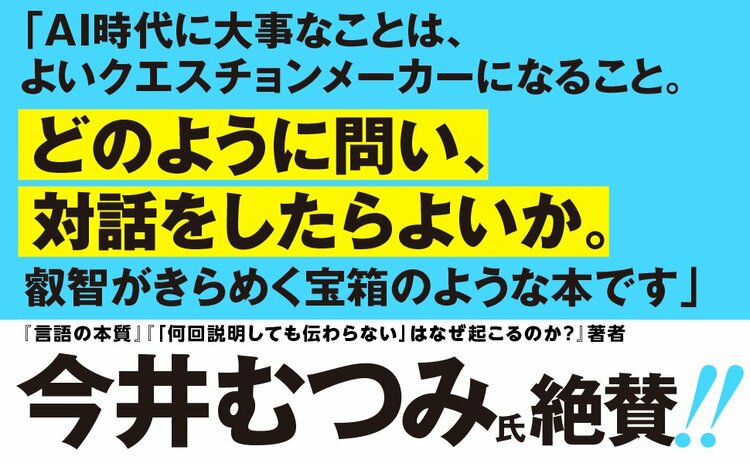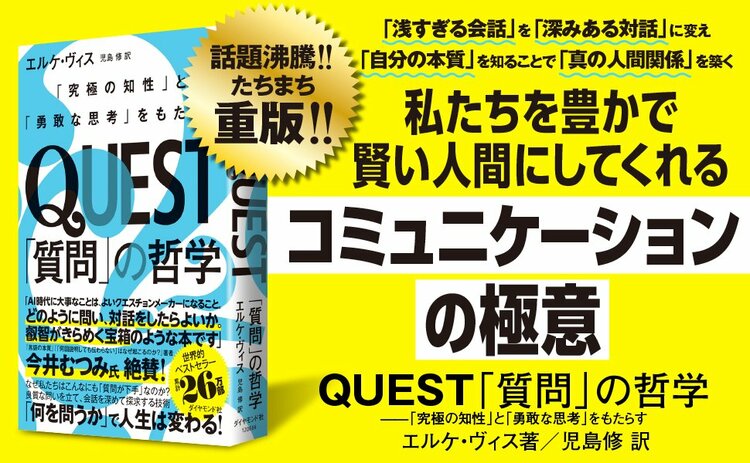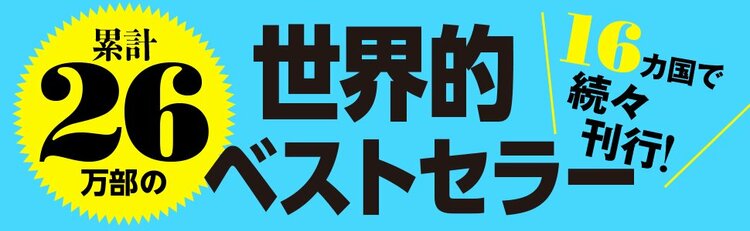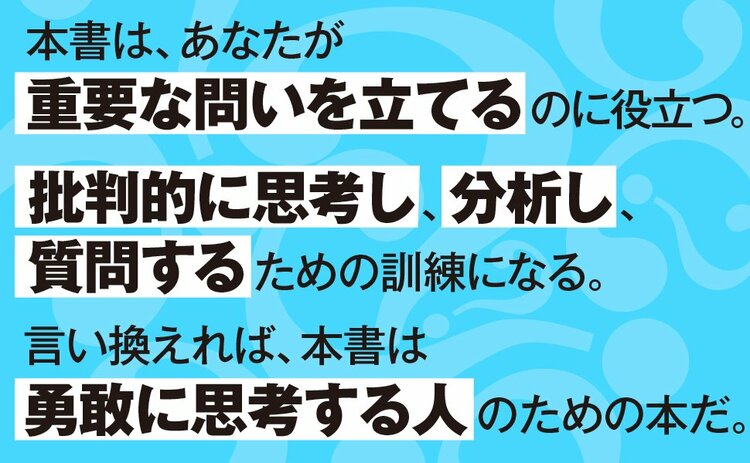「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
共感するより大切なこと
ある程度の距離を保つことが適切な状況では、必要なのは共感ではなく思いやりだ。
思いやりは相手を助けたいという気持ちを生む。
出来事を俯瞰し、自らの感情にとらわれることなく、相手の話を聞き、分析できる。
共感を棚上げしてこそ、価値のある質問ができる。
ソクラテス式問答法では、これは「共感的中立性」として知られている。
一定の距離を保って批判的な質問をするために、相手の感情や苦しみを共有しようとするスイッチを切るのだ。
感情やその表現を、肯定も否定もせずに認識する。
会話中に共感的な反応が始まり、「助けたい」「ヒントを与えたい」「自分の経験を伝えたい」という考えにかられ、実際にそうしてしまうと、相手の思考の流れが止まってしまう。
共感的中立性を保っていれば、相手は自力で深く掘り下げて考えることができる。
状況によっては、それはあなたが相手に与えられる最大の贈りものになる。
共感的中立性があれば、質問を続けやすくなる。
相手と会話のテーマから距離を保ち、どんな質問をすれば相手をさらに考えさせ、洞察を深め、思考を助けるかを吟味できる。
もちろん、これは注意深い傾聴とも密接に関連している。
同情の言葉で安心させない
ソクラテスは共感を一時的に封印することに長けていた。
会話の中で、事実や議論、仮定に対して容赦なく疑問を投げかけた。
共感的中立性を保つことで、相手を不安にさせたり、怒りや羞恥心を抱かせたりすることにもなった。
ソクラテスが、同情的な「ああ、言いたいことはわかるよ」「そうか、残念だったね」といった言葉で相手を安心させなかったからだ。
こうした容易な共感を拒否したからこそ、ソクラテスとの会話は価値のあるものになったのだ。
相手は、自分の考えが妥当なものであるかどうかを真剣に考えるようになった。
概念を別の視点からとらえるようになった。新しい発想を抱く余地が生まれた。
もしソクラテスが「ああ、君が困っているのがわかるよ。本当に辛いよね。さあ、ビールでも飲みに行こう」と共感的に対応していたら、真摯な対話から生まれる深い理解は得られなかっただろう。
しかし、私たちは日常において、ソクラテスとは別の方法を採用することが多い。
「相手に共感しなければならない」という思いから、重要かつ有意義な質問をすることを犠牲にしてまで、相手の痛みを全力で感じようとする。
しかし実際には、共感して肩を叩くよりも、考え抜かれた質問をするほうが、はるかに相手のためになるケースは少なくないのである。
共感のマイナス面や、共感的中立性の価値が見えてきただろうか?
(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)