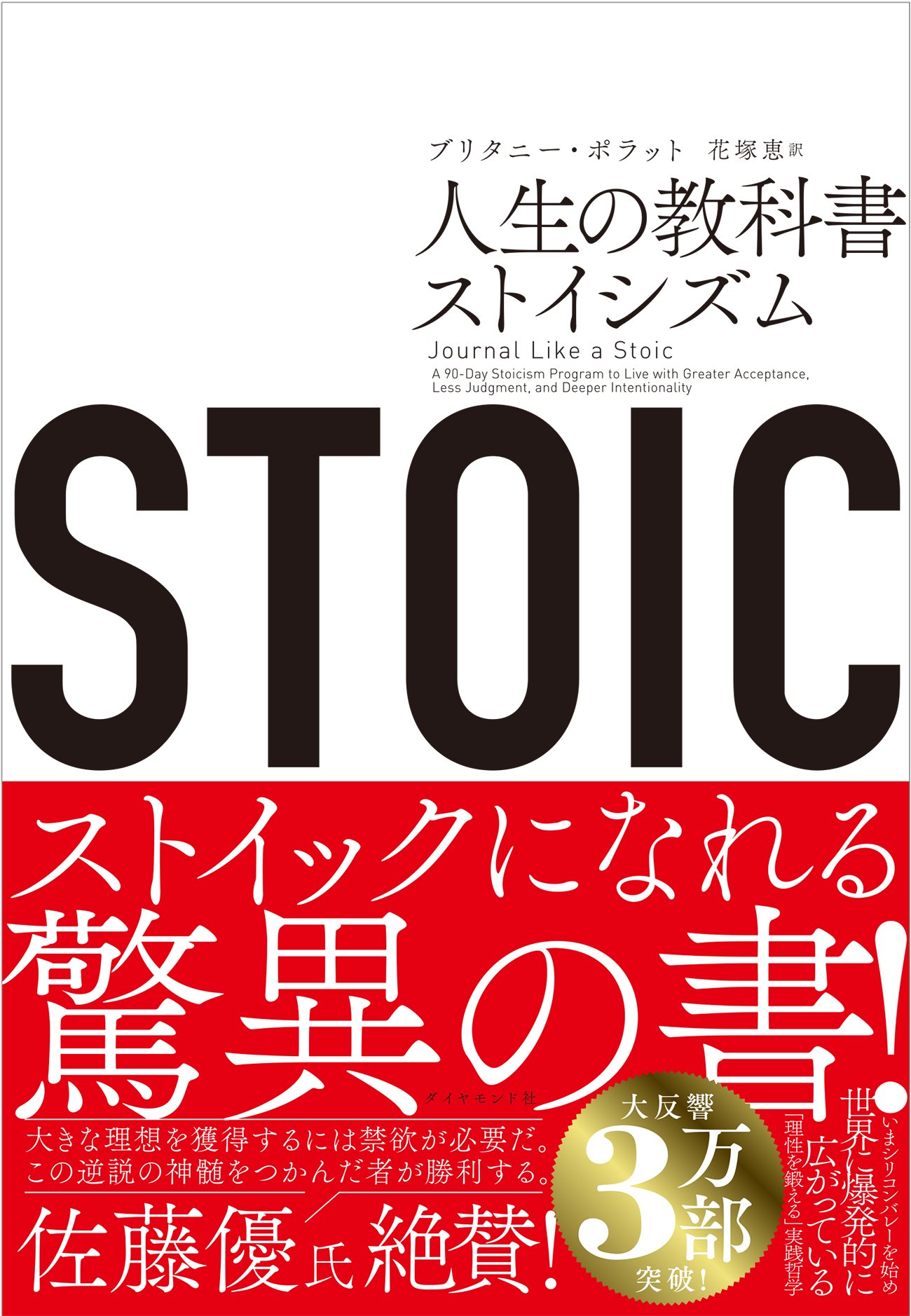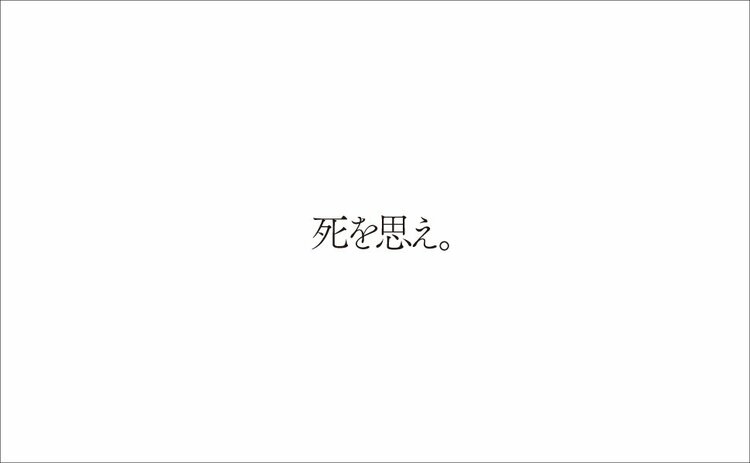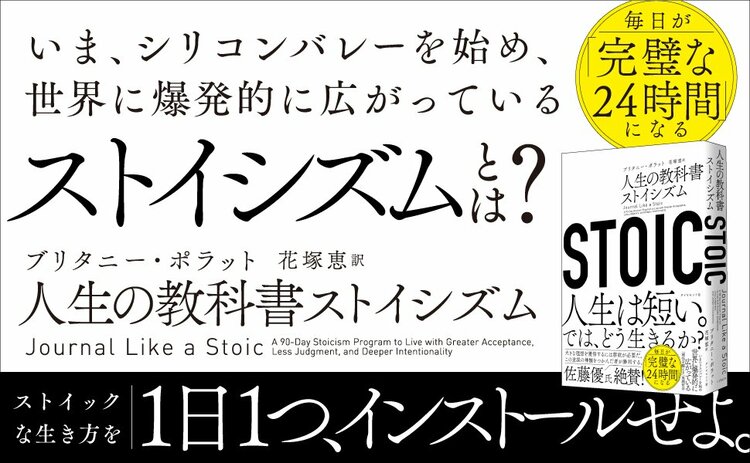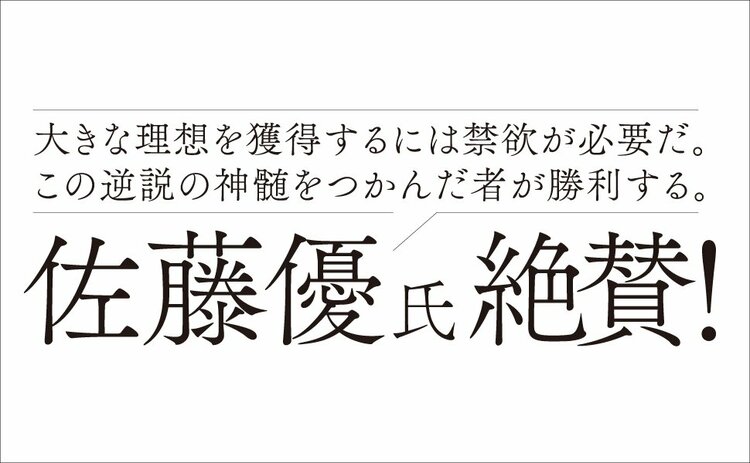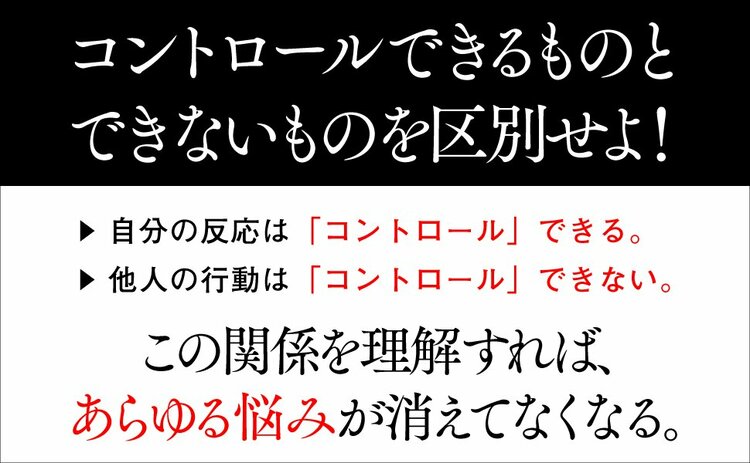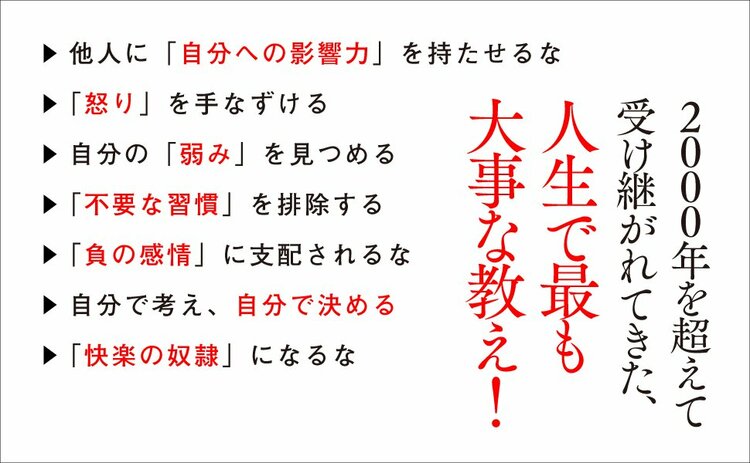いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
自分にはどんな義務があるだろう
ほとんどの人と同様に、私はルールを守ろうと思っている。
列に横入りはしないし、締め切りは守るし、適切に会計処理をする。ちゃんと納税もする。税金の使い道にはいろいろ文句があったとしても、納税は国民の義務だ。「いまはどうしても資金繰りが厳しくて」いうわけにはいかない。
そういった「それは守るのが当たり前でしょ」というルールのほかにも、義務はある。落とし物を交番に届ける、PTAの仕事を引き受ける、地域のお祭りのボランティアスタッフをする、など。
ただ、このあたりになってくると、人によって考え方が違うかもしれない。「義務」の範囲をどう考えるかだ。
自分にはその義務があると考えることもできるし、自分がやらなくても他の誰かがやってくれるからいいと考えることもできるかもしれない。
あらためて、義務とは何だろう。言葉の意味的には、「それぞれの立場に応じて当然しなければならない務め」だ。正直に言って、あまり嬉しい言葉だと感じたことはない。
ストア哲学者のマルクス・アウレリウスは、「義務を果たすときは四の五の言わずにやれ」ということを言っている。
やるべきことをやる
眠くても、よく寝てすっきりしていても、罵られても、褒められても、死を目前にしていても、別のことをしていても同じだ。
死ぬことも人生の行為の一つにすぎない。よって、いまやっていることをよくやれば、それで十分である。(マルクス・アウレリウス『自省録』)
――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より
ストア哲学で言う「義務」とは、美徳に即した行動をすることだ。「知恵」「正義」「勇気」「節制」という4つの美徳を高めて、理性的に生きることを説いている。
マルクス・アウレリウスはローマ皇帝として地上最大の権力を手にしながら、哲学者として生きようとした人だ。『STOIC 人生の教科書ストイシズム』ではマルクス・アウレリウスについてこう説明している。
マルクス・アウレリウスは「美徳に即して行動し、誠実に理性的に生きる」ことを人間の義務ととらえ、どんな状況であってもその義務を果たそうとした。
「寒いとか暑いとかを気にするな」
「やらなければならないこと」「(立場に応じて)当然しなければならない務め」と考えるとあまり嬉しくないが、美徳に即して行動するのが義務なのだと言われると、どこか清々しく感じる。
どんな状況でも人を思いやり、公正に、勇気を持って、かつ、慎みを持って行動するのだ。かっこいいではないか。それは当然ルールを守ることになるし、役割を果たすことにもなるだろう。
朝起きて、「やるべきこと」を前にして「だる…」と思うことはよくある。すぐに動けばいいのに、やる気が出ないからいったんSNSをチェックしてからとか、もうちょっと寝てから、などと自分に言い訳をしてだらだらしてしまうこともある。
そんなとき、「義務を果たそうというときに、寒いとか暑いとかを気にするな」というストイックな言葉を思い浮かべると、シャキッと気合いが入るのである。
(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)