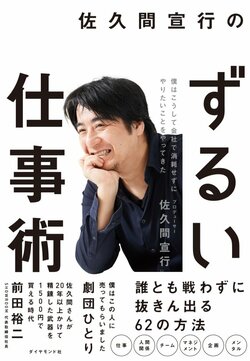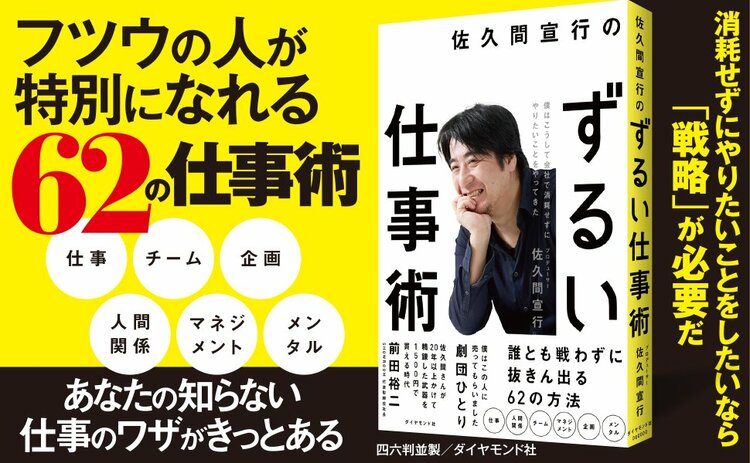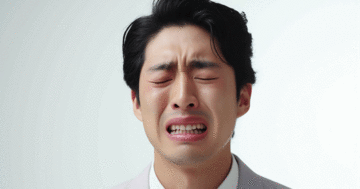「「メンタル第一、仕事は第二でいい、というメンタルに関する章が刺さった」「問題児をどうするかなどチームマネジメントが参考になった」……。こんな声が続々と寄せられ、ロングセラーとなっているのが、『佐久間宣行のずるい仕事術』だ。テレビプロデューサーであり演出家、作家、ラジオパーソナリティなど、多方面で活躍する佐久間宣行氏が、独立して初めてまとめた1冊。やりたいことをやってきた、という佐久間氏が語る「誰とも戦わずに抜きん出る方法」とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
いい仕事は、楽しそうにしている人に行く
入社したばかりの人、リーダーを命じられて責任が重くなった人、仕事が楽しめない人……。ロングセラーになっているのは、幅広い読者に支持されているからだろう。
「はじめに」では、「入社当時の絶望から20年以上かけて僕が身につけた作戦の数々が入っています」と記されている。
テレビ東京勤務時代、番組プロデューサーとして「ゴットタン」「あちこちオードリー」などヒット番組を多数制作。フリーランスになって以降も、多方面で活躍している佐久間氏だが、意外にも「自分は芸能界もテレビ界も苦手っぽい」とすぐに気づいたという。
そんな彼が「やりたいこと」を実現していくための方法として編み出したのが、もっとずるくなること、だった。
展開されていくのは、誰でもできるのに案外やっている人は少ない「いい仕事」をするための62のヒント。仕事術編、人間関係編、チーム編、マネジメント編、企画術編、メンタル編の6章に、「佐久間宣行の鞄の中身」などファン垂涎の6つのコラムから構成されている。
まず興味深いのは、こうした仕事術の本ではなかなか見られない、ユニークなヒントが少なくないことだ。
例えば、仕事術編の冒頭にあるのが“「楽しそう」を最強のアピールにする”という項目だ。
とにかく楽しそうに働く。その姿を、まわりや上司にアピールする。
「やりたい仕事をやると、こんなにご機嫌に働くのか!」
そう思ってもらえると、楽しい仕事を振られたり、任せてもらえるようになる。(P.16)
たしかにそうかもしれない。楽しそうにしている部下と、つまらなそうに仕事をしている部下と、上司は面白い仕事をどちらに投げようと考えるか。
佐久間氏は「組織にいるうえで、不機嫌でいるメリットなど一つもないのだ」と記す。
若いときはもちろん、中堅になってからも、フリーランスになってからも、楽しそうに働く姿を見せることを大事にしていたのだそうだ。実はこれ、この文章を書いている私の仕事のモットーの一つでもあるので、大いに共感する。
「歯車」仕事も、見ている人は見ている
一方で、まだ入社年次が浅かったり、経験が少なかったりすると、なかなか自分のやりたい仕事をさせてもらえず、雑務ばかりという日々を送ることも少なくないものだ。
中には、「こんな仕事をやりたくて会社に入ったのではない」とあっさり会社を辞めてしまうというケースもあるようだ。
こうしたケースで誰かに相談すると「下積みはしょうがない」「我慢の時期は必要だ」「石の上にも3年ということわざがある」などというアドバイスが語られがちだが、佐久間氏は違う視点を与えてくれる。同じく仕事術編からのヒント“「雑務」こそチャンスに変える”だ。
やりがいがない、忙しさの割にスキルも自信もつかない。
ただその場を回すだけの歯車仕事。
そんな仕事をするときは、ある意味、いちばんしんどいと思う。
でも、だれにでもできる仕事の中に、自分にしかできない仕事に変えられるものがあることがある。どんな仕事にも、おもしろくする余地や改善の余地があるのだ。(P.18)
退屈な仕事でも、「自分にしかできない仕事」になるというのだ。ここでは、まさに佐久間氏の経験談が載っている。入社1年目、ドラマのADの仕事を委ねられた佐久間氏に「雑用」が降ってきた。
監督から急に、明日の撮影で小道具として使う「サッカー部の女子マネージャーの手づくり弁当」を用意してこいと言われたのだ。しかも、画面から見切れるくらいで、ストーリーには特に関係がない。
面倒だったし、命令口調にイラッとした。でも学生時代にアルバイトをしていた居酒屋に頼み込んで厨房を借り、夜中に弁当をつくってみた。
女子高生の手づくり弁当なんて、想像もつかない。何度かつくってみたが、ウソっぽくなる。途方に暮れた。
そこで早速、海苔を六角形に切り抜き、まるいおにぎりに貼りつけてみた。(P.20)
ウインナーや玉子焼きも添え、出来上がったのは、朝の5時。ロケは2時間後。現場で弁当を見せると、思わぬことが起きた。
「ちょっと台本変えよう。この弁当をストーリーのメインにしたい」と監督。このとき、自分の中でなにかが変わったという。
「歯車」だと思っていた仕事が、「佐久間の仕事」になったのだ。小さな仕事でも、だれかが必ず見てくれている。評価してくれていると知った。
嫌な人との仕事は、コントにしてしまえ
仕事は、いろいろな人とすることになる。中には、どうにもウマの合わない人もいる。嫌な人との仕事は、ストレスが高まる。これは、誰でも味わうことだ。
佐久間氏もそうだったが、おすすめの方法があるという。これがなんともユニークなのだ。人間関係編に出てくる、“「コント:嫌いな人」でバトルを避ける”だ。
その人と対面した瞬間、心の中でこう唱える。「コント:嫌いな人」。
そう、芸人がコントをはじめる前に言うタイトルコールだ。
「コント:性格の悪い人」
「コント:自己中クライアント」
「コント:メンツおじさん」(P.71)
こうやってコントのコールを入れるだけで、自分と相手を客観的に眺められるようになるという。「相変わらず理不尽! 後でどうやってネタにしよう」と面白がることもできると記す。
嫌いな人について、なんとか好きになるなんてことは必要ない。目の前の嫌な人とのやり取りを、「せっかくだから面白がってしまえ」というのだ。結局、ああ、嫌いな人と話さないといけないと思うから、嫌になるのである。
同じようにユニークなのが、同じく人間関係編の“「合わない上司」は分析してみる”だ。
まずは、上司に言われたことを書き出して、最近どんなことを指摘されたか「分析」するのだ。
これをあらかた書き出したら、納得できるか◯と×をつけていこう。(P.73)
言っていることには一理あると思ったら「◯」。聞き入れられないと思ったら「×」。
こうすることで、上司の「なにが不快か」が見えてくるという。何が自分のメンタルを削っているのかが分析できるのだ。
理不尽な上司に我慢しなければいけないわけではない。しかし、ただ反発しても、単なるわがままと受け止められかねない。だから、書き出して分析するのだ。これで上司の上司に交渉することもできる。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『メモ活』(三笠書房)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。