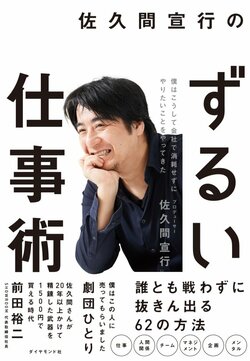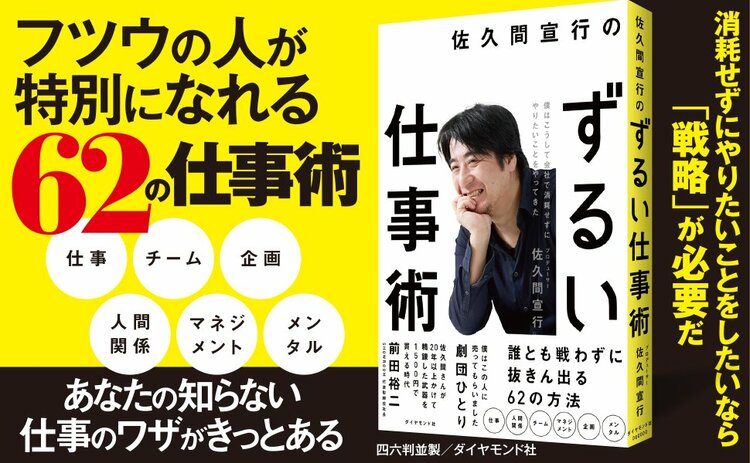「メンタル第一、仕事は第二でいい、というメンタルに関する章が刺さった」「問題児をどうするかなどチームマネジメントが参考になった」……。こんな声が続々と寄せられ、ロングセラーとなっているのが、『佐久間宣行のずるい仕事術』だ。テレビプロデューサーであり演出家、作家、ラジオパーソナリティなど、多方面で活躍する佐久間宣行氏が、独立して初めてまとめた1冊。やりたいことをやってきた、という佐久間氏が語る「誰とも戦わずに抜きん出る方法」とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
企画書は「出すもの」ではなく「通すもの」
入社したばかりの人、リーダーを命じられて責任が重くなった人、仕事が楽しめない人……。ロングセラーになっているのは、幅広い読者に支持されているからだろう。
「はじめに」では、「入社当時の絶望から20年以上かけて僕が身につけた作戦の数々が入っています」と記されている。
テレビ東京勤務時代、番組プロデューサーとして「ゴットタン」「あちこちオードリー」などヒット番組を多数制作。フリーランスになって以降も、多方面で活躍している佐久間氏だが、意外にも「自分は芸能界もテレビ界も苦手っぽい」とすぐに気づいたという。
そんな彼が「やりたいこと」を実現していくための方法として編み出したのが、もっとずるくなること、だった。
展開されていくのは、誰でもできるのに案外やっている人は少ない「いい仕事」をするための62のヒント。仕事術編、人間関係編、チーム編、マネジメント編、企画術編、メンタル編の6章に、「佐久間宣行の鞄の中身」などファン垂涎の6つのコラムから構成されている。
ヒット番組を次々と生み出してきたプロデューサーだけに、やはり読者が知りたいのは、「いかにして尖ったアイデアが生まれてきたのか」かもしれない。
企画術編は“企画書は「ラブレター」”という項目から始まるが、いきなりハッとさせられる内容だ。
たった数枚の紙切れに、たくさんの関係者がアイデアを乗せ、かたちにしていく。
上司から「企画書を出せ」とせっつかれたら、それを「出す」ことで精一杯という人も多いと思う。
でも、企画書は「出すもの」ではなく「通すもの」。(P.148)
そうなのだ。企画書は単につくり上げられるだけでは意味がないのだ。企画は、通さなければいけないのである。このことに気づくことができれば、企画書づくりに向かう意識が変わる。
「その企画書は誰が読むのか」に頭が向かうのだ。これが、企画書を、もっと言えば企画を変えていく。
企画が通らないのはセンスだけの問題ではない
この文章を書いている私には文章や企画書に関する著書があるが、文章にせよ、企画書にせよ、書く際に多くの人に抜け落ちがちなものがあると感じることが少なくない。それが「誰に向けて書くのか」だ。
企画書でもメールでも、実は「誰に向けて書くのか」で内容は変わるはずである。所属部署が主催するイベントの企画書を「課長に提出する」「役員に提出する」「クライアントに提出する」となれば、それぞれ書くべき内容、補足すべき内容は異なるはずだ。
しかし、実際にそこまで意識できている人は少ない。逆に意識することができれば、企画を通すためのハードルは一気に下がる。
一方でクオリティは上がる。読む相手が「何を求めているのか」が想像できるようになるからだ。「ただアイデアがあればいい」ではないのである。
だから僕たちの場合はまず、編成局に向けて企画書を書く必要がある。
ここで考えたいのが、相手は「なにを求めているか」だ。(P.149)
編成にとって最重要事項は(時間帯にもよるが)「視聴率」だという。
ならば、「なぜこの番組は、視聴率が取れるのか」を企画書の中で説明しなければならない。このときに必要になるのは、「なぜいま」の説得力だという。
社会の空気やマーケットの傾向、SNSの声などを使いながら、「なぜいまこの番組が高視聴率を取れるのか」を数字やデータ、ロジックで裏打ちしながら説明していく必要があるのだ。
「企画がどんなに面白いのか」という話ではない。求められているのは、「なぜいま」の説得力なのだ。なぜなら、企画書を受け止める側が、一番知りたいことだからだ。
つまり、自分の「言いたいこと」よりも、企画書の読者(上司や会社)の「知りたいこと」を優先して入れ込むことが、採用率を大きく上げるポイントなのだ。(P.149-150)
「とにかくこの企画をやりたい」がいきなり書かれている企画書と、上司や会社の「知りたいこと」が1枚目に書いてある企画書とでは、与える印象と採用率の違いが想像できるはずである。
ちなみに佐久間氏は、企画書が一切通らない鳴かず飛ばずの時期に、社内のあらゆる企画書を読み漁ったのだという。
そこで「企画が通らないのはセンスだけの問題ではない」と気づくのである。その最大のヒントは、「読み手」にあったのだ。
自分が会社に提供できるメリットを提示せよ
企画術編には12の項目があり、「佐久間流発想術」として「反転法」や「掛け合わせ法」などのテクニックも紹介されている。
実際にこの発想法で生まれた番組が紹介されたり、発想術が図式化されていたりして、極めて興味深い内容になっている。
また、意外にもその方法はシンプルで、テレビ番組以外の企画のアイデア出しにも活かせそうだ。
ただ、それ以上に興味深いのは、これぞ企画の本質、という項目がしっかり置かれていることだ。
ある意味、「これぞ佐久間氏がヒットメーカーであり続けている理由かもしれない」と感じた。たとえば、“「稼がなくていい企画」なんてない”。
でも会社は、「おもしろいこと」がしたいわけじゃない。
だから立てた企画を続けるためには、会社の好きな匂いを漂わせ続ける必要がある。それが「儲かる匂い」と「成長の匂い」だ。(P.174)
会社は、ただ面白いことをさせてくれる場所ではないのだ。それは、利益を生むから実現できるのである。
そのことを忘れて「とにかく面白いことがしたい」で企画に走るとうまくはいかない。
逆に「儲かる匂い」と「成長の匂い」のどちらかがあれば、会社は続けるチャンスを与えてくれると佐久間氏は記す。なぜなら、このどちらかが、営利団体である会社にとって「続ける理由」になるからだ。
楽しく仕事をするためにも、やりたいことをやり続けるためにも、自分が会社に提供できるメリットを提示しよう。(P.176)
そうでなければ、テレビ局であれば「打ち切り」になる。だからピンチを迎えると、「儲かる匂い」か「成長の匂い」を出すことに佐久間氏は頭をひねった。
本書では「あちこちオードリー」がコロナ禍に、いち早くオンラインの配信イベントを企画したエピソードが載っている。
番組単体のオンラインイベントは、まだ社内で誰も成功していなかった。そこできちんと売り上げを立てることにチャレンジし、成功した。
紹介されているヒントの数々は、どれもユニークで実践的。読み終えたとき、自分の企画書にも何か一つ、変化を加えてみたくなるかもしれない。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『メモ活』(三笠書房)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。