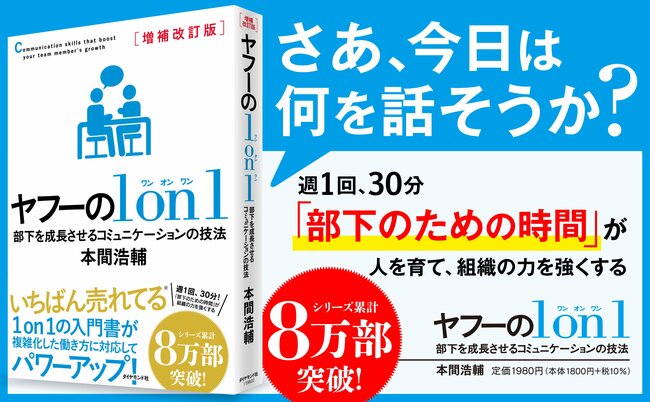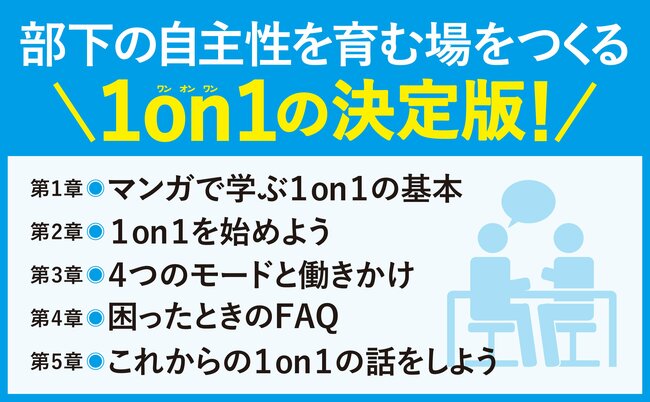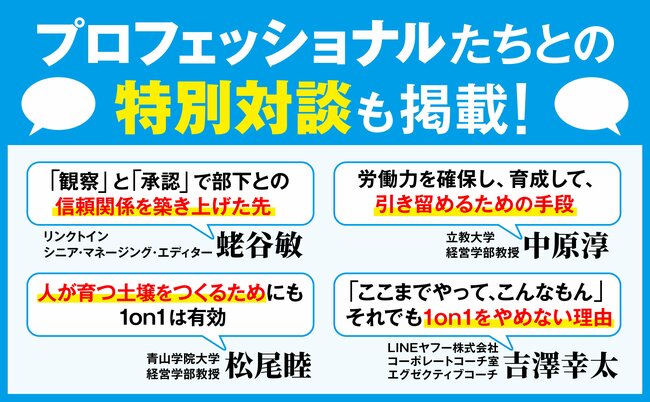上司と部下が一対一で定期的に面談をする「1on1」。ヤフー(現・LINEヤフー)が2012年に取り入れて実践してきたこのマネジメント手法は、単なる業務報告や評価面談とは異なり、部下の成長を支援し、信頼関係を築くためのものだ。しかし、「部下とイマイチうまく話せない」「部下から話を引き出せない」と悩んでいる上長も多いのではないだろうか。そこで今回は、当時、ヤフーで上級執行役員を務めており、1on1の仕掛け人でもあった本間浩輔氏(現在はパーソル総合研究所取締役会長や朝日新聞社の社外取締役などを務める)の著書『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』から、より対話を実りあるものにする技術を紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
1on1での対話をより実りあるものにする方法
昨今、1on1を取り入れる企業は増えたが、うまく1on1の場を使えているだろうか。
1on1のよくある失敗としては、上長が自分の言いたいことばかり言って終わってしまうことが挙げられる。
部下の話をきちんと聞かなければ、部下にとっては「話を聞いてもらえないから意味がない」となってしまう。
しかし、人の話を引き出すのはなかなか難しいものだ。
日本では「相手の話をただ聞くのではなく、心を込めて注意深く、理解しようとする姿勢で聴く」ことを「傾聴」と言うが、ただ真剣に耳を傾けるだけでは話を引き出すにまでは至らないことも多い。
一体どうすればいいのだろうか。
本間氏は、本書で「対話をより実りあるものにするための基本技術」として、2つの手法を挙げてくれている。
それは「アクティブリスニング」と「承認」だ。
これは、どちらも「部下の発言にどう対応するか」という手法だ。それぞれについて、詳しく解説しよう。
話し手に思考を促す「アクティブリスニング」
アクティブリスニングは一般的に「傾聴」と訳されることが多いが、「真剣に黙って聞く」イメージが強い「傾聴」よりも、文字通り「アクティブに聞く」イメージだ。
本間氏の言うところの「アクティブに聞く」とは、ただ黙って相手の話を聞くのではなく、うなずいたり、相槌を打ったり、キーワードを繰り返すなど、反応を示しながら聴くことを指す。
例えば、次のような形だ。
上長:Aさんは、考える時間をとりたいと思っているんですね。
部下:はい。でも時間がとれないんです。
上長:なるほど、忙しすぎて、考える時間がとれない。
部下:はい。でも、考える時間がないのは忙しいからだけではないかもしれません。(P.123-124)
このケースでは、上長は部下の言葉をオウム返しにするだけで、意見を述べてはいない。
しかし、部下は話をしながら、自分で考えを整理しているのだ。
上司が発言を繰り返すことで、自分の言ったことを客観的に聞き返す状態になっているのがいいのだろう。
これは、聞き手(上長)はオウム返しをしているだけだと実感するのに対し、意外にも話し手(部下)は、聞き手がオウム返しをしているとは感じないのだそうだ。
むしろ、「じっくり話を聞いてくれた」「考えが整理できた」という感想を持つことがほとんどだという。
非常に取り組みやすい方法なので、ぜひ試してみてほしい。
話し手の感情を一旦受け止める「承認」
もう一つは「承認」だ。
「承認」とは、「相手が存在することを認める」という意味である。
1on1での承認とは、「目の前にいる部下の存在を認め、部下のありのままを受け止める。そしてそれを相手がわかるように伝えること」だと本間氏は語る。
それは次のようなことだ。
たとえば、部下が自分の業務量が多いと不満を持っているが、上長はもっと仕事をやってもらいたいと思っていたとする。
このとき、上長は自分の感情を横に置いて、部下の「業務量が多い」という感情を認める必要があるという。
なぜならば、上長がどう思っていようと、部下が「業務量が多い」と感じているのは事実だからだ。
対話の例を見てみよう。
上長:忙しそうだね。いつもありがとう。
部下:何で僕だけこんなに忙しいんですかね?
上長:そうだね。僕がAさんに頼りすぎなのかもしれないね。
部下:(沈黙)いやいや愚痴でした。すみません。(P.125-126)
仮にここで、上長が「Aさんの給料を考えると、もっと仕事してほしいんだけど」「俺が若い頃はもっと仕事をしたものだ」などと、自分の感情を押し付けるようなことを言うと、きっと部下は心を閉ざしてしまうだろう。
「この上長は自分の気持ちを理解してくれないんだな」と考えるであろうことは、想像に難くない。
この対話のポイントは、「業務量が多い」という部下の感情に対して上長は共感し、部下の感情を無条件に受け入れてはいるが、同意はしていない点だ。
本間氏は次のように述べる。
たとえば、「業務量が多い」と訴える部下に、「業務量が多いのはあなただけではない」「あなたの仕事の進め方に問題がある」と指摘してもコミュニケーションは平行線をたどるだけです。
まずは、きちんと承認すること。そして、部下がそれを実感できるようなコミュニケーションが大切です。(P.126-127)
感情には共感しつつも、業務量の多い・少ないに関しては特にコメントはしない。
感情と実際の業務量については別物として扱い、感情面だけ受け止めているのだ。
話の聞き方を意識をすれば対話も変わる
アクティブリスニングも承認も、特別な対応ではないように思うが、意識しておかないとなかなかできないのではないだろうか。
「聞き方」を少し意識するだけで、これまで以上に実のある対話が生まれるはずだ。
1on1の予定がある人は、ぜひ次回試してみていただきたい。