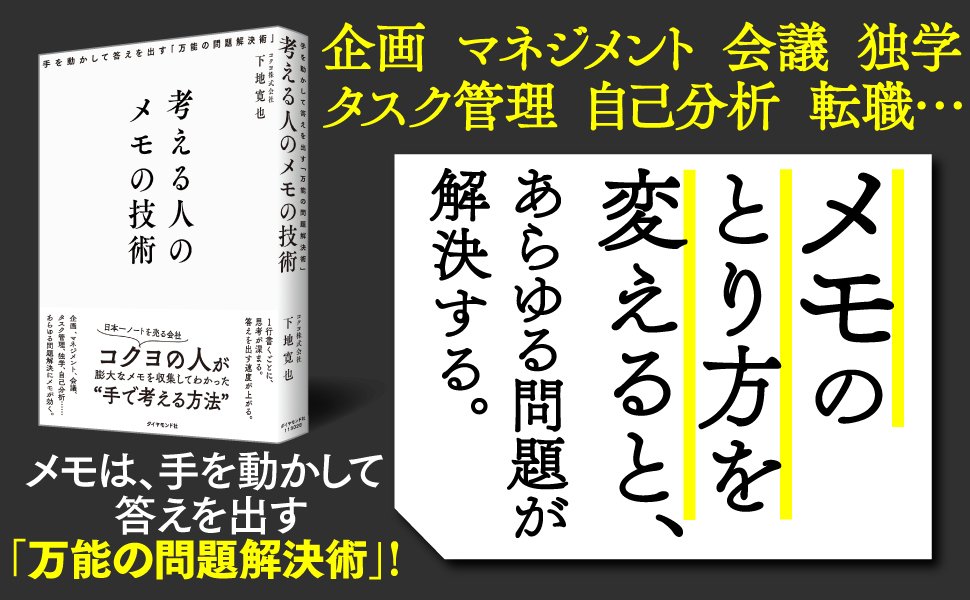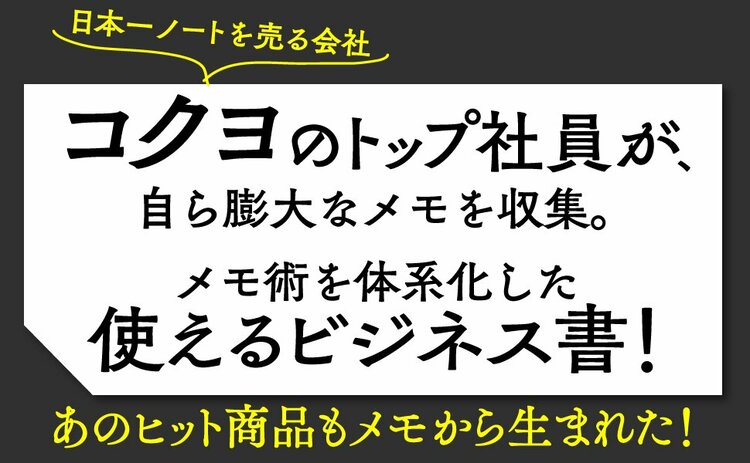答えのない時代に、メモが最強の武器になる――。
そう言い切るのは日本一ノートを売る会社コクヨで働く下地寛也氏だ。トップ社員である彼自身が、コクヨ社内はもちろん、社外でも最前線で働くクリエイターやビジネスマンにインタビューを重ねて上梓した『考える人のメモの技術』。読者からは、
「いかに自分のメモが仕事に役立っていないかが、わかってしまった」
「だれにも聞けないメモの取り方を、手取り足取り教えてくれる本」
「メモを変えたら、仕事の質が上がった!」
といった多くの声が届いている。
たかがメモ。されどメモ。
今回は特別に「言語化とメモ」をテーマに著者の下地氏に寄稿いただいた。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
言語化センスのある人は難しい言葉を使わない
人の話を聞いていて「本当にうまいこと言うなあ」と思うことがあります。そういったセンスはどこから来るのでしょうか。
私は、「なるほど!」と思う言い回しを聞いたときにメモをするようにしています。
最近メモした中で言語化のセンスが光っているなあと思ったものをいくつかご紹介しましょう。
(白井一幸氏)
(曽山哲人氏)
(為末大氏)
いずれも私が勤める会社、コクヨで開催した講演でのメモです。多少の言い回しの違いはあるかもしれませんが、本当に「言語化うまいなあ~」と唸ってしまう内容だと思いませんか?
特別に難しい言葉を使っているわけではありません。むしろ子どもでも分かる平易な言葉づかいです。それでもなぜか頭に残る。
逆に「言語化センスがイマイチだな」と感じてしまう人にも、いくつか共通する特徴があります。
① 当たり前のことをもっともらしく言う
例えば「やっぱり大切なのはチームワークだよね」という発言。時と場合によってはよい言葉ですが、一般的には、まぁそれはそうだよねとなりがちです。
相手が想定していることより一歩深い表現をしないとセンスがないなあと思われてしまいます。
② 難しい言葉でもっともらしく語る
「エンパワーメントすることによりアジリティが高まる」といったようなカタカナ語や専門用語を使う人。
難しい表現を知っていることを披露したいのかなと勘ぐってしまいます。
③ もっともらしく言うけどポジションを取らない
「どちらが良いかというのは世代で違うと思うので、ケースバイケースですよね」みたいに、何を言いたいのかわからないパターン。
多面的な視点を私は理解していますと言いたいのでしょうが、自分の主張がありません。
こうした言語化のセンスの悪さは、自分はどう考えているのかを日々言葉にする訓練をしていないから起こります。
では、言語化センスのある人はどのようなことを意識しているのでしょうか。
まず前提として、ここでいう“言語化センス”は、芸人さんやコピーライターのような言葉遊びのうまさではありません。
日常の中で、「そこが本質だなあ」と思わせる表現や、「そう、それが言いたかったんだよ」と共感を呼ぶ言い回しのことでしょう。
この“センス”、持って生まれた才能のようにも見えますが、実はそうではありません。
これはトレーニングによって身につくスキルなのです。
言語化センスを磨く「気づき」のメモ
まず試してほしいのが、面白いと思った情報や出来事をメモするときに「気づき」を加えることです。
気づきと言うと何か特別なヒラメキのような気がしますが、単に頭に浮かんだこと、たとえば「部下育成の参考になる!」「クールさと優しさのギャップに泣かされるな」といった簡単なコメントでOKです。
メモした情報は自分の外にあるもので、気づきは自分の中から出たものです。
実はこの外から得られた情報に対する自分なりの解釈こそが、情報を自分ごとにする変換装置の役割を果たします。
食べ物を口から入れても、胃や腸で消化吸収されなければ意味がないのと同じように、情報もノートにメモしただけでは、自分の知識に取り込まれないと意味がないのです。
いろいろメモしているけど、結局、言語化力が磨かれないという場合、それはメモした情報に自分なりの示唆が盛り込まれていないからなのです。
気づきはインプット情報の隣、もしくは下に「▶」「★」「→」などのマークをつけて書いておきましょう。
どこまでが外から得た情報で、どこからが自分の中から生まれた気づきなのかを明確にするためです。
もちろん全ての情報に気づきを書く必要はありません。何かまとまった情報を得たところで、1つ2つ気づいたことを書き加えるので十分です。書き方にこだわる必要もありません。
たとえば、私がメモした内容を少し紹介します。
→批判もユーモアがあると受け取りやすい
→美しさのための無駄にも意味がある
→飴とムチを自分で準備、すごい!
どうでしょうか。単に情報をメモするより、ちょっとした気づきを加えるだけで脳みそが働いている気がするでしょう。この気づきを書く癖をつけておくと、言葉にする力が上がります。
常識を疑うメモで思考が柔軟になる
もう一つの方法は、常識を疑うメモを書いてみるということです。
言語化のセンスがある人の表現をみていると、常識にとらわれない意外性のある言い方をしていることがわかります。常識を超えた意見が言えると、センスの良い表現の幅が広がるのです。
そうは言っても、常識を疑うのは難しい。常識を疑うためには、そもそも常識とは何かを知る必要があります。そのためにも、まずは考えるべき対象物の特徴や使い方を拾い上げ、次に、だから◯◯が当たり前だよねという順番で考えてみましょう。
この2ステップを踏むことで常識に気づきやすくなるわけです。全ての常識に対してアイデアが出るわけではありません。でも常識を打ち破るための思考の起点となることは間違いないでしょう。
ノートを例にしてこの2ステップを考えたとき、皆さんはどんなことを思いつきますか。ちょっと拾い出してみました。カッコの中はそれをもとにしたアイデアを加えています。
・リングノートのリングは鉄 → リングに手が当たる (リングが樹脂で柔らかくできないか?)
・ノートは左から右に書く → ノートの右端は余ることが多い (幅の狭いスリムノートはどうだろう?)
・子どもはプリントをノートに貼る → プリントが少しはみ出る (プリントが貼れる少し大きいノートは?)
・文字を書くので横罫が主流 → 図がキレイに書きにくい (ドットを横罫に付けると図を書きやすいかも?)
実はこれ、すべてコクヨが商品化したノートの発想です。
特徴と当たり前を整理するだけで、常識を疑うアイデアの起点ができます。
言語化センスも同じです。「よくある言い方」や「当たり前の説明」の一歩先を考えることで、聞き手になるほどと思わせる表現になるわけですから、こういった思考の順番を工夫することがとても効果的なのです。
面倒に感じるかもしれませんが、意外と楽しい作業です。ぜひ言語化センスを磨いてみてください。
(本原稿は、『考える人のメモの技術』の著者・下地寛也氏による書き下ろしです)