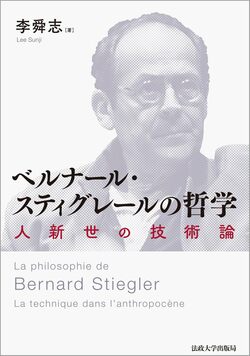オードリー・タン氏らが提唱する多元技術PLURALITY(プルラリティ)とデジタル民主主義を日本で実践し、社会全体を豊かにするには何が必要か。入門書『テクノ専制とコモンへの道』の著者に聞いた。3回連載の後編。(取材・文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮、撮影/嶺 竜一)
スティグレールの哲学、
アーレントの哲学
――李さんの前著『ベルナール・スティグレールの哲学』は、『PLURALITY(プルラリティ)』と共通する部分があるのでしょうか。
スティグレールは哲学者なので、「技術とは何か」のような抽象的・根源的なことを探究していて、『PLURALITY』と直結はしないのですが、共通する部分はあります。例えば、技術と人間の関係について、などです。
技術は、例えば時計が典型ですが、人々の動きを規制し集団を作り出します。他方、技術は同時に、集団に回収されない一人ひとりの固有性を実現することを支えます。この両方のバランスを、どう取っていくかが重要になっていきます。
このようにスティグレールが時間と技術の関係についても深く考察しているのに対して、『PLURALITY』は時間の観念についての考察はなく、より実践的なことを追究しています。
見方を変えれば、『PLURALITY』はデューイやジンメルなどの思想家の影響を受けているのですから、今後は、そうした思想的な面も深めていく必要があるのではないかと私個人としては考えます。
――『ベルナール・スティグレールの哲学』では、資本主義が人々を取り込んでいく様を歴史的に分析していきます。まず、テイラーの科学的管理法により労働のノウハウが機械に外注化されて労働者は「制作知」を失います。大量生産した商品は、広告による欲望喚起で、大量消費につながります。その際、人々は暮らしに関する「生活知」を奪われ、労働から解放されて得た余暇は映画やテレビに取り込まれていきます。そうして自律性を失った労働や画一的な消費生活を批判し、そこから脱しようとした1968年のパリ5月革命の「芸術家的批判」でしたが、その成果も資本主義は次第に取り込んでいったと指摘しています。
5月革命の時の若者は、毎日ベルトコンベアに乗せられた製品のごとく、自分たちも朝から晩まで同じ仕事をさせられるフォーディズム的な生活に不満を持ち、創造的な仕事がしたいと「芸術家的批判」を展開するわけです。しかし、その結果得た創造的な仕事とは、マーケットに合った商品をクリエイトするという類のものでした。
また、労働時間の柔軟性の要求は、仕事は自宅に帰ってからもできる、という形にすり替えられてしまう。かつて工場労働者は、職場を離れたら仕事ができないので、友人と交流したり絵を描いたりするなど自由な文化的活動ができたのに、芸術家的批判が認められて以降、家でも仕事をせざるを得なくなってしまうのです。
このことは、昨年ベストセラーになった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)で三宅香帆さんが指摘されたことに通じます。
労働時間と余暇時間の境界が曖昧になってしまい、すべてが資本主義に飲み込まれた社会を、どうにしかないといけないとスティグレールは問題提起するのです。
しかし、そうした問題提起の段階で、彼は亡くなってしまいました。パリでは思想を実践に移す試みをしていたのですが。彼の提言をどう実現していくかは、私たちに残された課題です。
――『ベルナール・スティグレールの哲学』の思考は、人間の活動を「労働」と「仕事」と「行為」の三つに区分するハンナ・アーレントの思想と繋がっています。そして、彼女は『PLURALITY』でも多く言及される思想家です。
アーレントは、プルラリティにとって重要な思想家です。アーレント自身、著書『人間の条件』(講談社学術文庫など)で、プルラリティ(複数性)こそが人間の条件だと論じています。人間の本質ではなく、人間の条件だと。人間は生物的に人間として生まれても、そのままでは人間ではなく、人間の条件が揃わないと人間にはならない、とアーレントは説きます。
これは古代ギリシャ時代から連綿と西洋が受け継いできた人間観です。いろいろな条件が揃わないと、人間は人間になれない。その条件の1つがプルライティです。
人間はそれぞれが自らの固有性、他人とは違うものを社会に公開、晒して、お互いがプルラリティを保ったまま、いろいろ意見を交換していくことが、アーレントにとっての人間の条件です。ここは、プルラリティの思想と響き合うところです。
――個々に異なる人たちが、言葉を介してコラボレーションすることで、社会が豊かになっていくと考えたアーレントの時代に対して、今日ではテクノロジーを介して、よりコラボレーションができるということですか。
そうですね。 ただ、アーレントが『人間の条件』で取り上げた世界は、古代ギリシャのポリスです。奴隷制度があり、市民は衣食住のための労働をする必要がなかったという特殊な環境です。市民は集まって、好きなだけ話し合いをできる余裕があるわけです。だから、現代社会にはそのまま適用できません。
とはいえ、『PLURALITY』で紹介されているような最新のテクノロジーを活用すれば、古代ギリシャとは別の形で人間の条件を万人に実現できるかもしれません。
――テクノロジーを使って、機械に、生活必需品の生産は任せて、それによりベーシックインカム制度を実現して、古代ギリシャにおける市民の世界を実現しよう、と。
ベーシックインカムの議論は、統合テクノクラシーの人たちもしていて、私の本『テクノ専制とコモンへの道』では、警戒的な取り扱いになっています。ともすれば、テクノロジーの進歩のおかげで労働者は用なしになったが、余剰生産はできるので、仕方がないからベーシックインカムを供与して、延命させてあげる、という方向に移りかねないのです。
『テクノ専制とコモンへの道』や『PLURALITY』で、私たちが論じているのは、AIが進歩するために活用している「データ」は、私たちがI Tを日々使う中で提供しているものだから、それに見合う報酬が得られて然るべきで、それは統合テクノクラシーの人たちが想定するベーシックインカムよりもはるかに大きなものだ、ということです。
――プルラリティコミュニティも、ベーシックインカム的な制度は研究されているのですか。
オードリー・タンさんとグレン・ワイルさんが所属するRadicalxChangeでは、「ポスト認知所得(Post-Cognitive Income/PCI)」という視点から、ベーシックインカム的な制度の可能性を検討しています。
産業革命が肉体労働を激変させたように、AIは今、人間の知識や思考力を使った認知的労働を周縁へと追いやろうとしています。今後、わずかな「認知のスーパースター」たちだけが娯楽産業のような形で活躍し、その他の人々は認知スキルを持っていても、限定的で低い報酬しかもらえない労働に甘んじる可能性があります。
そんな中、認知労働を超えた新たな収入源として、RadicalxChangeは「ポスト認知所得(PCI)」を資本所有、人格崇拝、関係性労働の3つに分類しています。まだ勉強中ですが、テクノロジーの進歩は、ユニバーサル・ベーシックインカムのように多様な人々の生存を確保することに貢献できると考えています。