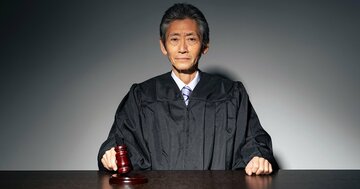今、公権的と述べた点ですが、実際日本でなされている裁判は国の機関である裁判所が行います。地方公共団体には裁判する権限はありません。地域や団体内の顔役が当事者双方から意見を聞いて判断を示してこれに従ってもらいたいというような場面がしばしばあることは、みなさん経験のあることだろうと思います。
小学校のクラスの中のことについての揉め事があったとしたら、クラス担当の教師が判断を示すことがありますよね。でも、これは裁判とはいいません。公権的なものではないからです。今述べたような具体的な紛争を解決するために裁判所が下す裁定のことを裁判というのです。なんとなくイメージが湧いて、新聞記事、特に三面記事あたりと相互理解が進むのではないかなと思います。
「具体的な紛争」とは?
裁判で扱うための条件
ここで1つ業界用語を紹介します。今述べた「具体的」という言葉は説明が必要でしょう。それは国語辞典に出ている意味とは異なり、特定の意味があります。つまりこの具体的というのは、紛争の当事者の権利や義務に関係するという趣旨です。事件の結論、つまりどちらが勝つか負けるかによって、当事者の権利が発生したり消えてなくなったり、義務が生じたりなくなったりという場合に限られます。したがって、より抽象的で、どちらが勝っても負けても当事者の権利や義務に影響がない場合には、具体的という条件は満たされません。
1つ例を挙げると、新しくできた法律が憲法違反である旨を宣言してほしいという訴訟が提起されたとしても、これは今述べた具体的という条件をクリアしませんので、裁判所としては取り上げて判断することはできません。学問上の争いもそうですね。
たとえば歴史学上の話を1つ例に挙げると、本能寺の変で明智光秀が織田信長を襲って殺したという事件がありましたが、その動機は何かというのは今現在、歴史学者の間でも様々な意見があって、統一された見解はありません。その動機は何かについて裁判所に訴えて決めてもらおうというようなことはできません。どちらが勝っても負けても当事者の権利や義務には関係がないからです。
同様にして、アインシュタインが唱え始めた相対性理論が正しいかどうかを判定してくれとか、数学の問題が解けたと思うけれども、それが正しいかどうかを判定してくれというような訴えも、ここでいう具体的なものとはいえません。