憲法問題で一定の見解を持っている人が裁くと、必ず結論が先に出ているような状態になってしまって、公平性が失われてしまいます。だから、裁判官が能動的というか、積極的に事件を選んで自分はこの事件の判決をするとかいうことができないようにして、最終的に裁判の公平を保つように図っているわけです。
定年間近の裁判官は
どんな判決を下す?
概して裁判官は、受動的で消極的ですが、定年間近になると、急に思い切った判決を書く人もいます。地裁と高裁の裁判官の定年は65歳です。簡易裁判所の裁判官は70歳です。定年間近に思い切った判決をしてももう人事上不利益は受けないですから、ありうるのです。新聞に出るような憲法違反とかいうような判断になるとだいたい合議体ですね。裁判官は3人います。裁判長が定年に近いかどうかという話になります。でも両陪席は若い人が多いですね。裁判長と10歳とかもっと年齢が若いとまだ定年に近くはありません。ですから、画期的な判決に関与して将来人事上不利益を受けるのではないかと危惧する場合もあります。
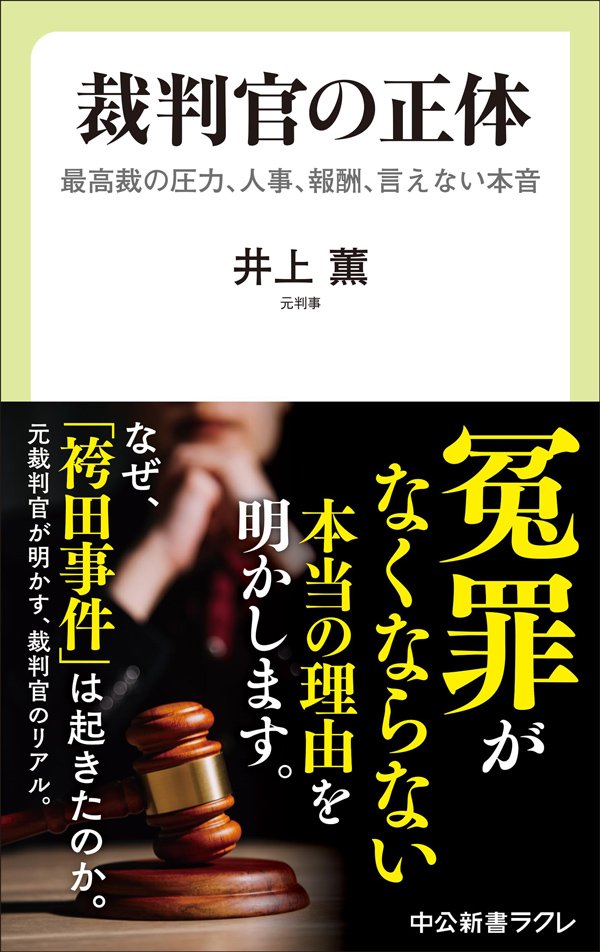 『裁判官の正体 最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(井上 薫、中央公論新社)
『裁判官の正体 最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(井上 薫、中央公論新社)
下級裁判所裁判官は、ほとんど最高裁の意向に沿って仕事をしています。そのため多くの裁判官は上ばかり見ているからといってヒラメ裁判官などと悪口を言われたりしますが。思い返せば、最高裁の教育は、司法修習生時代から始まっていました。司法修習生になると、司法研修所で判決や起訴状などの書き方を学びます。書き上げた書面を提出すると、教官から「これじゃ、最高裁は通らない」といった指導を延々と受けるのです。最初の洗礼です。
司法修習生はテストでよい点を取ることを最大の目標として歩んできた人が多いため、最高裁で通用しないなどと指導されれば、特段の疑問も持たず、最高裁に認められる書面を書けるよう、懸命に取り組んでしまうのです。それで、司法修習を終えた時点では、すでに最高裁に都合のよい人材になっているのです。







