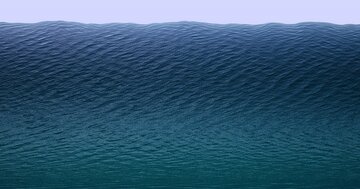「もうダメだ」と思った時に
突然蘇った祖父の言葉
――「津波てんでんこ」
小さい頃から繰り返し聞いてきた言葉が、いまさら思い出された。
それは三陸沿岸に古くから伝わる教訓である。「津波が来たら、てんでんばらばらに逃げろ」という意味で、家族や近所の人を気にせず、自分の命を最優先にして避難しろというものだ。「誰かを待っているうちに、共倒れになる」。過去の大津波で、幾度も多くの命が失われてきた中で生まれた“教訓”だった――。
泥水は、高橋さんがいる部屋の天井近くまで迫っていた。このままだと、息が出来なくなる。
「もうダメだ」そう思ったそのとき、再び、小さい頃に聞かされた“ある言葉”が、突然蘇った。
――「津波にのまれたら、息を止めろ」
それは、幼い頃に祖父が話してくれた昔話だった。「水を吸ったら終わりだ。息を止めて、力を抜け」と。漁師が津波にのまれて奇跡的に助かったことがあったのだという。医学的に正しい事なのかは全く定かではないが、不思議と心のよりどころになった。
「息を止めなきゃ」
高橋さんは口を固く閉じ、肺に残ったわずかな空気を守った。力を抜き、身を任せた。まもなく、目の前が水の色に覆われ、濁流に巻き込まれてぐるぐると回転し、上下も左右もわからなくなった。
意外と守ることができない
シンプルな教訓
――数日後。気づくと、高橋さんは搬送先の病院で寝かされていた。瓦礫(がれき)の下で倒れていたところを救助されたと、後から知った。
母の遺体は、流された自宅の裏手で発見された。手には、泥にまみれた手提げ袋が残されていた。
以来、高橋さんは、ずっと自分を責め続けてきた。自宅に戻ろうとした母を、自分が止めていれば。
高橋さんと母がとった、すぐに避難せずに「自宅へ戻る」という行動の危険性については、東日本大震災をきっかけに知った人も少なくないだろう。津波が発生する可能性がある場合は、迷わず高い場所に避難する。決して戻ってはいけない。このシンプルな教訓は、当然に正しいのだが、いざその場面に身を置くことになると、当人が守ることはそう簡単ではないようだ。