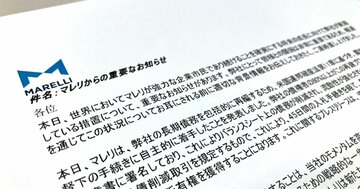日比谷聘珍樓(2025年5月東京商工リサーチ撮影)
日比谷聘珍樓(2025年5月東京商工リサーチ撮影)
横浜中華街の御三家として知られた名店「聘珍樓(へいちんろう)」を運営する(株)聘珍樓(横浜市港北区)が5月21日、東京地裁に破産を申請した。負債は12億1045万円だった。突然シャッターを下ろした老舗中華料理店のニュースは瞬く間に広がり、1000組といわれる予約が無効になって混乱を招いた。実は、「聘珍樓」を運営する会社の倒産が今回で3度目なのはあまり知られていない。現在、「聘珍樓」の商標権は破産と関係のない外国法人が所有し、復活を期待する声もある。名門中華料理店がたどった軌跡と「聘珍樓」のこれからを探った。(東京商工リサーチ 横浜支店 情報部 森澤章次)
多店舗展開やデパ地下出店で
中華街から全国区へ事業拡大
店名の由来は、「よき人、すばらしい人が集まる館」という意味があるという。横浜中華街で最古の歴史を誇った料理店「聘珍樓」は、1884年(明治17年)に産声を上げた。もともと店を経営していたのは1967年に法人化した(株)平川物産(旧商号:(株)聘珍樓、2017年3月に特別清算開始)だった。
中華街の名店から全国区へ。世の中がバブル経済で活況に浮かれた1990年代、高級中華料理店の多店舗展開を進め、デパ地下などで中華総菜やギフト商品も販売し、知名度を高めた。ピークの2001年3月期の売上高は118億円にのぼり、売上高は中華街トップクラスにのし上がり、「菜香新館」「萬珍樓」とともに御三家として君臨した。
だが、バブル崩壊、アジア通貨危機などで景気が低迷し、団体客や企業の接待利用が減少すると、横浜中華街でも安価な店が台頭し、売上高が落ち込んだ。一方で、店舗の維持費や人件費などの負担は重く、知名度向上と反比例して財務内容が悪化し、2007年3月期にはついに債務超過に転落した。不採算店の閉鎖で収益改善を目指したが、売上高は65億円(2016年3月期)とピークの半分に落ち込んだ。
この苦境を乗り切るため、中小企業再生支援協議会(現:中小企業活性化協議会)と再建を模索し、第二会社方式で事業再生を目指した。こうして2016年6月、「聘珍樓」はレストランと食品事業に関する権利義務を新会社に切り離し、社名を平川物産に変更して特別清算を申請した。負債は約25億円だった。