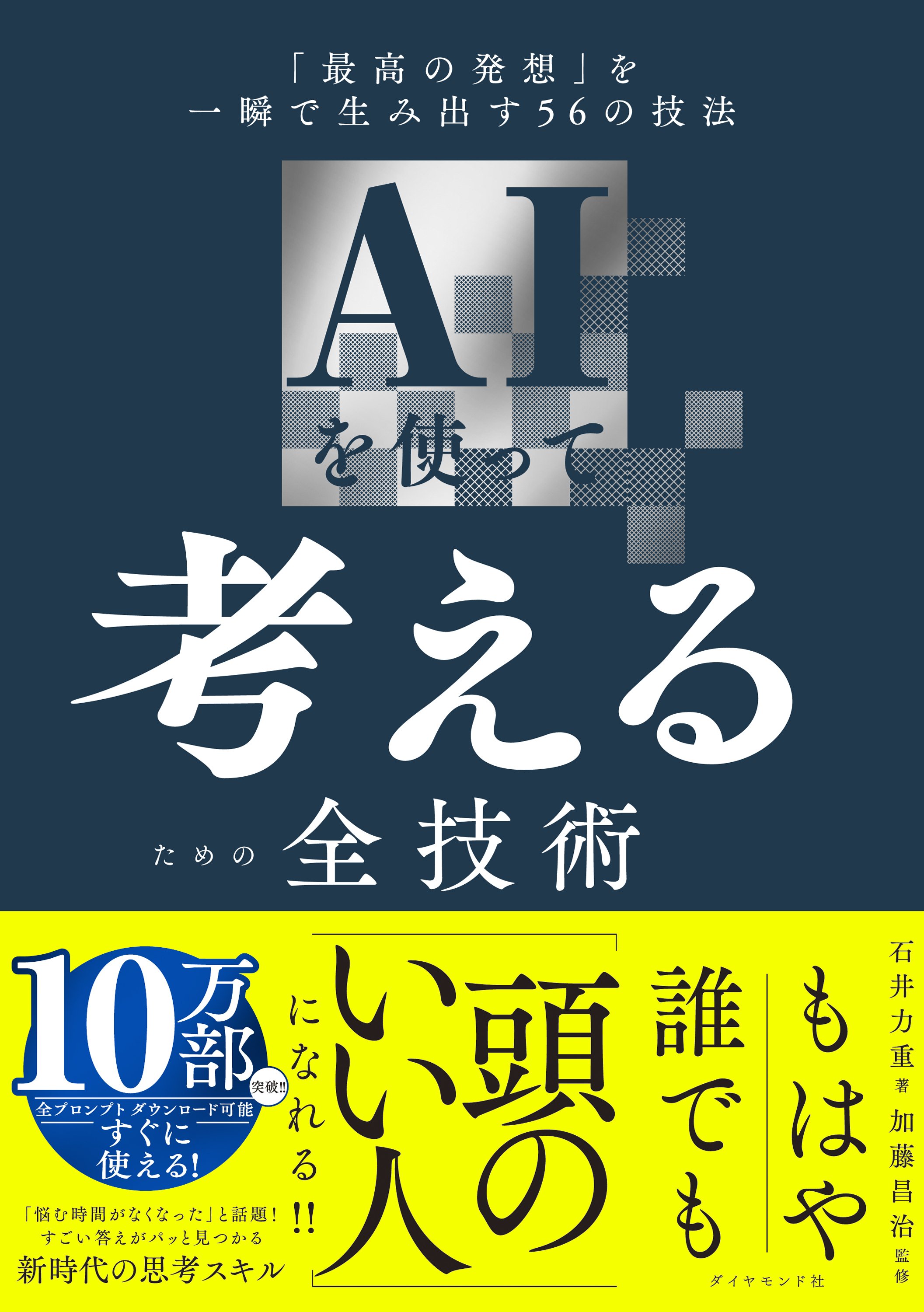いま、AIを使って仕事を進めることが当たり前になりつつある。しかし一方で、「AIなんて仕事の役には立たない」「使ってみたけど期待外れだった」という声も聞こえる。
「それは使い方の問題。AIの力を引き出すには適切な“聞き方”が必要です」。そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に研修をしてきた石井力重氏だ。「AIを仕事の効率化に使うだけではもったいない。適切に使えば“頭を使う仕事”にも大いに役立ちます」と言う。そのノウハウをまとめたのが、書籍『AIを使って考えるための全技術』だ。56の技法を全680ページで紹介。実践した人からは「AI回答の質が目に見えて変わった」との声も多く、発売直後から話題に。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も制作に協力した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「出しきった」と思ったときがアイデア出しのスタート
自らの考えを「発展」させ始める前に1つ、気にかけてほしいことがあります。それは、アイデアを「出しきったかどうか?」です。
アイデア発想において重要なのが、まずは「量」を出すこと。良いアイデアを選ぼうにも、発展させようにも、「磨けば光るアイデア」が存在していなければ意味がないからです。
では、いくつのアイデアを出せたら「出しきった」と言えるレベルになるでしょうか。「3つ」なんて言わないでくださいね。実務経験豊かなアイデアパーソンが数名集まるブレインストーミングを行ったなら、3桁におよぶアイデアが出てくることは普通の光景です。
そもそも、本当に素晴らしいアイデアを考えつくためには「出しきった」と思ったところがスタートです。その段階になって初めて、普通に考えても出てこない「盲点」のような領域にたどり着くことができますし、その領域には真に有用なアイデアが眠っています。
「出しきる」ために人間ができることの限界
残念ながら、人間には限界があります。どんなに頑張って考え尽くしても、すべての領域をカバーすることはまずできません。単独作業でも、チーム作業でも同様です。人間には認知的な偏りがあるからです。ゆえに、何十年も登場しなかった魅力的な新製品が新興企業からポンと出てきて、業界すべてが出し抜かれるなんてことが起こるわけです。
こうした偏りを人力のみで乗り越えるには、相当な苦労が要ります。よく使われるのは、2軸4象限を使った「アイデアマッピング」。チームメンバーから募ったり、ブレインストーミングで生み出されたりしたすべてのアイデアを、2軸で分割された4象限に置いていきます。すると、アイデアがたくさん出ている濃いエリアと、アイデアが出ていない手薄なエリアが視覚化されます。
視覚化されたなら、その空白領域を埋めるアイデアをさらに出していけばいいんです……と書いてしまうと簡単なんですが、実際にはそうはいきません。
まず現場で起こるのは「どの2軸にするか」問題。そもそもの軸が既存のありきたりなものだったら、空白領域を埋めたところで意味がありません。これまで語られてきた軸と軸では、おそらく「本当の空白(まだ世に出ていないアイデアの方向性)」が見えてきません。軸の設定自体にイノベーティブなアイデアが必要で、本当の空白を人力のみで探るのは困難な作業です。
AIで発想の盲点を明らかにする技法「新しい地平の探索」
こういった事情もあり、アイデアを「出しきる」のは難しい。ただ、1人きりで作業しているなら満遍なくアイデアを出すことはハードルが高く感じるでしょうけれど、AIのサポートを受けながらであれば、可能性を網羅するアイデア群を大量に出すのも難しくありません。
そのための技法が「新しい地平の探索」です。人間だけでは気づきにくい、アイデアの在り処をAIに探してもらいます。
こちらが、そのプロンプトです。
〈アイデアを得たい対象を記入〉というお題でアイデアを出してきました。アイデア群の偏りから、まだ考えられていないアイデアの方向性を見つけたいです。以下のアイデア群の偏りとして、どんなものがあるか教えてください。
〈ここまで出た全アイデアを記入〉
仕掛けはシンプル。すでに場に出ている全アイデアを入力して、「このアイデア群の偏りから、まだ考えられていないアイデアの方向性」を探す指示をすることで、まだ出ていないアイデアの「空白領域」をAIに見つけてもらいます。この手の概念処理が、AIはとてもうまいのです。
「空白領域」が見つかったら、今度は人力で発想してみましょう。人間の思考を遮る遮蔽物をガガガッと壊して新しい地平を見いだす作業はAIにお任せして、そこからは人間。「アイデアが出ていない領域」が可視化されたら、がぜんアイデアを思いつくことができます。もちろんAIに「その空白領域についての、有効なアイデアを出して」と追加の指示を出してアイデアを収穫することも可能です。
1人でアイデアを充分に出した、出しきったと感じた後に。あるいはチームでアイデアを持ち寄り、ブレインストーミングを経てアイデアを出しきった後に使うと、効果を発揮する技法です。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、分析、発想、発展、具体化、検証、予測といった“頭を使う作業”にAIを活用する方法を多数紹介しています)