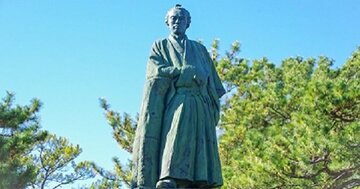天明3年に起こった浅間山の大噴火による溶岩流でできた光景(鬼押出し園) Photo:PIXTA
天明3年に起こった浅間山の大噴火による溶岩流でできた光景(鬼押出し園) Photo:PIXTA
江戸時代中期、江戸の三大飢饉の一つである「天明の大飢饉」が発生した。舞台の大河ドラマ『べらぼう』でも、米価高騰などの状況が描かれている。多くの死者を出した大飢饉。ドラマには描けないほど、すさまじい惨状だったという記録がある。(歴史学者 濱田浩一郎)
“異常気象”の後にやってきた
「天明の大飢饉」
江戸時代中期から後期を舞台にした大河ドラマ『べらぼう』では、米価の高騰が描かれています。くしくも、「令和の米騒動」に揺れる今の日本と、非常にリンクする内容といえます。
江戸時代中期に勃発したのが、「天明の大飢饉」です。1783(天明3)年の大凶作により深刻な飢饉となり、関東・東北に甚大な被害を与えました。
大飢饉の前兆は、1782(天明2)年の冬に見られました。その年は、12月になってもとても暖かかったといいます。菜種の花が咲きそろい、タケノコが生えてきて、春の陽気が感じられたとか。そうかと思うと、時々、雷雨があるという異様な気候でした。
年が明け天明3年、その年の春はさぞかし暖かくなるだろうと、人々は予想していました。前述したように、前年の12月から暖かい日が続いていたからです。
ところが、春になってみると冬かと思うほどの「寒気」が襲来。雨が降る日が多くなり、晴れた日は少なくなっていきます。5月になりこれから徐々に暑くなってくるかと思いきや、まだ寒さは去りません。
人は皆、綿入れを着て、火に当たるという状況。この気候では「作物が育たないだろう」と多くの人々が不安を感じていたようです。よって、穀物の値段が諸国同じように上がっていきます。
7月になると、さらなる災いが関東の人々を襲います。