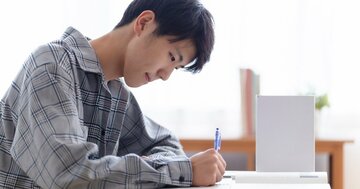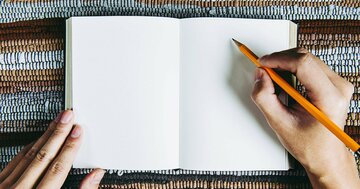頭のいい人の「モチベーション管理術」ベスト1
働きながら3年で、9つの資格に独学合格! 大量に覚えて、絶対忘れないノウハウとは?
「忘れる前に思い出す」最強のしくみ、「大量記憶表」を公開!
本連載の著者は棚田健大郎氏。1年間必死に勉強したにもかかわらず、宅建試験に落ちたことをきっかけに、「自分のように勉強が苦手な人向けの方法を編み出そう」と一念発起。苦労の末に「勉強することを小分けにし、計画的に復習する」しくみ、大量記憶表を発明します。棚田氏の勉強メソッドをまとめた書籍、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の刊行を記念して、メソッドの一部を公開します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「やる気が出ない」に効くすごい方法
本日は学習効率を上げる方法についてお話しします。
宅建試験に向けて日々学習を続けていると、多くの受験生が一度は直面するのが「モチベーションの維持」という問題です。特に権利関係に突入し始めたタイミングで、急に難易度の壁を感じてやる気を失ってしまう人が少なくありません。「権利関係が難しくて挫けそうです」「急にやる気がなくなってきました」といった声もよく聞きます。
確かに、宅建業法や法令上の制限までは比較的スムーズに進めたという人でも、権利関係に入った瞬間に「なんじゃこりゃ」とつまずくことは多いです。それはあなただけではなく、ほとんどの受験生が経験していること。むしろ当たり前なのです。私自身も初めて権利関係に取り組んだときは、まさにその壁にぶつかりました。
だからこそ、学習スケジュールの途中でモチベーションが下がってしまったときに「どうやって持ち直すか」が極めて重要になります。私が皆さんに強くおすすめしたいのが、フィットネスジムの活用です。
なぜフィットネスジムがモチベーション維持に効果的なのか?
まず第一に、ジムに来ている人は、総じて前向きなエネルギーを持っています。健康を意識していたり、体を鍛えたいと思っていたり、何かしらの「目標」を持って通っている人が多い場所です。そんな空間に身を置くだけで、自然と気持ちがポジティブに引っ張られていきます。
「自分も頑張ろう」「もう少し続けてみよう」と思えるようになるんです。これは理屈ではなく、体験するとわかります。ネガティブな雰囲気の居酒屋で飲んだり愚痴をこぼすより、ジムで汗を流して前向きな空気に浸った方が、圧倒的に気持ちは晴れます。
そしてもうひとつの理由、それは「ながら学習に最適な環境」だということ。ランニングマシンで軽くジョギングしながら、Bluetoothイヤホンで耳学をします。耳学とは、市販の問題集を音声で耳から聞いて学習することです。自分のスマホを使って、自分で録音します。その音声を繰り返し聞くだけでも、記憶にしっかりと残っていきます。これが本当に効率的なんです。ジムでの運動中はある程度意識が空く時間帯。そこに音声学習を組み合わせることで、健康管理、モチベーション維持、そして学習効率アップと、一石三鳥です。
私自身、毎日平日は1時間と決めてジムに通っています。30分程度ランニングや筋トレをして、その後お風呂に入って帰る。たったそれだけのルーティンですが、これだけでも気持ちは大きく変わります。ストレスがリセットされ、また次の日に向けての活力が戻ってくるんです。
「時間がない」「疲れている」からこそ、ジムを活用してほしい
よく「そんな時間があったら勉強したい」と言う方がいます。でも実は逆なんです。疲れているからこそ、勉強が手につかなくなる。集中できない。だから、まずは心と体をリフレッシュさせて、モチベーションをリカバリーする必要があるんです。その方法として、ジムは最適なんですね。
ジムのいいところは、拘束時間が短くて済むということ。1時間もあれば十分。しかも、24時間営業のジムも増えているので、早朝や深夜に通うこともできます。今の時代、感染対策も進んでいるので安心して利用できますし、月会費もリーズナブルなところがたくさんあります。
勉強を頑張る人を、周囲も応援しよう
もしご家族に宅建を目指している方がいるなら、ぜひジムに行く時間を作ってあげてください。その間、お子さんの面倒を見るなどの協力をするだけで、受験生の学習とメンタルのサポートになります。これは受験に限らず、転職や仕事に対するモチベーションにも通じる部分です。
「ジムなんて自分には合わないかも」と思っている方も、ぜひ一度足を運んでみてください。誰かとコミュニケーションをとる必要はありません。ただ、前向きな空気の中で、自分のペースで運動するだけで十分です。それだけで、気持ちは変わります。
宅建の勉強に疲れたら、ジムで汗を流す。そしてイヤホンで音声学習。心も体もリセットされ、また前を向けるようになります。時間がない中でも、少しの工夫でモチベーションを取り戻すことはできます。自分を追い込みすぎず、うまくリズムをつくって、今年の試験を乗り切っていきましょう。
(本原稿は、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の一部抜粋・加筆したものです)