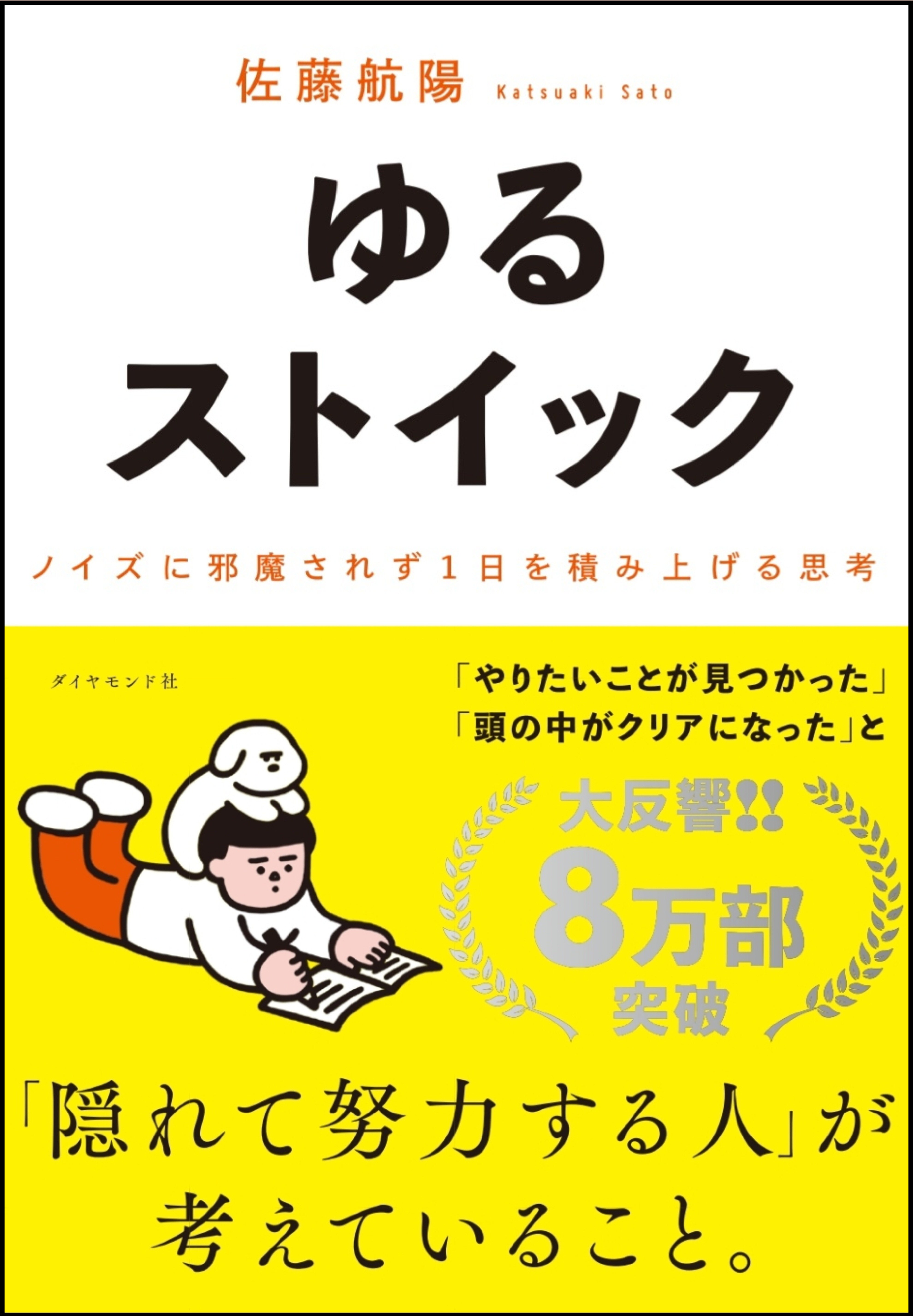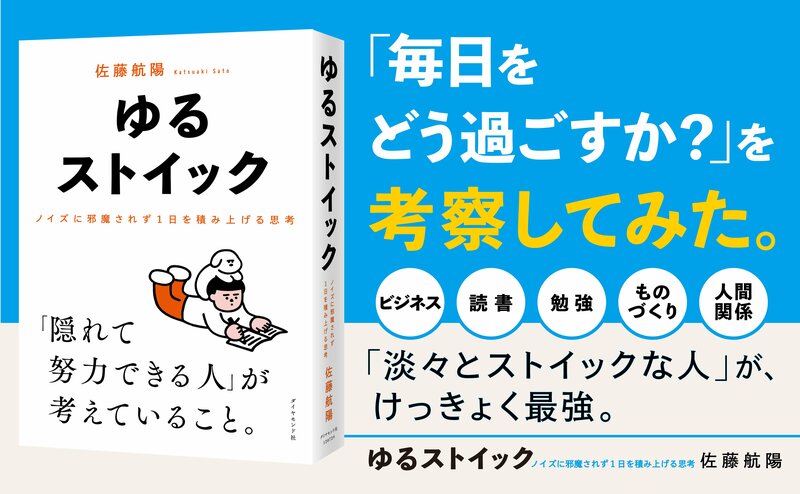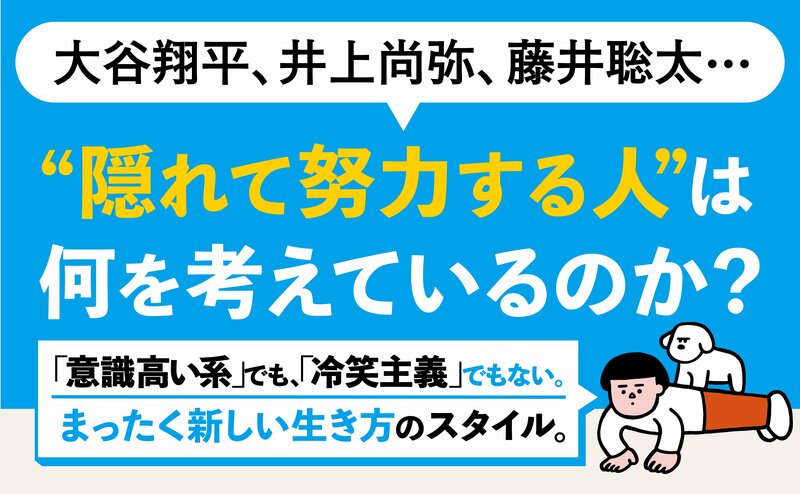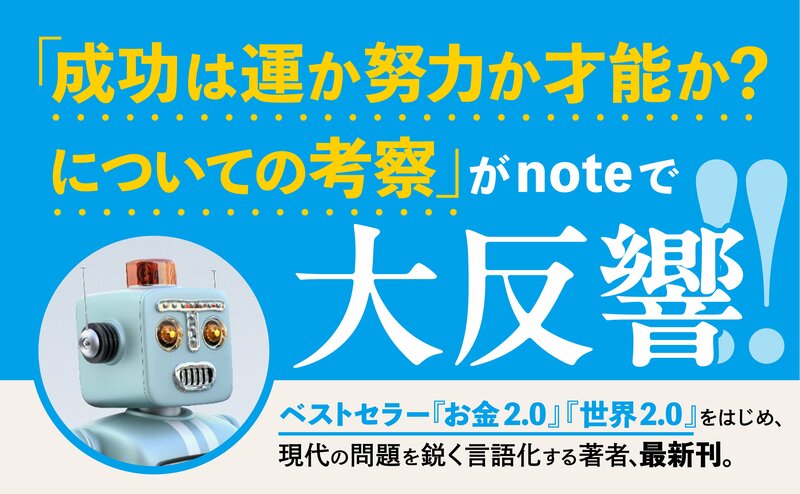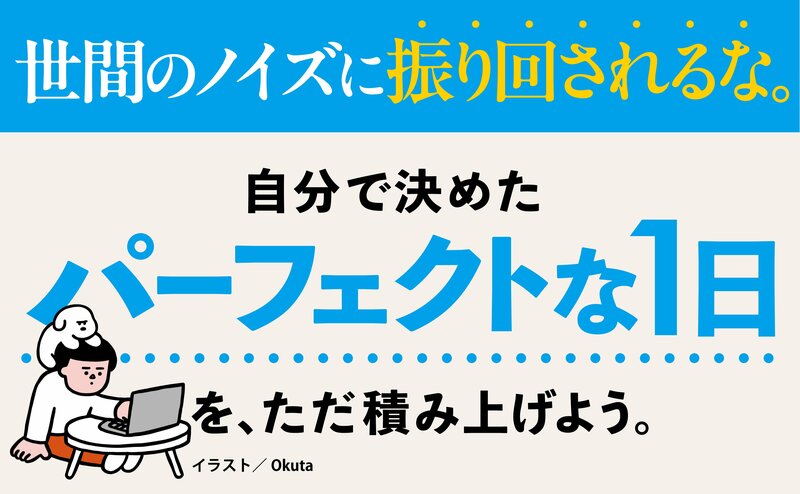日本人の8割が小学校レベルの国語と数学の問題を正しく解けない。じゃあ、どうやって伝えればいいのか。
次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。数々の成功者に接し、自らの体験も体系化し、「これからどう生きるか?」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。
コロナ後の生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち(大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…)は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。
『ゆるストイック』では、新しい時代に突入しつつある今、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、「私自身が深掘りし、自分なりにスッキリ整理できたプロセスを、読者のみなさんに共有したいと思っています」と語っている。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「言葉」は不完全
これからの時代をどう生きればいいのか。
その話をまとめていきましょう。
現代社会において、「言葉」は過剰に評価されていると言えます。
私たちの社会の多くは、「言葉」を基盤に築かれています。
法律や規則、論文や書籍など、近代社会の枠組みの大半は文字情報を基に成立しているからです。
しかし、実際には、言葉は人類のコミュニケーション手段の中で最も「新参者」です。
言葉が誕生するはるか昔から、視覚、聴覚、嗅覚などの感覚は、生物の進化の過程で重要な役割を果たしてきました。
心理学の有名な「メラビアンの法則」によれば、人がコミュニケーションを取る際、相手に影響を与える情報の割合は、言語情報がわずか7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%だとされています。
つまり、目と耳から入る情報が9割以上を占めており、言語そのものが人に与える影響は非常に小さいのです。
たとえば、ボロボロの身なりの人が国際政治について語ったとしても、多くの人はその話を真剣に受け止めないでしょう。
一方で、ハリウッドスターのような容姿やセレブリティのような身なりをした人物が同じ内容を話せば、それに耳を傾ける人が増えるはずです。
この例が示す通り、容姿や声といった情報のほうが、言語よりも人々を動かす力が強いのです。
日本人の約8割が小学校レベルの問題を解けない
さらにショッキングなデータもあります。
実際には、多くの人の国語力や数学力は「小学校高学年のレベル」で止まっているという調査結果があるのです。
OECDが中心となって実施する「OECD国際成人力調査(PIAAC)」というものがあります。ざっくり言えば16〜65歳の大人を対象とした学力テストです。
そのテストでは、点数によって「習熟度」という指標でレベル分けされます。
「習熟度レベル4」で小学校高学年から中学校低学年の国語と数学のテストに出るような問題を解ける学力と捉えてかまいません。
令和6年12月の調査結果からは、以下のようなことがわかっています。
1 読解力(国語)の習熟度レベル4以上に該当する日本人は約2割(20.9%)
2 数的思考力(数学)の習熟度レベル4以上に該当する日本人は約2割(21.2%)
つまり、「日本人の約8割が小学校高学年の国語と数学の問題を正しく解けない」という事実が見えてきてしまいます。
この記事を読んでいるような読者の中には、「そんなバカな」と思う人もいるでしょう。
しかし、これが事実なのです。
言い換えれば、日本人の8割の人々の読解力や数的思考力は、小学校4〜5年生と同程度であるということになります。ちなみに、日本人の習熟度レベルは先進国でもトップです。
つまり、知識社会に適応できた人類の割合は多くの人々が考えるよりも少なく、多めに見ても全体の2割という事実が浮かび上がってきます。
この事実を冷静に受け止めれば、SNS上での論争や世の中で起きている問題の構造を理解しやすくなるはずです。
近代社会は、知識社会に適応した一部の人々によって設計されました。
法律、科学、経済、政治など、あらゆる仕組みが「言語」と「論理」を基盤にして成り立っています。
しかし、実際は人類全体の8割の人々がこの知識社会にまだ順応できておらず、その恩恵を享受していません。
現代の二極化や経済格差は、経済的な問題だけでなく「知識格差」とも言える構造を持っています。
アメリカの大統領選挙に富裕層・エリート・インテリの多くが驚いたのは、自分たちが置き去りにした多くの人々からの「しっぺ返し」を食らったからに他なりません。
自分たちが作り上げた知識社会から取り残された人々の怒りや不満が、自分たちの足場を崩す流れを後押ししているのです。
その事実を前提にして、私たちはコミュニケーションをしていかなければなりません。
言葉だけではなく、「画像」や「動画」を用いるなど、「説明すれば伝わるはずだ」というバイアスを取り除き、伝える手段を変えてみることをしていきましょう。
株式会社スペースデータ 代表取締役社長
1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人(Forbes 30 Under 30 Asia)に選出される。最新刊『ゆるストイック』(ダイヤモンド社)を上梓した。
また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。