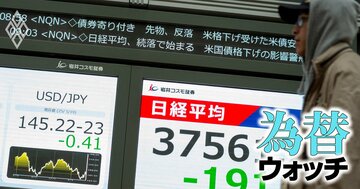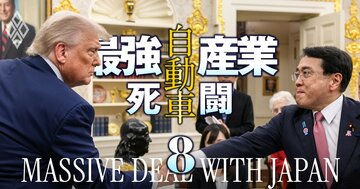国の関税措置に関する総合対策本部で発言する石破茂首相(右から2人目)=25日、首相官邸 Photo:JIJI
国の関税措置に関する総合対策本部で発言する石破茂首相(右から2人目)=25日、首相官邸 Photo:JIJI
曖昧な関税引き下げの日本の代償
80兆円投資の具体的な仕組みは不明
日米関税交渉が7月22日に合意に達した。相互関税の国別上乗せ税率は25%とされていたが、15%になり、日本が撤廃・縮小を求めていた自動車25%関税は12.5%になり既存の2.5%と合わせると関税率は15%になる。
こうしたアメリカの関税引き下げの代わりに、日本は5500億ドル(約80兆円)の対米投資やアメリカの農産物やコメの輸入拡大などをするという。
トランプ大統領は、「史上最大のディールだ」と、SNSの投稿で成果を強調、一方で石破首相も「対米貿易黒字を抱える国の中で、(関税率は)最も低い数字」「守るべき国益は守った」と語った。合意を受けて、日経平均株価は大幅に上昇した。
しかし、今回の合意は手放しで喜んでよいものとは言えない。
関税率引き下げの代償として、どのような責任を日本がこれから負うことになるのかが、はっきりしないからだ。
とりわけ問題なのは、80兆円の投資という約束の具体的な内容がほとんど分からないことだ。この約束によって、日本はアメリカに対して今後どのような義務を果たす必要があるのか、投資を達成する期間はいつまでなのか、そもそも投資を決定する主体はどこなのか、肝心な点が明らかにされていない。
これまでも通商や外交交渉で重要な点を曖昧にされたまま、「合意」が演出されることはなかったわけではない。
だが巨額の対外投資であり、悪くすれば日本産業の空洞化も招きかねない。政府は合意の内容を詳しく国民に説明する必要がある。