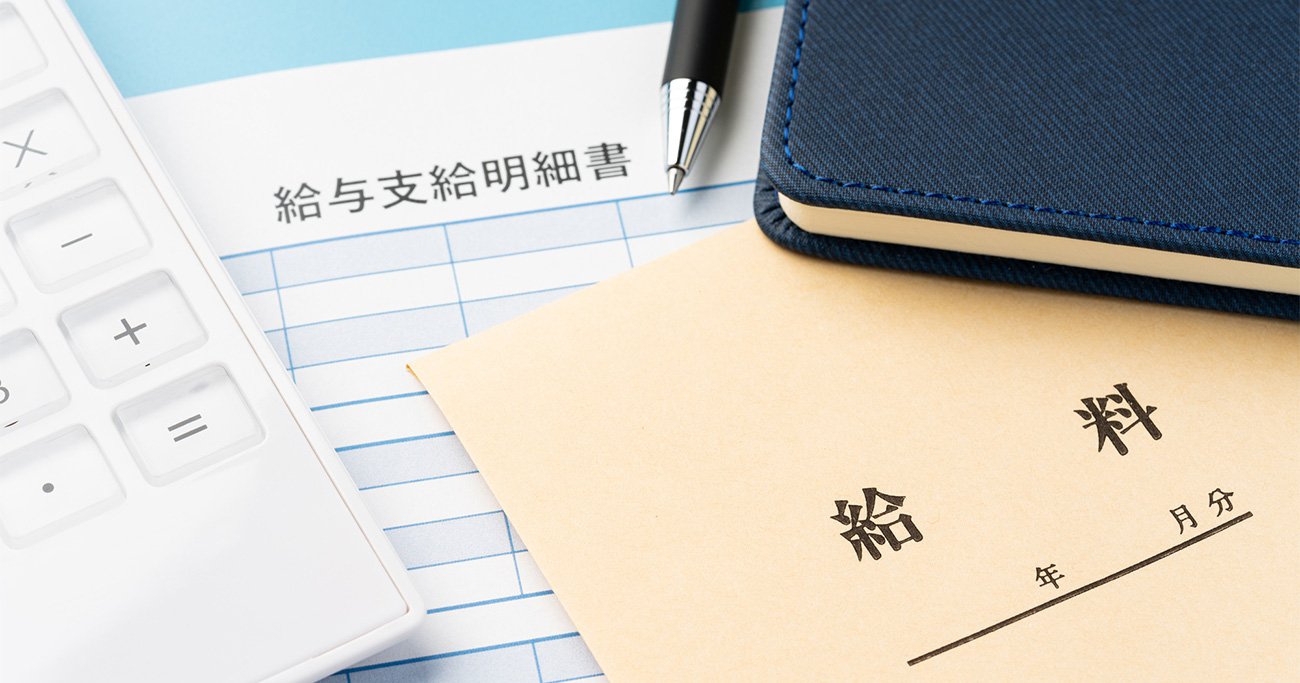 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「来期から賞与を廃止し、その分を月給に上乗せします」――社内でこんな発表があったら、社員はどんな反応をするでしょうか。真っ先に気になるのは、「得か損か」でしょう。月々の給与アップは嬉しくても、「手取りは減らないのか」「評価はどう反映されるのか」といった不安が同時に湧き上がるかもしれません。会社としては、「ボーナスの給与化」のメリットを生かしつつ、デメリットをどうケアするかが重要です。制度変更で生じるリアルなギャップを洗い出し、社員の納得感を高めるポイントを解説します。(特定社会保険労務士、大槻経営労務管理事務所 永野奈々)
ソニー、大和ハウス、バンダイも導入!
「ボーナスの給与化」が増えている?
2025年春以降、ソニーグループや大和ハウス工業、バンダイなど大手企業が相次いで「賞与の一部を月給へ組み込む」報酬改革を公表しました。
●ソニー:冬季賞与を廃止し、初任給を最大4万8000円引き上げ
●バンダイ:初任給を約30%アップ
●大和ハウス:月例給を平均10%引き上げ
企業側は、「年収総額は維持しつつ支給タイミングと内訳を見直す」のが狙いのようです。「ボーナスを分割し給与に上乗せする企業が増加」などと報道されたことから、「ボーナスの給与化」と言われるようになりました。単なるトレンドではなく、報酬設計の新しい流れとして注目されています。今後は中小企業でも追随が増えると予想されます。
ではなぜ今、企業はボーナスの給与化を選ぶのでしょうか。主に次の三つが考えられます。
(1)人件費の見通しを立てやすくする
賞与は業績連動のため年度末のキャッシュアウトが読みにくい一方、月給化すれば毎月の固定費として計上でき、資金計画が立てやすくなります。とりわけ複数の拠点(海外含む)を持つ企業では、為替リスクなどと相まって賞与のブレが経営課題になりがちです。安定的なコスト管理は大きなメリットとなります。
(2)採用競争力の強化
若手ほど「月々いくらもらえるか」を重視する傾向があり、求人票で高い月給を提示できれば応募率は上がるでしょう。「初任給30万円」などインパクトのある表現が可能となり、求職者の目を引きやすくなります。
(3)報酬体系のシンプル化と納得感の向上
成果主義の浸透に伴い評価制度が複雑化し、従来の賞与がインセンティブとして機能しにくい企業も少なくありません。「複雑な変動給で説明責任を果たすより、ベース給を厚くして透明性を高める」という考え方が広がりつつあるのです。これにより、評価への納得感を上げ、マネジメント負荷の軽減が期待されます。







