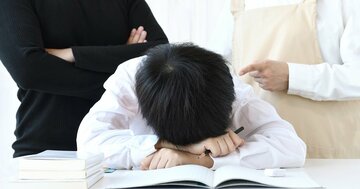そもそも嫌なことに耐える根性は必要でしょうか?根性は興味のあることに没頭してこそ、育つものです。
もしかしたら、習いごとの先生への気遣いや世間体など、いわゆる大人の事情を気にしているのかもしれません。それよりも、子どもの「好き」を優先することのほうがずっと重要です。
一般的に、何かをやめるときには心理的ハードルが高くなるものです。
就職よりも退職、付き合うときより別れるとき、結婚よりも離婚、飲み会も集合よりも帰るタイミングを見計らうほうがずっと難しい。
だから、子どもに根性がつかないという問題ではなく、そもそも親御さん自身のやめることへのハードルが高いのかもしれません。このタイミングに、親子で「やめるレッスン」をすることも大事な体験です。
思考停止でずっと嫌な場所に通い続けていると、快・不快すら自分で捉えられなくなってしまいます。
そして、何かを手放さないと新しいものは入ってきません。
子どもが好きではない習いごとを手放したら、今度は子どもが夢中になる習いごとや活動に出会えるかもしれません。そんなふうに考えて、次に進んでみてはいかがでしょうか。
(お悩み3)
意欲が感じられなくて不安
子どもの言葉を真に受け過ぎないことも大切です。子どもと対話をしたり子どもの様子を観察したりすることは重要ですが、親がそのすべてに反応していては自分の身が持ちません。
お子さんは「いやだ」「できない」とつぶやいて、本当にやっていないのでしょうか?
たとえば、大人も仕事に取りかかるときに「うわぁ、こんなに作業があるのか。やりたくないなー」や「洗濯物の山!マジで面倒!」と思うことはたくさんありますよね。それでも、なんやかんやで取り組んで終わらせます。
子どもの場合は、大人が口に出さない心の声が漏れ出しているだけです。
「いやだ」「できない」の声は、ほどほどに受け止めましょう。