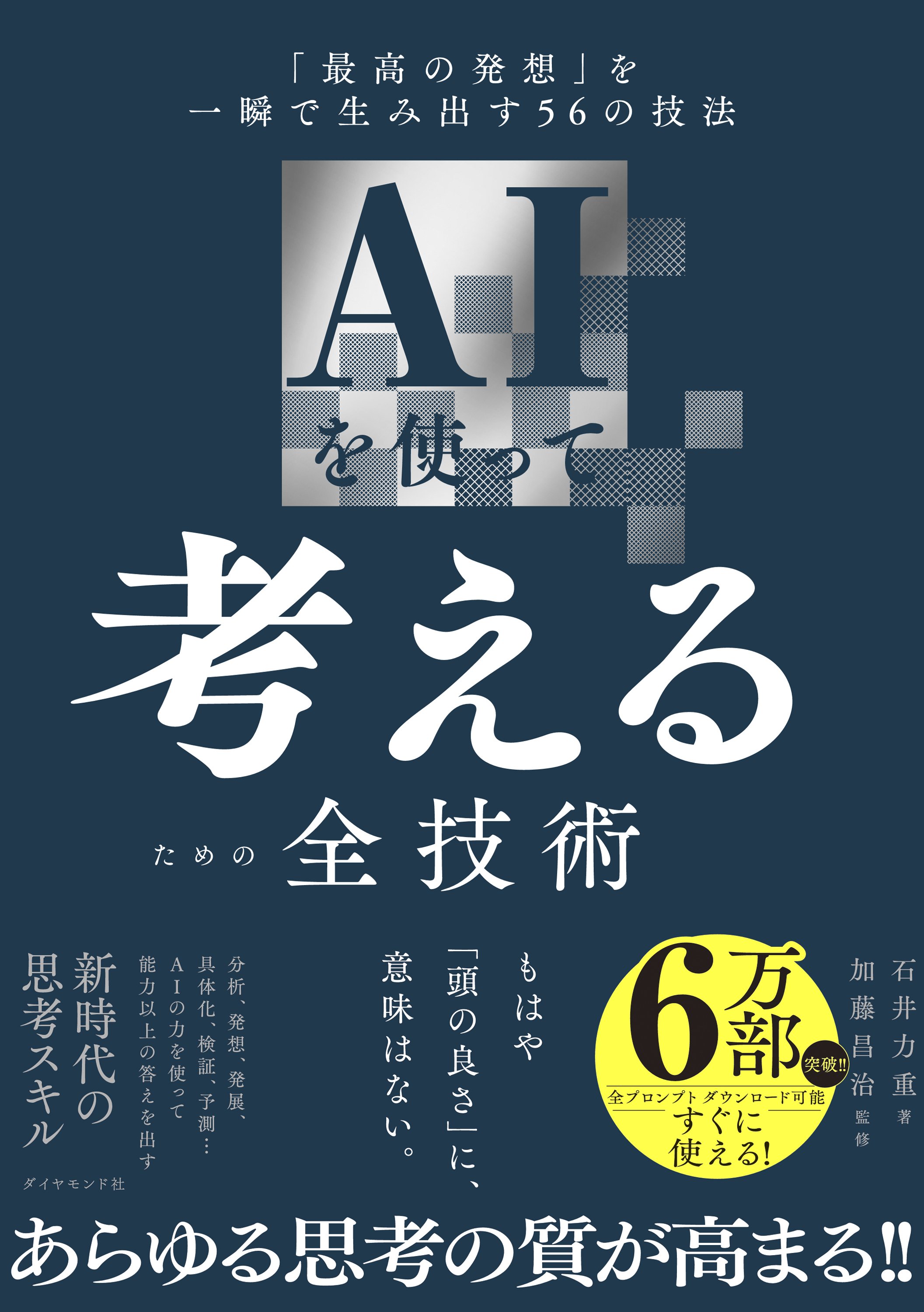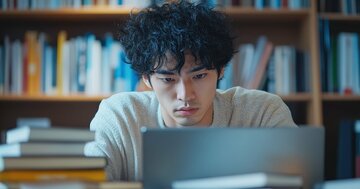街から野良猫を減らす取り組みには、多様な専門家の知識とスキルが求められます。以下に、それぞれの専門家がどのような貢献をする可能性があるかを具体的な案とともに示します。
1.クリエイティブな専門家
・猫の飼い方や避妊手術の重要性に関する意識啓発キャンペーンを企画し、広告、ポスター、ビデオコンテンツを制作する。
・野良猫の問題に焦点を当てたアートプロジェクトや展示会を開催して社会的な関心を高める。
2.技術専門家
・避妊・去勢手術の効率化やコスト削減を目指して、新しい医療技術や手術機器の開発を行う。
・野良猫の動きを追跡し、人間との衝突を避けるためのスマートな監視システムを開発する。
3.ビジネス専門家
・野良猫問題解決に向けた社会的企業やNPOを立ち上げ、資金調達やビジネスモデルの構築を行う。
・地域コミュニティと連携し、猫の適正飼育や里親制度の普及を促進するプログラムを開発する。
4.学術研究者
・野良猫の生態や行動パターンに関する研究を行い、科学的根拠に基づいた管理策を提案する。
・野良猫による生態系への影響を評価し、保全生物学の観点から解決策を考察する。
~~~~~(以下、略)~~~~~
紙面の都合で省略しましたが、AIは他にも「社会科学者」「ユーザー(地域住民や猫愛好家)」「ディスラプター」「ユーモアのセンスを持つ人々」「冒険家」と、9人の専門家の視点からアイデアを出してくれました。
出てきたアイデアの数、そして要した時間。いずれも驚異的なレベルです。出てきたすべての回答を自分だけで思いつこうとしたら、かなりの時間と労力を要するはず。アイデア発想の充分な経験を積んだ人でも、簡単にはいきません。
求める回答を得るまでAIと「対話」する
さて、本当に重要なのはここからです。各技法のプロンプトによって出力されるAI回答は、いわばスタート地点。その回答をどう捉えるか、続けて何を聞いていくかによって、たどり着けるゴールは変わってきます。
技法を使ったやりとり。残念ながら1往復のラリーだけで、すぐに素晴らしいアイデアにたどり着けるとはかぎりません。アイデア自体は玉石混交なことも多々あります。
そしてAIは、一回あたりの指示文が長いと、指示文の中盤あたりの指示をすっぽかしたりします(将来的には改善されると思いますが、本書制作時点では)。質問の最初と最後だけに回答してきたり、途中で尻切れトンボになったり。AIからの塩対応、私も何度もくらったことがあります。
よって、価値あるアイデアにたどり着くコツは、3~4回に分けてやりとりをすることです。
7つほどアイデアがほしいと依頼したのに5つで止まってしまったら、気を取り直して「続きをお願いします」「最後まで出力してください」と聞き直しましょう。回答が大ざっぱだなと思ったなら、「もっと具体的にしてください」「抽象的すぎるので、細かく記述してください」と重ねて聞きます。人間同士でのやりとりと同じです。
やりとりを重ねるうちに、AIが最初の質問を忘れてしまうこともたまにあります。そんなときは仕切り直し。チャットを一度終了して最初からやり直します。面倒くさいのですが、その方が早いのです。
プロンプトを知るよりも「大事なこと」
こういったAIを使って考える方法を、本の中では56個の「技法」としてまとめました。それぞれの技法は、AIで実行する際に必要な「プロンプト(問いかけのひな型)」の形になっています。基本的には、各技法のプロンプトを使って、皆さんの「課題」や「目的」といった、アイデアを得たい対象について聞いてもらうだけでOKです。
各プロンプト、まずは「そのまま」使ってみてください。効果的な回答を得られるよう、AI用にチューニングした文章だからです。複数種類のAIにおいても一定の有効性を担保している、汎用性を重視する工学的なアプローチで開発されています。慣れてきたら自由演技もOKですが、最初は守破離の「守」からをおすすめします。
なお、本書に記載しているプロンプトは、あくまでも本書制作時点で、AIから有用な回答を得られるように調整したものです。皆さんも体感しているように、AIは日々ものすごいスピードで進化しています。本書を手に取った時期によっては、紹介しているプロンプトが通用しなくなっていることも充分考えられます(その場合でも、まったく的外れな回答になるということはないと思いますが)。
よって、AIの「使い方」の部分にも着目していただきたい。「専門家の知見を取り入れたアイデアを生み出す」「アイデアのリスクを検証する」「プレスリリースの形にまとめる」……などなど、本書では様々な用途の技法を紹介しています。「こんな使い方もできるのか」と知っていただくだけでも、本書は充分に価値を発揮できるでしょう。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを使って思考の質を高める方法を多数紹介しています)