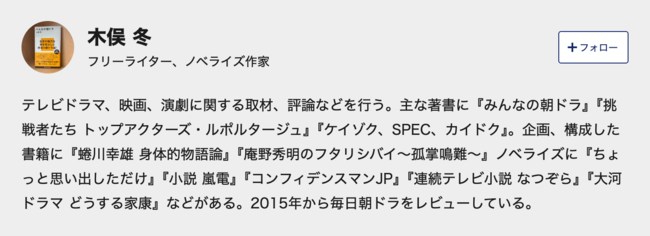作家自身が主人公になった朝ドラは?
砂男から佳保の事情を聞いて、のぶも嵩もまた、幼い頃に父を亡くしているから、共感を覚える。戦後は、父母を亡くした戦災孤児もたくさんいた。世界には、家族を亡くした人たちがたくさんいる。その寂しさが嵩の愛にあふれた詩で少し癒やされる。
主人公の幼少期を演じた子役が終盤、登場するときはたいてい、主人公の子どもや孫など身内の役が多いが、今回、偶然出会った少女役で登場。でも、親を早くに亡くした子どもという点で、のぶと佳保は似ている。
永瀬は幼いのぶと、生意気・佳保をみごとに演じ分けていて、同じ俳優とは思えないほどだ。
「あなたの書く詩には喜びの裏にどうしようもない悲しみが滲んでいる」と砂男は言う。
帰り、嵩は、佳保に似顔絵を渡す。実際、中園も似顔絵を描いてもらっていて、ドラマの制作発表のときに持ってきていた。この時点で、終盤のこの展開を構想していたのかもしれない。
嵩の詩が誰でも書けそうなやさしいものだから自分も書けそうと、即興で詩を諳んじて、「やない先生がなれるんだから私もなれる」と自信満々だった。やがて佳保は、売れっ子脚本家に育つのであろうか。
脚本家の実人生を書いた朝ドラには、橋田壽賀子の自伝ドラマ『春よ、来い』(NHK、1994〜95年)がある。
『おしん』に続き1年間の大作だ。いまは放送100年だが、こちらも放送開始70年の節目に制作された。折しもいまは放送100年。中園ミホも自伝とはいかずとも、父を亡くした少女がやなせたかしと出会って、救われ、同時にやなせたかしも少女に出会って活力を得たというすてきな物語を生み出したようだ。
この物語は昨今注目されている「ナラティブ(語り、物語)・アプローチ」によるものだろう。起承転結のストーリーではなく、書き手の個人的な主観(ナラティブ)が強調されることで、自分ごと感が高まり、受け手の共感を促す。物語の強度が上がるのだ。
『あんぱん』に作家自身の実体験に基づいて、作家自身をモデルにした少女が出てくることで、『あんぱん』というフィクションに説得力が生まれる。その一方で、こういう作家の主張が強く出たものが好きではないという視聴者もいるとは思う。
賛否両論あるだろうが、長丁場で息切れしがちな朝ドラの終盤に来て、強烈な球を投げてきたことには感心する。