「中間管理職の悩みが消えた」
「ハラスメントに配慮して働けるようになった」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
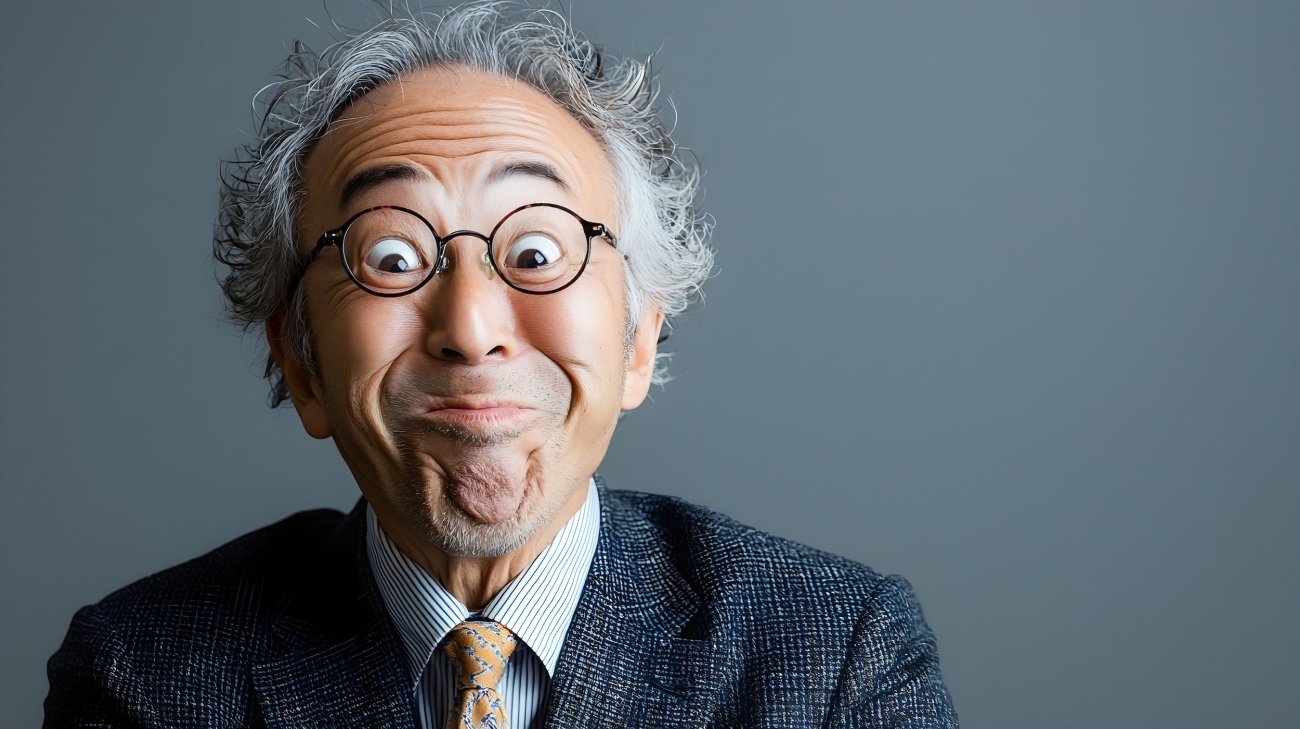 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
リーダーになった瞬間に崩れる組織
組織において、プレイヤーとして優秀であっても「リーダーには絶対に向かない人」が存在します。
そのような人物が昇進すると、現場は停滞し、メンバーは疲弊し、最終的にチーム全体が機能不全に陥ります。
問題なのは、その人が、一見「真面目」で「仕事が速く」「コミュニケーションも悪くない」ことです。
表面だけを見れば、むしろ昇進させたくなる人物です。
だからこそ、見極めが難しいのです。
ワースト1:「他責志向」が抜けない人
絶対に昇進させてはいけない特徴。
それは「何か問題が起きたとき、他人や環境のせいにする傾向が強い人」です。
これが組織を最も破壊する性質です。
このタイプの人は、メンバーの成果が出ないときに「本人の能力不足」「他部門の協力がないせい」「タイミングが悪かった」など、外的要因にばかり原因を求めます。
自分のマネジメントの欠陥には目を向けません。
リーダーというのは、「うまくいかない原因を自分のマネジメントに求める力」が問われるポジションです。
自責で考えることができない人がマネージャーになると、組織は改善されることなく、問題が再生産され続けます。
リーダーに求められる最低条件
「成果が出なかったのは自分の指導の仕方に問題があったのかもしれない」
「計画の立て方を見直す必要があった」
このように、原因の中心を自分に置けるかどうかが、リーダーに求められる最低限の条件です。
一方で、他責の人は、問題の当事者にならずに、評論家的な態度を取り続けます。
これはチームにとって極めて有害です。
仮面をかぶって、淡々と選びましょう
昇進という判断には、時に冷たさが求められます。
感情ではなく、数字や過去の傾向を踏まえて選抜すべきです。
感情を脇に置いて、仮面をかぶりましょう。
リーダーにすべき人を、淡々と選び抜いてください。
(本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです)
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。










