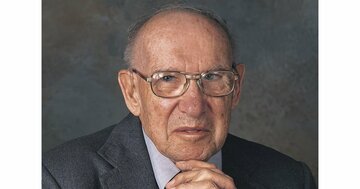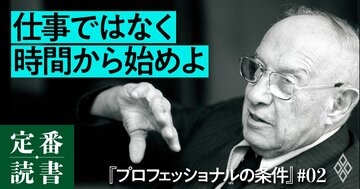今年はマネジメントの父、ピーター・F・ドラッカー没後20年。そのマネジメント論は現代でも深く息づいています。
「マネジメントの基礎を身につけたい」
「リーダーとして、どうメンバーに接したらいいのかわからない」
「管理職として仕事をしてきたけど、うまくいっていない気がする」
「ドラッカーは難しそうだから、今まで触れてこなかった」
そのような悩みを解決するヒントが詰まった書籍『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』が発売されます。本書は、これまでドラッカーを知らなかった人でも物語の中でその本質を学べる1冊です。
本記事では、著者の吉田麻子氏がドラッカーから学べることをストーリー形式で解説します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
超優秀、だけど遅刻癖のある部下
「またかよ……」
高橋課長(仮名)はため息まじりに小さい声を漏らした。
会議のたびに3~5分遅れてくる、部下のA君。
他のメンバーはすでに着席している。とがめるようにA君を見る者が数名いた。
A君は気にする素振りもなく静かに席に着く。
会議がまさに始まろうとする頃に悪びれずに現れる彼の姿は傲慢にも見え、組織の雰囲気を害しているように感じられた。
普段は仕事ができる優秀な部下だ。
しかし、会議の時間を守るのもまた大切なことではないか――。
そんなモヤモヤを長く抱えていた高橋課長が休日の午後に借りてきたドラッカーの本をめくっていると、ある一文が目にとまった。
「これは……」
そこには思いがけないヒントがあった。
強みに焦点を合わせる
『現代の経営(上)』の第13章「組織の文化」の冒頭に、こうある。
「重要なことは、できないことではなく、できることである」
続く箇所にはこうも書かれている。
「組織の良否は、人の強みを引き出して能力以上の力を発揮させ、並みの人に優れた仕事ができるようにすることができるかにかかっている。同時に、人の弱みを意味のないものにすることができるかにかかっている」
「焦点は常に、強みに合わせなければならない」
ドラッカーの言う「強み」とは、単なる得意なことではない。
たとえば、「英語が得意」というのは結果にすぎず、その背景には「社交性」「継続力」「集中力」などの“資質”がある。
資質とは、その人らしさそのものだ。
先天的な資質としてすでに備わっているその人固有の強みを磨くと、他の人には真似のできない卓越性となっていく。