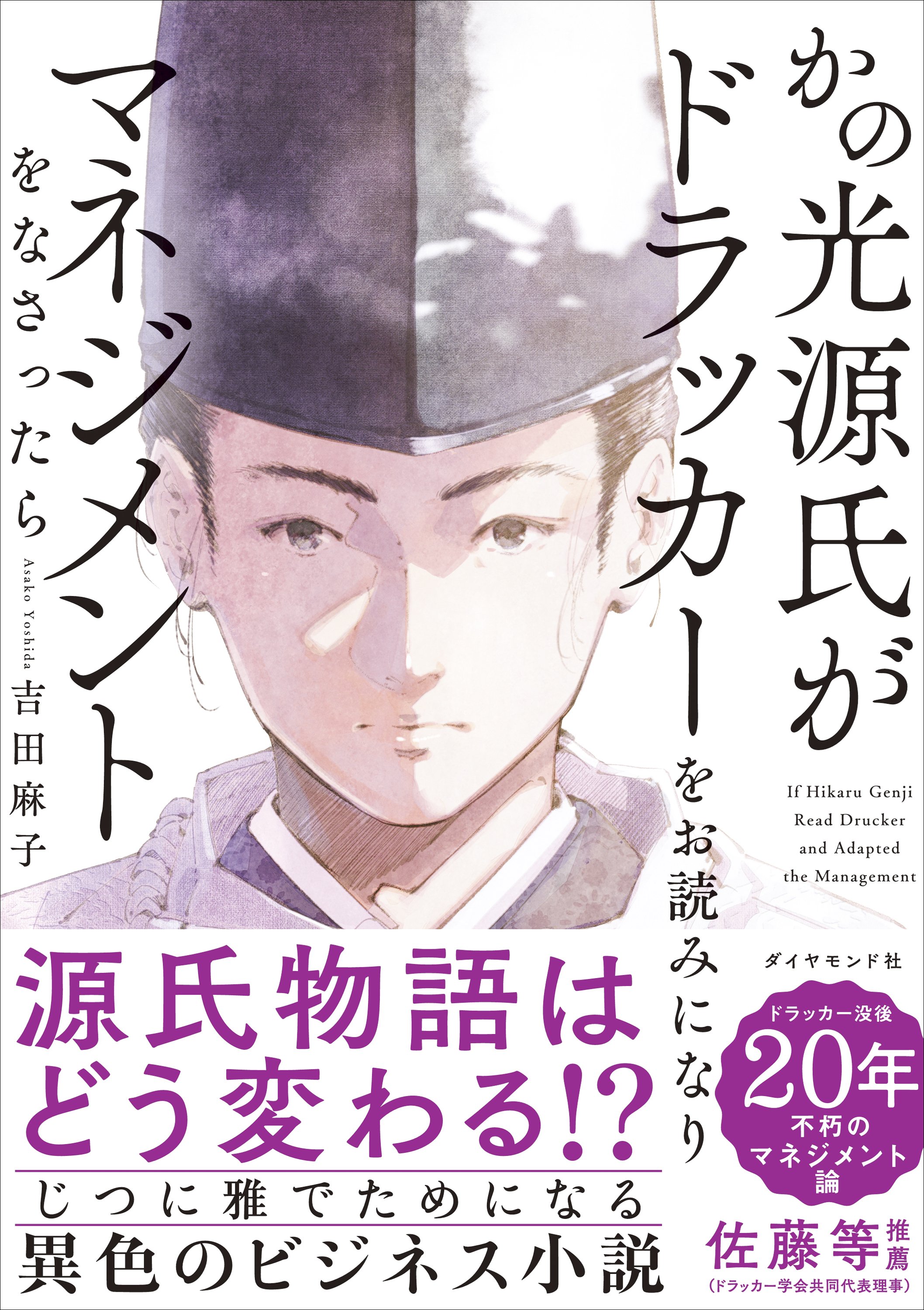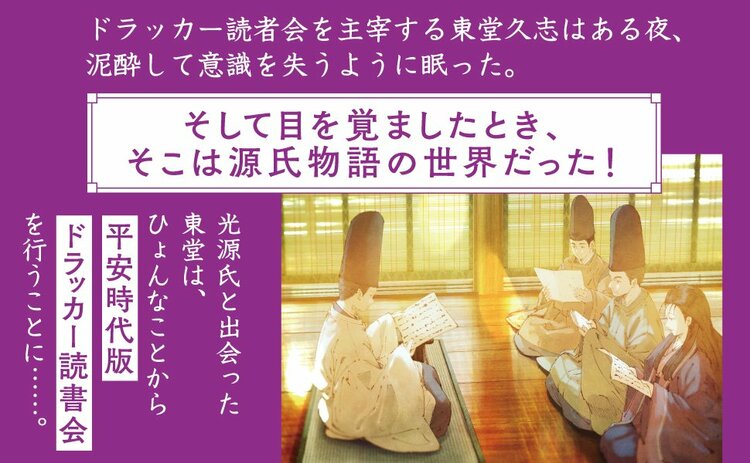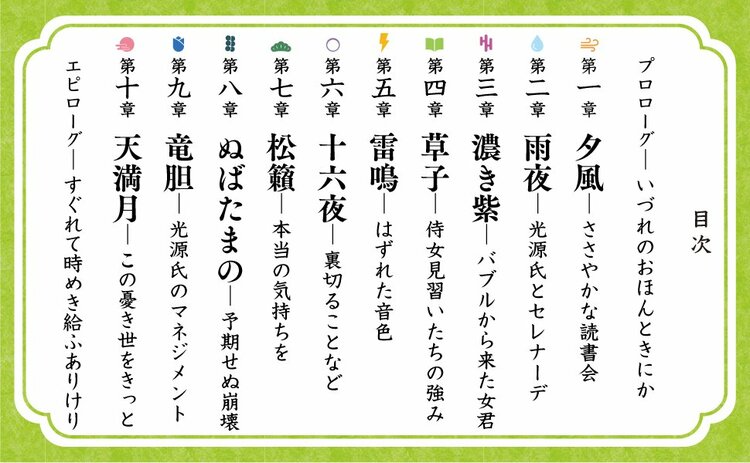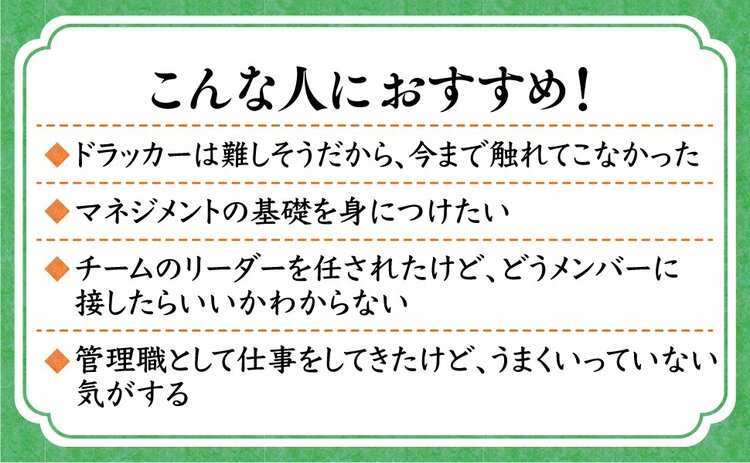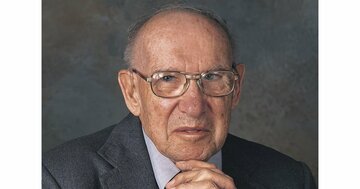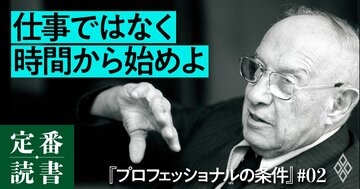遅刻の裏にある資質
「遅刻」という行動には、必ず理由がある。
たとえば、A君が会議直前まで時間を忘れてデスクで作業をしていたのなら、それは高い集中力の表れかもしれない。
取引先との電話が長引いたのなら、社交性や人間関係を大切にする資質が背景にある可能性もある。
また、複数の仕事を同時に抱えて時間感覚が曖昧になるマルチタスク抱え込みタイプかもしれないし、単に会議アラート設定に気づいていないという環境要因のケースもある。
同じ「遅刻」でも、その裏にある資質や原因は人によって異なる。
だからこそ、表面的な行動だけを見て評価を下すのではなく、「なぜそうなるのか」「どんな資質がそこにあるのか」を見極める視点が重要だ。
欠点を宝物に変えるための問い
では、どうすれば欠点に見える行動を強みに変えられるのか。
私が提案したいのは、たった一つの問いである。
◻︎「この行動の裏にある、その人らしさは何だろう?」
この問いを持つと、対応の仕方が変わる。
集中型の人には、会議の15分前に区切りをつけられるアラートや合図を用意する。
社交型の人には、会議前に雑談の時間を設けて自然に場に入れるようにする。
マルチタスク型なら、予定管理のサポートを行い、切り替えを助ける。
環境要因なら、会議の予定通知やリマインダーを整備すればよい。
そうすることで会議への遅刻という課題をクリアできるかもしれない。
しかしもっと本質的な問いである。
ドラッカーは強みを生かせ、という。
集中型の人は、文書や動画など没入して高いクオリティのものを創作する仕事が向いているかもしれない。
社交型の人は、顧客のクレームに対応したり、未然に課題をヒアリングしたりといったレベルの顧客対応が向いているかもしれない。
マルチタスク型は、全体を俯瞰してプロジェクトを進行するポジションで強みを発揮できるかもしれない。
ついつい、傲慢そうな態度に腹を立ててしまいそうになるが、ドラッカーは『経営者の条件』の『第四章 人の強みを生かす』でこうも言っている。
「人に成果をあげさせるには、「自分とうまくいっているか」を考えてはならない。「いかなる貢献ができるか」を問わなければならない。「何ができないか」を考えてもならない。「何を非常によくできるか」を考えなければならない」
見方が変われば、組織も変わる
部下の欠点を矯正することだけがマネジメントではない。
欠点の裏にある資質を見抜き、それを活かす設計をする――それこそが、組織全体の力を底上げする。
もちろん遅刻することへの指摘や指導、対応策はなさなければならない。
しかし短所だけを認識してしまうことで感情的に腹が立ち、何か良い資質の発見という、潜んでいる機会を逃してしまうかもしれない。
次に部下が遅れてきたら、深呼吸して、この問いを思い出してほしい。
◻︎「この行動の裏にある、その人らしさは何だろう?」
その瞬間、モヤモヤの向こうに、新しい可能性が見える。
そしてその視点の変化こそが、リーダーとしての成長の一歩になる。
誰かへのモヤモヤは、マネジメント能力を高める機会のサインなのかもしれない。