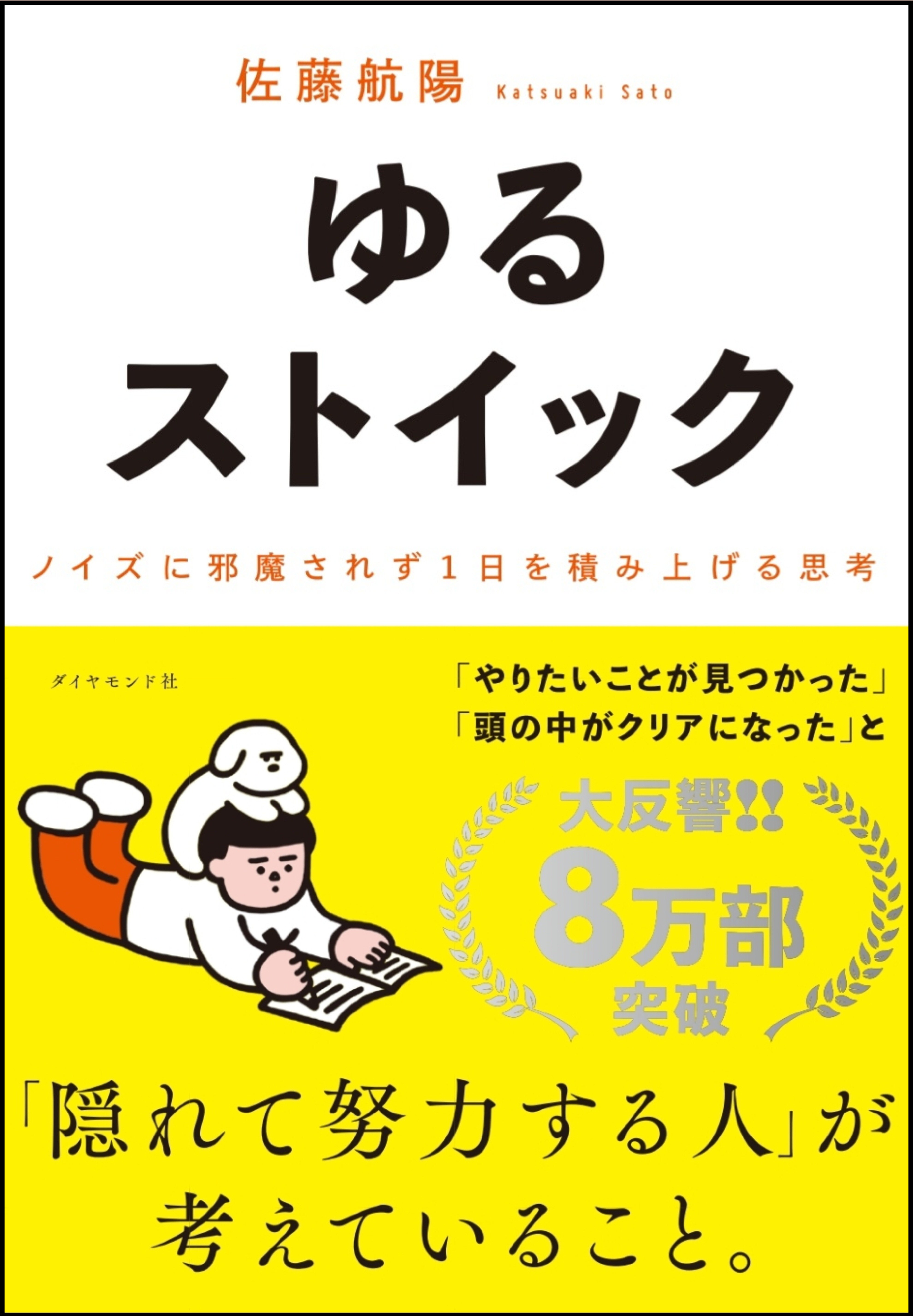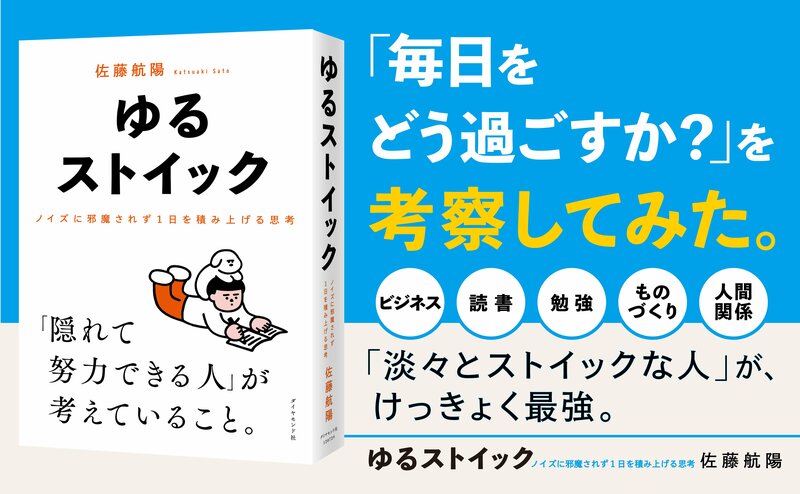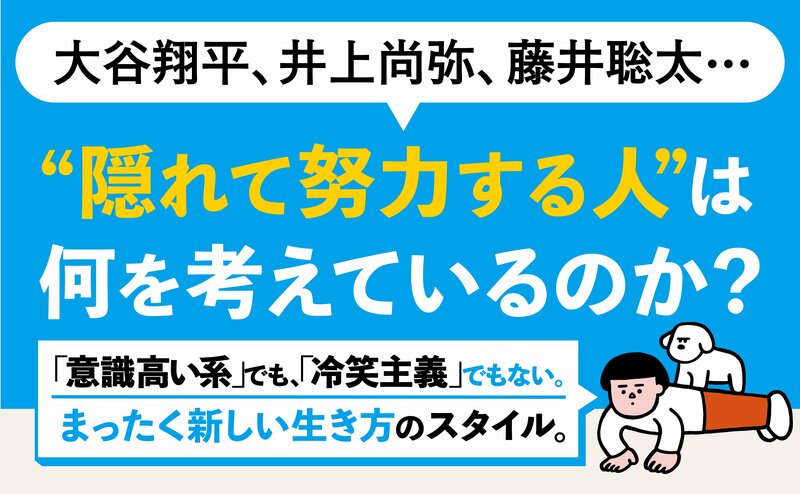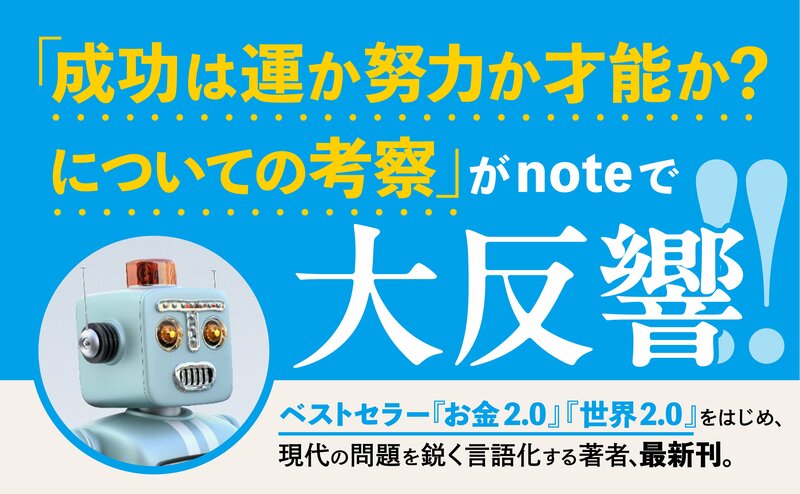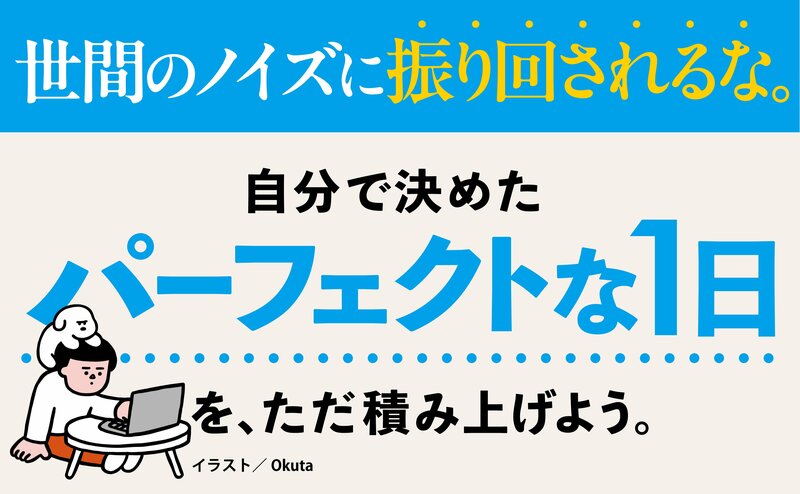呆れるほど頭が悪い人は「YouTubeやTikTokは下世話でくだらない」と語る。じゃあ、頭のいい人は?
次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。数々の成功者に接し、自らの体験も体系化し、「これからどう生きるか?」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。
コロナ後の生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち(大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…)は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。
『ゆるストイック』では、新しい時代に突入しつつある今、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、「私自身が深掘りし、自分なりにスッキリ整理できたプロセスを、読者のみなさんに共有したいと思っています」と語っている。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「伝わらない」ということへの寛容さ
言葉が期待通りに受け取られないことがあります。
その場合でも、「なぜ、伝わらないんだ!」と、相手を非難するのは視野が狭い態度です。
相手が言葉を誤解したり、内容に触れずに視覚や聴覚に基づいた反応を示したとしても、それは人間が本来持つ性質を反映しているだけです。
何万年もの間、言語に依存せずに生活してきた人類にとって、言葉が不完全なコミュニケーション手段なのは自然なことなのです。
言葉以外が大事
これからの時代、情報発信者として重要なのは、言葉だけで相手を説得しようとするのではなく、視覚や聴覚を通じたコミュニケーションの重要性を理解し、それを活用することです。
言語はあくまで「補助的」なツールです。
感覚を通じた伝達がいかに重要であるかを認識することが、より多くの人々にメッセージを届けるカギとなるのです。
インターネットが現実世界に近づきつつある
「YouTubeやTikTokは下世話でくだらない」
そう語る大人が、いまだに多くいます。
しかし、そうした見方自体が、現代の世界の理解から遠ざかっている態度です。
かつて、今の中高年が初めてインターネットに触れた頃、ネットはまだ一部のインテリやエリートだけが利用できるツールでした。
ネット上に存在するコンテンツも、必然的にそうした人々が好む「知的な内容」に偏っていました。
しかし、スマホやSNSが普及し、インターネットがすべての人に開かれたツールになると状況は一変しました。
言語は新しいコミュニケーションツールにすぎない
現在、インターネット空間は現実世界そのものに近いものとなっています。
つまり、ネットはもはや一部の知識社会に属する人々のためのものではなく、現実世界の多様性をそのまま反映する場となっているのです。
その結果、言語情報の重要性が相対的に下がり、視覚や聴覚を重視したコンテンツが主流となりました。
これはインターネット空間が「現実世界の本来の形」に近づいただけなのです。
元来、人間のコミュニケーションは視覚、聴覚、感覚を通じた伝達に依存してきました。
言語はその後に発達した新しいコミュニケーションツールにすぎません。
五感すべてを駆使する
しかし、知識社会に適応した人々は、この事実を無視してきました。
インターネットが普及し、SNSが主流になるにつれ、言語情報よりも視覚的・聴覚的なコンテンツが優勢になるのは、むしろ自然な流れと言えます。
TikTokやYouTubeでは、言語ではなく、ビジュアル、音、踊り、歌、話し方、テンポ、リズムといった要素が情報の主流となりつつあります。
これにより、特に若い世代は、視覚や聴覚の重要性を直感的に理解し、それを取り入れたコンテンツ作りをおこなっています。
文字情報だけでは伝わりにくいことを知っている彼らは、容姿や声のトーン、表情、動作など、五感すべてのあらゆる要素を駆使して情報を発信しているのです。
一方で、言語情報に頼り切ってきた層は、SNSが主流となった現代では苦戦しています。
SNS上では、言語よりも視覚や聴覚の要素が優位に立つため、言語情報だけでコミュニケーションを図るスタイルは影響力を失いがちです。
インテリ・エリート層の多くが、「質の高い言葉や丁寧な論理で語れば伝わる」と考えていますが、現実はそうではありません。
視覚や聴覚を通じた情報のほうが圧倒的に多くの人に届き、影響を与える力が強いのです。
現在のインターネットは、もはや「知識社会の延長線上」にあるわけではなく、現実社会そのものと重なりつつあります。
言語は万能ではない
この新しい環境では、言語だけに頼った情報発信は効果を失い、視覚や聴覚といった感覚に訴える方法がますます主流になっていくでしょう。
言語や論理に偏った視点を持ち続けることは、現代の情報社会での影響力を減少させるだけでなく、時代に取り残されるリスクを伴います。
このような変化を前提に「言語は万能ではない」という認識を持ち、視覚や聴覚を含む多様なコミュニケーション手段を活用することが、これからのカギとなるでしょう。
この記事もこうやって活字で書いていますが、ここまで読み進めてくれた人たちは少数派であると捉えています。
株式会社スペースデータ 代表取締役社長
1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人(Forbes 30 Under 30 Asia)に選出される。最新刊『ゆるストイック』(ダイヤモンド社)を上梓した。
また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。